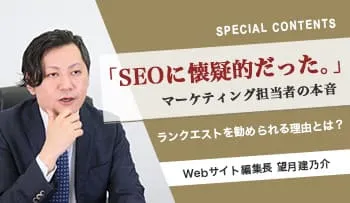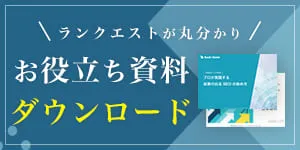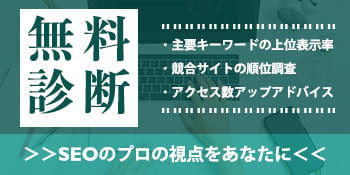最近、SEO対策の勉強を始めた方のなかには「キーワード選定」がよくわからず、途方に暮れている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
SEO=キーワードといわれるほど密接に関係しているので、確実に理解しておきたいところです。
本記事を読めば、SEOにおけるキーワードの基礎知識や選定手順、おすすめのツールも網羅できます!
SEOで成果を出したいWeb担当者の方は、ぜひ参考になさってください。
目次
SEOにおけるキーワードとは
SEOキーワードとは、Googleなどの検索エンジンでユーザーが検索する語句のことです。
この記事にたどり着いた方は、GoogleやYahoo! JAPANなどの検索エンジンで「SEO キーワード」「SEO キーワード 選定方法」などと打ち込んだのではないでしょうか。
SEOにおけるキーワードとは、まさに今、あなたが検索窓に打ち込んだ検索語句のことを指します。

SEO対策では、コンテンツを制作する前に、自社のターゲットが検索しそうなキーワードを予測・選定して、その最適解を返すためにどのような施策を行えばよいのかを考えます。
なぜなら、ユーザーにとって有益なコンテンツを作るには、まずユーザーのニーズを把握しておかなければならないからです。
たとえば「SEO キーワード」と検索したユーザーは、「SEOにおけるキーワードの意味や選定方法を理解して、自分でもSEO対策を行いたい」と考えていると推測できます。
検索キーワードから逆算してユーザーのニーズをつかみ、彼らが求めているコンテンツを用意すれば、自社サイトへの流入増加を計ることができるわけです。
関連記事:コンテンツSEOとは?導入のメリットや手順、成功事例を解説
キーワード選定を慎重に行わないとどうなる?
キーワードを適当に選んでコンテンツを制作すると、どうなるでしょう。
たとえば、多くの人が検索しそうだからという理由で検索ボリュームの大きい「SEO」をキーワードとして設定し、記事コンテンツを制作したとします。
これでは、競合サイトが多すぎて、検索結果画面に上位表示させることは難しいでしょう。
たとえ上位化に成功したとしても、自社のターゲット層と検索ユーザー層がマッチしていなければ、結果にはつながりません。
キーワード選定の工程をきちんと踏んでおくと、ターゲットのニーズに合ったコンテンツを作ることができ、結果につながるWebサイトになります。
SEOで成果を出すためには、最適なキーワード選定が欠かせません。
サイトのテーマと異なるキーワードや、検索流入が見込めないキーワードを狙ってしまうと、CVが獲得できない可能性があります。
たとえば、上位表示されても流入が増えなかったり、ターゲット以外のユーザーばかり集めたりすると、思うような成果が見込めません。
サイトのテーマとターゲットの需要を考慮しつつ、自社にとって最適なキーワードを選定しましょう。
SEO施策におけるキーワード上位化の位置
ここで注意したいのは、キーワードの上位化がコンバージョンの獲得に直結するわけではないことです。
キーワードの上位化は、あくまでもコンバージョンを獲得する手前の対策であり、コンバージョンを獲得するためには、また別の対策が必要になります。
焦らずに一つひとつ段階を踏んでいくことが、成功への道を確実なものにします。

関連記事:CRO(コンバージョン率最適化)とは?具体的な施策を3つ紹介
【よくある質問コーナー】クエリとキーワードの違い
よく聞かれる質問に「クエリとキーワードの違い」があります。
クエリはユーザーが実際に検索した語句であるのに対して、キーワードはWebサイトの運営者が広告を掲載するために設定する語句を指します。
たとえば、検索エンジンで実際に「SEO キーワード」と検索されていたら、それが検索クエリです。
その検索クエリに対して、Webサイトの運営者が広告を出稿するために「SEO キーワード選定」という語句を設定したとしたら、そちらがキーワードです。
キーワード選定は難しい?覚えておきたい4つのポイント

キーワード選定を行う前に、次の4つのポイントを押さえておきましょう。
ポイント(1)記事コンテンツを制作する目的を明らかにする
「どのような結果を得るために、記事コンテンツを制作するのか」を考えることが、キーワード選定における第一のポイントです。
コンバージョンの獲得や知名度アップなど、目的によってコンテンツの内容は異なってきます。
目的を明確にしなければ、最適なキーワードを選定することも、適切なコンテンツを制作することもできません。
まずは記事コンテンツを制作する目的を明らかにして、それを達成するためにはどうしたらよいのかを考えましょう。
ポイント(2)需要のあるキーワードを選ぶ
需要がないキーワードを選んでコンテンツを制作しても、ユーザーに検索すらされない、あるいは検索結果画面に表示されない可能性があります。
しかし、あまりに検索件数が大きいキーワードを選ぶと、競合サイトが多く、上位化が難しくなります。
まずは、競合が少なく、かつ一定の需要があるキーワードを選定するのが確実です。
ポイント(3)ターゲットとペルソナを設定する
ユーザーのニーズに合ったキーワードを選ぶためには、あらかじめターゲットとペルソナを設定しなければなりません。
ターゲットとペルソナは、似ているようで異なり、ターゲットが「集団」を指すのに対して、ペルソナは「個人」を指します。
また、それぞれの設定方法にも違いがあるので注意しましょう。
ターゲット設定では、性別や年齢、居住地域などから、自社が狙うべき「実際に存在する集団」を設定します。一般的にはターゲットを設定した後、当てはまる具体的な人物像をペルソナとして作り込みます。
一方ペルソナ設定では、性別や年齢はもちろん、趣味や興味関心、ライフスタイルなど、個人の詳細なユーザー像を作り込みます。
ペルソナは必ずしも実在する人物である必要はありませんが、限りなくそれに近い人物像を設定することが大切です。
ペルソナを作り込むとユーザーのニーズがわかり、適切なキーワードを選ぶことができます。
ポイント(4)トピッククラスターを意識する
トピッククラスターとは、Webサイトの内の記事を戦略的にグルーピングして、SEO評価を高める戦略のことです。以下2つの要素でテーマごとにグループを構成し、まとめてコンテンツを制作していきます。
|
ピラーページ |
グループの中心となるページ。対策キーワードに設定したテーマの概要や、関連する記事のリストなどを記載する。 |
|
クラスターページ |
ピラーページを補足するページ。メインテーマを深掘りした内容や、関連する話題など、メインテーマと関連性の高いコンテンツを作成する。 |
トピッククラスターを作るには、必要なキーワードを抽出した後、検索ボリュームや検索意図に応じてキーワードを仕分けします。
たとえば「SEO対策」に関するキーワードで上位表示を狙う場合、以下のようなグルーピングが効果的です。
|
ピラーページの対策キーワード |
SEO対策 |
|
クラスターページの対策キーワード |
|
上記のキーワードに応じたコンテンツをまとめて作成し、それぞれを内部リンクで適切に繋げば完成です。
トピッククラスターを作成すれば、検索エンジンがWebサイトを回遊しやすくなる、専門性が高まるなどのメリットが生まれます。
また、事前にキーワードをグルーピングして記事を制作することで、重複コンテンツやカニバリズムを防げます。ユーザーも必要な情報を探しやすくなるため、効果的なSEO対策につながるでしょう。
関連記事:トピッククラスターとは?メリットやSEO効果・作り方を解説
キーワード選定の手順

それでは、キーワード選定を行う際の流れを見ていきましょう。
手順(1)SEO施策の目的を明確にする
まずは、SEO施策の目的を明らかにするところからスタートします。
このあとに設定するメインキーワードやペルソナを決めるための指標として、施策の目的が必要になるからです。
SEO施策の目的としては、売上や知名度の向上、集客コストの削減、採用活動の効率化などがよく挙げられます。
それぞれの目的によって選定すべきキーワードも変わってくるので、途中で目的がブレることがないよう、念入りに議論を重ねておきましょう。
また、表示される語句のことを関連キーワードと呼びます。
手順(2)メイントピックとなるキーワードを決める

SEO施策の目的が決まったら、自社のWebサイトのテーマに合わせて、メイントピックとなるキーワードを選びます。
たとえばWebサイトのテーマがSEOだとしたら、メイントピックのキーワードは「SEO」となりますね。
なぜメイントピックを決めるのかというと、サブトピックのキーワードを決める際に必要になるためです。
以下の表のように、メインが「SEO」だとしたら、「SEO 方法」「SEO 独学」「SEO 費用」など、SEOに付随したキーワードをサブトピックとして選びます。
【メイントピックとサブトピックのキーワードの例】
|
自社のWebサイトのテーマ |
メイントピックのキーワード |
サブトピックのキーワード |
|
SEO |
SEO |
SEO 方法 |
この方法であれば、Webサイトのコンテンツにまとまりが出るうえ、記事同士を内部リンクでつなぎやすくなり、サイト内の回遊性を高められます。
まだこの段階ではサブトピックのキーワードは選定しませんが、メイントピックをあらかじめ準備しておくと、のちの作業を効率よく進められますよ。
手順(3)競合サイトが対策しているキーワードを洗い出す
3つ目の手順はランクエスト独自の方法ですが、今回特別に公開いたします!
弊社では、メイントピックのキーワードを決めたあと、Ahrefs(エイチレフス)とよばれるツールを使って競合サイトのURLで対策されているキーワードを調べます。
Ahrefsとは、SEOの被リンク分析・競合調査ができる有料SEO分析ツールのことです。
自社のWebサイトだけではなく、競合サイトの分析もできる便利なツールです。
競合サイトのURLを洗い出す目的としては、上位化しているWebサイトが対策しているキーワードを対策することで、上位化を目指しやすくなるためです。
また、上位化しているWebサイトに含まれているコンテンツを網羅しつつ、独自性のあるコンテンツを制作する際にも、競合研究が役立ちます。
手順(4)ペルソナを設定する

「キーワード選定の際に押さえておきたいポイント」でも触れたペルソナの設定は、この段階で行います。
ペルソナを設定しておくと、自社のターゲットではないユーザーが流入するのを防ぎ、確実に自社のターゲットに対して刺さるコンテンツを作成できます。
なお、ペルソナはメイントピックのキーワードごとに設定するのがポイントです。
キーワードごとにユーザーの特性や状況が異なるので、それぞれに適切なペルソナを設定しなければ、顧客のニーズをうまくつかめない可能性があるためです。
メイントピックが複数ある場合は、必ずキーワードごとにペルソナを設定しましょう。
手順(5)ペルソナに合うサブキーワードを抽出する
メイントピックのキーワードごとにペルソナを設定したら、サブトピックとなるキーワードをリストアップします。
このとき、以下の3つの手順を踏みましょう。
【サブトピックのキーワードをリストアップする手順】
- 過去にコンバージョンに至ったキーワードを洗い出す
- 競合他社のコンテンツで上位表示されているキーワードを分析する
- 周辺キーワードを追加する
サブトピックのキーワードを選定するには、すでにコンバージョンが発生したキーワードの洗い出しから始めます。
コンバージョンが発生したのであれば、ユーザーが今後も同じキーワードで検索する可能性が高いからです。
このとき、計測ツールの「GA4(Googleアナリティクス4)」と「Googleサーチコンソール」を使うのが便利です。
まずGoogleアナリティクス4でコンバージョンが発生しているWebページを探し、Googleサーチコンソールで、そのページが何というキーワードで検索(流入)されているのかを調べます。
2つ目の手順では、競合他社のコンテンツを分析して、上位化されているキーワードを抽出します。
「Ahrefs(エイチレフス)」や「Semrush(セムラッシュ)」などを使うと、競合他社のWebページを簡単に分析することが可能です。
最後に、Googleのサジェスト機能を利用して、周辺キーワードを押さえておくことも大切なポイントです。
たとえば、Googleの検索窓に「SEO」と打ち込むと、「SEOとは」「SEO 対策」「SEO キーワード」などの関連キーワードが出てきます。
ここで見られるキーワードは、ユーザーが検索する頻度の高いものなので、サブトピックのキーワードとして選定しておきましょう。
また、関連キーワードは「Googleキーワードプランナー」を活用して調べることもできます。
手順(6)月間平均検索ボリュームを確認する
「Googleキーワードプランナー」を使って、リストアップしたキーワードが1か月のあいだにどのくらい検索されたのかを確認しましょう。
検索ボリュームが大きければ多くの流入数を見込めますが、そのぶん競合サイトも増えて、検索結果画面に上位表示させるのが難しくなります。
また、あまりに検索ボリュームが小さくても、効果を期待できません。
そこで、検索ボリュームを確認して、リストアップしたキーワードがどのような位置にあるのかを確認することが大切なのです。検索ボリュームごとにキーワードを仕分け、コンテンツ制作の優先順位や対策のスケジュールを決めましょう。
手順(7)リストアップしたキーワードを潜在層・顕在層に分類する
ここまでで洗い出してきたキーワードを、潜在層・顕在層に分類します。
たとえば「SEO キーワード」で検索するユーザーは、自社にとって潜在層なのか、顕在層なのかを考えてみましょう。
顕在層であれば、SEOのキーワードに関しての知識をある程度持っている、あるいは検索する必要がないと考えられるため、この場合は潜在層に分類します。
このように、抽出したキーワードをユーザー層ごとに一つひとつ分類していきます。
手順(8)潜在層から対策開始!
先ほどの工程で潜在層に分けられたキーワードをリストアップしたら、キーワード選定の完了です!
なぜ潜在層のほうから対策するのかというと、顕在層に比べて上位表示させる難易度が中~低程度である傾向があるためです。
検索結果の上位に上げやすいキーワードから対策すれば、Webサイトの評価も高まり、多くのユーザーの流入を狙うことができます。
アクセスが集まりWebサイトの評価が向上してきたら、検索ボリュームが多い顕在層狙いのキーワードも対策していきましょう。上位表示に成功すれば、更に多くの流入を獲得できます。
初心者向け!おすすめのキーワード選定ツール

先ほどのキーワード選定の手順で少しご紹介しましたが、キーワード選定を行うには、専用のツールを使う必要があります。
そこで、おすすめのキーワード選定ツールをご紹介します。
Googleキーワードプランナー
Googleキーワードプランナーは無料で使えるキーワード選定ツールで、SEO対策を行ううえで欠かせない存在です。
特定のキーワードやWebサイトの関連キーワードを調べることができるほか、キーワードの検索ボリュームや入札単価を調べることも可能です。
どのくらいのユーザーの流入数を見込めるのか、上位表示させるにはどのくらいの難易度なのかを調べるのに役立ちます。
参照: Google 広告 ヘルプ -キーワード プランナーを使う
Googleサーチコンソール
自社Webサイトを訪れるユーザーが、どのキーワードで検索して来ているのかを調べる際は、Googleサーチコンソール、通称「サチコ」を使います。
狙ったキーワードで検索結果に表示されているのかをチェックできるほか、競合サイトにはどのようなキーワードでユーザーが流入しているのかを確認することもできます。
また検索順位や表示回数、クリック数、クリック率なども無料で確認できるため、ぜひ活用しましょう。
参照: Search Console ヘルプ -Search Console の概要
Googleトレンド
Googleトレンドは、キーワードの検索回数の推移を調べることができるツールです。
たとえば「クリスマスプレゼント」というキーワードの検索回数を調べてみましょう。

10月から徐々に上がり始めて、12月にピークを向かえ、12月25日以降はほとんど検索されていないことがわかります。
これにより読者のニーズがつかめるようになり、コンテンツを制作・公開するタイミングを計ることができます。
参照:Google トレンド
ラッコキーワード
ラッコキーワードは、関連キーワードの抽出や、競合サイトの洗い出しを行う際に役立ちます。
検索画面に調べたいキーワードを打ち込むだけで、関連キーワードのリストが表示されるほか、競合サイトの見出し(hタグ)を抽出することも可能です。

これらの機能は無料で利用できますが、月間検索数は有料プランに入らなければ表示されません。
検索数を確認する際は、関連キーワードをコピーして、Googleキーワードプランナーに貼り付けると確認できます。
参照:ラッコキーワード|無料のキーワード分析ツール(サジェスト・共起語・月間検索数など)
再検索キーワード調査ツール
再検索キーワードは、ユーザーが最初に訪れたページを離脱した後に、改めて検索したキーワードを指します。ユーザーが求めている顕在的なニーズ情報だけでなく、潜在ニーズも把握できます。
再検索キーワードはGoogleの検索結果から調べられますが、「再検索キーワード調査ツール」を使用すれば、容易に分析できます。
使用するには、開発者の柏崎剛氏がX(旧Twitter)で毎週日曜日に発信するパスワードが必要です。
参照:再検索キーワード調査ツール – 検索意図や潜在ニーズを抽出
Ubersuggest
Ubersuggest(ウーバーサジェスト)は、検索ボリュームやSEO難易度、クリック単価、サジェストキーワードを調査できるツールです。
特定のキーワードに関する多くの情報を抽出できるため、SEO対策はもちろんキーワード選定の際にも役立ちます。
また、自社サイトのURLを登録すれば、アクセス数や検索順位の追跡、サイトの修正点も確認できます。
ohotuku.jp
ohotuku.jpは、指定したキーワードのサジェストやSEO難易度、月間検索ボリュームを簡易的に調査できるツールです。
抽出したキーワードは、コピペして自社で管理することも可能です。またチェック履歴も残せるため、次回以降もデータを見返せます。
Googleキーワードプランナーを使用せず、検索ボリュームやSEO難易度、サジェストを調査したい場合に適しています。
aramakijake
aramakijake(アラマキジャケ)は、GoogleとYahoo!JAPANの月間推定検索ボリュームを調査できるツールです。会員登録不要なので、初心者にもおすすめです。
ただし、検索ボリュームが数十回程度のキーワードはデータを取得できません。スモールキーワードの検索ボリュームが知りたい場合は、Googleキーワードプランナーを推奨します。
参照:キーワード検索数チェックツール|無料SEOツール aramakijake.jp
SEOチェキ!
競合サイトを調査した上でキーワードを選定したい場合は、SEOチェキ!が適しています。
競合サイトのURLを入力するだけで、タイトルやディスクリプション、コンテンツ内で使用されるキーワードを取得できます。その他、キーワードの出現頻度や検索順位、インデックス数の確認も可能です。
競合サイトを簡易的に分析したい方は、ぜひ活用してみてください。
Yahoo!知恵袋
ユーザーの検索意図を深掘りする際は、Yahoo!知恵袋が最適です。
検索窓に特定のキーワードを入力すれば、それに関連するユーザーのリアルな悩みが表示されます。具体的な悩みからユーザーの求める情報をイメージできるので、キーワード選定だけでなくペルソナを設定する際にも役立ちます。
rishirikonbu
rishirikonbuは、候補キーワードや関連キーワードの検索数を予測するツールです。
アクセス数だけでなく、1位取得時の月間アクセス数の予測や、キーワードの出現場所まで調査してくれます。対策するキーワードの優先順位まで決められるため、キーワードの選定の効率化が図れるツールです。
参照:関連語・候補キーワード一覧抽出ツール | 無料SEOキーワード選定ツール集 rishirikonbu.jp
SEOキーワードの種類と分類方法

検索キーワードは、実にさまざまな方法で分類でき、どの方法を使うのかも自由に決められます。
ここからは、いくつかのキーワード分類方法をご紹介します。
なお、キーワードとクエリという2つの言葉が出てくるので、おさらいしておきましょう。
キーワードとは、Webサイトの運営者が選定する語句のこと、クエリとは、ユーザーが検索窓に打ち込む語句のことです。
先述した「【よくある質問コーナー】クエリとキーワードの違い」でもご紹介しているので、ご参照ください。
分類方法(1)検索数ごとに分ける(ビッグ・ミドル・スモールキーワード)
SEOのキーワードは、その検索数ごとにビッグキーワード・ミドルキーワード・スモールキーワードに分類できます。
ビッグキーワードは、3種類のなかでもっとも検索数が多く、ミドル、スモールの順に少なくなっていきます。
たとえば「SEO」のように、1つのキーワードのみで検索されるものはビッグキーワードです。
「SEO キーワード 代行会社 東京」のように、キーワードが具体的になるほど検索数が少なくなるため、これらはミドルワード・スモールキーワードに分類されます。
ビッグキーワードは多くのユーザーに検索してもらえる可能性があるものの、ライバルが多いため、上位表示が難しくなります。
まずはミドルキーワード・スモールキーワードを上位化させることを狙うのが、SEO対策を成功させる秘訣です。
それぞれのキーワードについて、以下で詳しく解説していきます。
ビッグキーワード
ビックキーワードは、「SEO対策」「Webサイト制作」「Webマーケティング」などの検索ボリュームが多いキーワードのことです。
一般的に検索ボリュームが10,000以上のキーワードが、ビッグキーワードに分類されます。検索数が多いため、上位表示できれば多くのアクセスが見込めます。
一方で競合が多い、検索意図が見えづらいなどの理由から、上位表示が難しいキーワードです。
たとえば「SEO対策」で検索しているユーザーは、以下のようなさまざまなニーズを持っていると考えられます。
- SEO対策の概要が知りたい
- SEO対策を専門会社に依頼したい
- SEO対策を自社で行う方法が知りたい
- 現在行っているSEO対策の改善点が知りたい
上記のニーズにすべて対応するには、概要を網羅的に紹介したコンテンツが必要です。1つ1つの内容を深掘りするのが難しいため、コンバージョンへ誘導するのが難しい傾向にあります。
ただし、上位表示できれば自社の認知向上はもちろん、アクセスの向上による間接的なSEO効果も期待できます。
上位表示に時間がかかるため、SEO対策の初期段階では優先度は低いです。しかしある程度、成果が出てきたタイミングで必ず対策しましょう。
ミドルキーワード
ミドルキーワードは、検索ボリュームがビッグキーワードとスモールキーワードの中間に位置するキーワードです。一般的に1,000〜10,000程度の検索ボリュームのものが該当し、以下2つの特徴があります。
- ユーザーニーズが汲み取りやすい
- 競合が少ない
ミドルキーワードは「SEO対策 やり方」「SEO対策 効果」など、複合キーワードが多く、ニーズが汲み取りやすいです。そのためユーザーが満足する、コンバージョンにつながりやすいコンテンツを作成できます。
また、ビッグキーワードよりも競合が少なく、比較的上位表示しやすい点もメリットです。アクセス数も少なくないため、SEO対策の初期〜中期においてメインで対策するキーワードになります。
スモールキーワード
スモールキーワードは、検索ボリュームが少ないキーワードのことです。一般的に検索ボリュームが1,000以下のキーワードが該当します。
ミドルキーワードと同じ特徴を持ちますが、競合がより少ないため上位表示が容易です。
1記事のアクセス数は少ないですが、多くのスモールキーワードで上位表示できれば、効果的に集客できるようになります。
SEO対策では、Webサイトの認知を広げてアクセス数を伸ばしたり、被リンクを獲得したりすることも重要です。
そのため、SEO対策の初期段階では、スモールキーワードから対策し、地道にアクセス数を伸ばすようにしましょう。
分類方法(2)検索意図ごとに分ける(Know・Do・Go・Buyクエリ)
ユーザーの検索意図によってキーワードを分類する場合は、以下の4つの種類に分けます。
【検索意図分類表】
|
分類 |
概要 |
キーワード例 |
|
Knowクエリ |
「知りたい」というニーズのキーワード |
SEO とは |
|
Doクエリ |
「何かをしたい」というニーズのキーワード |
Webコンテンツ 作り方 |
|
Goクエリ |
「行きたい」というニーズのキーワード |
株式会社eclore アクセス |
|
Buyクエリ |
「買いたい」というニーズのキーワード |
新幹線 予約 |
上記のように、ユーザーのニーズに合わせてキーワードを分類すると、コンテンツ制作の方向性が明確になります。
以下で一つずつ見ていきましょう。
knowクエリ【知りたい】
Knowクエリは、ある情報を知りたい方や、解決方法を探している方が検索するキーワードです。
「SEOとはどういうもの?」「SEO対策を行うメリットとは?」といった疑問を解決したいというユーザーの検索意図があるものが分類されます。
Doクエリ【何かをしたい】
Doクエリとは、何かのやり方や行う際のポイントなどを知りたいユーザーが検索するキーワードを指します。
「Webコンテンツを作りたいから方法が知りたい」「商品レビューを書きたいけれど、書き方がわからない」といった、行動に結びつくキーワードであれば、Doクエリといえます。
Goクエリ【行きたい】
検索した場所に行きたいという意図のキーワードを、Goクエリといいます。
ユーザーは「○○株式会社へのアクセス方法を知りたい」「お店の住所がわからない」といった意図で検索するため、その答えを返せるコンテンツを用意しておく必要があります。
Buyクエリ【買いたい】
Buyクエリは、検索したキーワードの商品やサービスを買いたいと思っているユーザーが検索するキーワードです。
ユーザーには「新幹線のチケットを予約・購入したい」「パソコンを買いたいから人気ランキングが知りたい」といったニーズがあります。
分類方法(3)成約率の高さで分類する(指名・購入・情報検索キーワード)
成約につながる可能性の高いキーワードを分類したい場合は、以下のような種類に分けることもできます。
指名検索キーワード
指名検索キーワードは「Amazon」や「楽天市場」など、企業名そのものを検索して、そこで購入しようという購買意欲の高いユーザーが使うキーワードで、成約率1位を誇ります。
自社の企業名やECサイト名で検索してもらうためには、この指名検索キーワードを対策していく必要があります。
購入検索キーワード
先ほどの検索意図ごとに分類する方法でご紹介した「Buy」と同じ種類に分類されるキーワードです。
指名検索に次いで2番目に成約率が高く、多くの企業がこのキーワードで対策しています。
情報検索キーワード
情報検索キーワードは、検索意図ごとのキーワードの種類でご紹介した「Know」と同様に、疑問を解決したいと思ったユーザーが使うキーワードです。
全検索数の約8割を占めており、多くのユーザーの流入を狙えますが、企業にとってお金にならないというイメージが先行し、見過ごされる傾向があります。
【ランクエストオリジナル】キーワードの分類方法

ここまでは、一般的によく使われているキーワードの分類方法をご紹介しました。
ランクエストでは、独自の分類方法を採用しています。
それは、キーワードを潜在層と顕在層に分けてから、さらに検索数の多いものと少ないものに分類するというやり方です。
理由としては、潜在層かつ、月間検索回数が少ないキーワードを抽出する目的があるためです。
潜在層のほうが、顕在層に比べて検索順位を上げる難易度が低いことは先ほどご紹介しましたが、さらに検索数の少ないキーワードに分類することで、上位化を狙います。
また、検索数の少ないキーワードであれば、検索数の多いキーワードを包括することもできるため、結果としてはビッグキーワードの対策を行うことにもなるのです!
キーワードを選定する際の注意点
キーワードを選定する際は、以下の3点に注意してください。
- キーワードの選定・見直しを継続的に実施する
- キーワードは表で管理する
- 検索順位を定期的に確認する
キーワードは一度選定したら終わりではありません。継続的なSEO効果を得るためにも、必ず実践しましょう。
キーワードの選定・見直しを継続的に実施する
キーワードの選定や見直しは、3か月に1度を目安に実施しましょう。
なぜなら、コンテンツを作成する中で、キーワードの対策範囲が変わったり、現状より最適なキーワード候補が出たりする可能性があるからです。
具体的には、一つのコンテンツで複数キーワードの検索上位を獲得できた場合、他のキーワードで新規ページを作成する必要がなくなります。
また、コンテンツを作り続ける限り、キーワードは必ず枯渇します。よいキーワードを見つけるためにも、継続的な追加選定や見直しが必要になるでしょう。
キーワードは表で管理する
膨大な数のキーワードを選定していると、どのキーワードでコンテンツを作成したのかがわからなくなる場合があります。
そのような事態を避けるためにも、選定したキーワードはExcelやスプレッドシートなどの表形式ツールで管理しましょう。
キーワードだけでなく、検索ボリュームや順位、公開日、リライト実施日を併せて記載するとより効果的です。表で管理することで、データの再検索や順位も容易にチェックできます。
検索順位を定期的に確認する
キーワードを選定しコンテンツを公開した後は、検索順位を定期的に確認しましょう。
公開して間もないうちは、週に1回の頻度でチェックすると次に取るべきアクションを明確にできます。
コンテンツは一度作って終わりではありません。ユーザーの検索ニーズは日々変化しますし、キーワードに関連する新情報がリリースされる場合もあります。
また、公開から数か月経っても検索順位の上昇が見込めない場合は、内容を改善する必要があるでしょう。
キーワードに関する情報や検索順位の傾向を見て、リライトしたり、新規コンテンツを追加したりするなど、必要に応じた対策を講じましょう。
ダメ絶対!キーワード乱用

コンテンツ内にキーワードを不自然なかたちで何度も登場させて上位化を狙うのは、おすすめできません。
Google検索セントラルの「Google ウェブ検索のスパムに関するポリシー」にも、以下のような記載があります。
キーワードの乱用とは、Google 検索結果のランキングを操作する目的で、ウェブページにキーワードや数字を詰め込むことです。キーワードの乱用では、不自然にリストやグループの形式を使ったり、関連性のない場所でキーワードが記載されたりする傾向があります。
引用元:Google検索セントラル「Google ウェブ検索のスパムに関するポリシー」
不自然にキーワードを連呼すると、Googleからスパムだと認識される可能性があります。
せっかくコンテンツを制作しても上位化できなくなるため、あくまでユーザーにとって有益な記事を意識して、自然な流れでキーワードを組み込みましょう。
選定したキーワードで対策する際のポイント
ここまで、キーワード選定に関する情報を主にご紹介してきましたが、SEO対策をする際に押さえておきたいポイントについても軽く触れておきましょう。
ポイント(1)タイトルの左側にキーワードを含める
タイトルは、Webページが検索結果に表示される際に利用される重要な要素です。対策キーワードを含めれば、ユーザーが自身の検索意図との関連性を感じやすくなるため、クリック率が向上します。
タイトルにキーワードを含める際は、ユーザーの目に入りやすいよう、できるだけ左側に配置するのがおすすめです。
ただし、日本語がおかしいと不信感を抱かれるため、自然な文章になるように工夫しましょう。
ポイント(2)h1タグには必ずキーワードを入れる
Webページは、すべてHTML(Hyper Text Markup Language)という言語によって構成されています。
HTMLとは、文章の構成や役割を指示するために使う言語のことで、検索エンジンに対してWebページがどのような内容なのかを伝えます。
このときに使うのが「タグ」です(メタ要素やメタ情報、メタタグ、メタデータなどともよばれます)。
文字に意味を与える印のような役割を担っており、文字をタグで囲むと、見出しや箇条書き、リンクであることを検索エンジンに認識させられます。
SEO対策においては、見出しタグ(h1~h6)のなかに対策キーワードを設定するのが基本です。
h1はタイトル、h2~6は見出しを設定する際に使い、文字が若いものほど大きな見出しになります。
タイトルであるh1には必ずキーワードを入れ、h2には必要に応じて適度に入れておきましょう。
hタグは、数字に応じて以下のような意味を持ちます。
|
h1 |
大見出し |
|
h2 |
中見出し |
|
h3 |
小見出し |
|
h4〜h6 |
超小見出し |
一般的にh1タグにはタイトル、h2タグに内容ごとのメインの見出し、h3タグにはh2の内容を補足する見出しを設定します。
h4〜h6タグは、h3タグをさらに補足する内容がある際に使用します。
しかし、階層構造が深くなりすぎるのはSEO的に良くないと言われているため、h4タグまでに留めるのが無難です。
中でもh1タグとh2タグは、タイトルと同じように検索結果に表示されることがあります。そのため、h1タグには必ずキーワードを含め、h2タグにも適度に入れ込みましょう。
たとえば「SEO キーワード 選び方」が対策キーワードだとしたら、以下のようにキーワードをはめ込みます。
【見出しタグの設定例】
<h1>SEOのキーワードの選び方とは?徹底解説</h1> (タイトル)
<h2>SEOのキーワードを選ぶ手順</h2> (見出し2)
<h3>手順(1)目的を明確にする</h3> (見出し3)
<h3>手順(2)メイントピックを決める</h3> (見出し3)
無理にキーワードを入れると乱用と判断されてしまうので、h1に必ず入れたら、あとは必要に応じてわかりやすいかたちで入れるよう心がけてくださいね。
なお、見出しの書き方については、以下の記事で詳しくご紹介しています。
関連記事
ポイント(3)ディスクリプションの文頭にキーワードを入れる
ディスクリプションとは、検索結果画面でタイトルの下に表示されるテキストのことです。
ユーザーは、検索画面でこのテキストを見てWebサイトの内容を判断します。
そのため、ディスクリプションを作る際は、なるべく文頭のほうに対策キーワードを持ってくるのが理想です。
「この記事には知りたいことが書いてありそう」という印象を持ってもらえます。また、ディスクリプション内に検索キーワードと一致する文字列がある場合、太字で表示されます。

ユーザーに効率的に記事の関連性をアプローチできるため、クリック率の向上も期待できるでしょう。
ポイント(4)本文中にキーワードを使う場合は自然なかたちで組み込む
本文にも程よくキーワードを入れておきたいところです。
ただ、対策キーワードに関する記事を書いていれば、自然と本文中でキーワードを使うことになるため、そこまで強く意識する必要はありません。
意識して書くと不自然な使い方になってしまい、ユーザーにストレスや不信感を与える原因になります。
滞在時間の減少によりSEOに間接的な悪影響を与えたり、コンバージョン率が低下したりする恐れがあるため注意が必要です。
また、過剰にキーワードが詰め込まれているページを、Googleはスパムとみなします。ペナルティの対象になるため、自然な文章を心がけましょう。
関連記事:SEOスパムとは?Web担当者が把握したいリスクや対策を解説
ポイント(5)キーワードによって対策するWebページを変える
キーワードによって対策すべきWebページは異なるため、注意しなければなりません。
たとえば対策キーワードが「歯医者 新宿」だとしたら、まずはGoogleで検索してみます。
すると、歯医者さんのWebサイトのTOPページがずらっと出てきます。
つまり、「歯医者 新宿」のキーワードはTOPページで対策したほうが上位化しやすいということがわかりますね。
また「歯 正しい磨き方」と検索してみると、今度はコラムページがたくさん出てきます。
ということは、「コラムページで対策するのがよさそうだな」とわかるわけです。
このように、キーワードによって上位化しやすいWebページは異なります。
試しに検索してみて、出てくるのがどのようなページなのかを確認しましょう。
ポイント(6)キーワードは1ページにつき1個に絞る
キーワードを選定する際、一つのコンテンツに関連キーワードを多く入れれば、SEOによい影響が加わるのではないかと考える方もいるでしょう。
しかし、基本的には1コンテンツにつき1キーワードがルールです。
一つのコンテンツにキーワードを詰め込みすぎると、伝えたい情報やターゲットがブレてしまい、かえって集客効果が低下します。
キーワードからユーザーが必要な情報だけを厳選し、1つ1つを深掘りして書いたほうが良い効果が得られます。
もし、関連情報を詳しく説明したい場合は、別でコンテンツを作成し、内部リンクで繋ぐなどの工夫がおすすめです。キーワードを盛り込むことはせず、伝えたい情報を統一しましょう。
ポイント(7)重複している記事がないか確認する
コンテンツ制作で起こりやすいミスとしてあげられるのが、既存ページとの重複です。
たとえば、以下3つは異なるキーワードですが、いずれもSEO対策の方法について記載したページが上位表示されています。
- SEO対策 やり方
- SEO対策 初心者
- SEO対策 自分で
気づかずにコンテンツを作成すると、似た内容のページが複数出来上がります。無駄な人件費の発生に加え、Googleからの評価が分散する可能性もあるため注意が必要です。
自社サイトの中で足を引っ張り合うこととなり、SEO対策のリソースが無駄になってしまいます。もし、対策キーワードと同じ内容の記事が既に存在している場合、リライトをする、削除して新しく書き直すなどがおすすめです。
コンテンツ制作の前に、キーワード同士の関連性や検索結果、既存の記事を確認し、重複が起こらないようにしましょう。
選定したキーワードを盛り込むべき場所は?
ユーザーの検索意図を正しく理解した上でコンテンツを作成すれば、キーワードは自然と適切な位置に盛り込まれるでしょう。しかし、最低限押さえておくべき場所はあります。
- タイトル
- メタディスクリプション
- 見出し
- 本文
それぞれ見ていきましょう。
タイトル
タイトルはコンテンツ内でユーザーが最初に目にする要素で、検索結果画面にも表示されるため、キーワードの挿入が必須です。
タイトルの文頭にキーワードを配置することを意識しましょう。後半にキーワードを配置すると、文字数の関係から表示が難しくなったり、ユーザーに認知されないリスクがあります。
文字数の目安はデバイスによって異なりますが、PCは29文字、モバイルは30〜35文字です。
なお、キーワードを入れたいからといって、不自然な文章をタイトルに採用するのは注意が必要です。ユーザーが何に関する記事か理解できなくなり、クリック数や流入数の低下につながります。キーワードを入れつつも、読みやすく自然な文章を設定しましょう。
関連記事:SEO効果を高めるタイトルの付け方とポイントを解説
メタディスクリプション
メタディスクリプションは、検索結果画面でタイトルの下に表示されるコンテンツの要約文です。
ユーザーがコンテンツを閲覧するかどうかの判断材料になるため、適切なキーワードが設定されていれば、クリック数や流入数の増加につながります。
メタディスクリプションもタイトルと同様、PCで120文字、モバイルで80文字と検索結果画面で表示される文字数が制限されています。
キーワードを前半に入れながら、コンテンツの内容をわかりやすくまとめるよう意識しましょう。
関連記事:ディスクリプションとは?SEOに効果的な書き方と設定方法を解説
見出し
すべての見出しにキーワードを配置する必要はありませんが、h2見出しには意識的に入れるようにしましょう。その際に注意したいのが、キーワードを意識しすぎるあまり、機械的で不自然な見出しになることです。
|
不自然な見出し |
適切な見出し |
|
<h2>選定したキーワードを盛り込むべき場所は? |
<h2>選定したキーワードを盛り込むべき場所は? |
ユーザーに読みにくい印象を与えるため、ページ離脱につながる恐れがあります。ユーザビリティを第一に考え、端的でわかりやすい見出しを設定しましょう。
本文
コンテンツ本文にもキーワードを入れるように心がけましょう。
メインとなるキーワードはもちろん、サジェストや再検索キーワード、共起語などが含まれているか、公開前に確認します。
しかし基本的には、ユーザーの検索意図を理解した上でコンテンツを作成できていれば、意識せずともキーワードは自然に含まれます。
キーワード選定・対策に関するよくある質問

ここからは、キーワード選定においてよくある質問をご紹介します。
Q. 1つのキーワードで複数の書き方がある場合はどうしたらいいの?
たとえば「ねこ」というキーワードは、「猫」「ネコ」とも書けますよね。
このように、ひらがな・漢字・カタカナと表記方法が複数ある場合は、それぞれの検索ボリュームを調べて、大きいものを選びましょう。
Q. いきなりビッグキーワードで対策したらいけないの?
ビッグキーワードから対策を始めても、なかなか成果が出ない可能性が高いため、あまりおすすめできません。
また、ビッグキーワードを包括したテイルキーワード(スモールキーワード)を対策すれば、ビッグキーワードで対策することにもなり、一石二鳥です。
Q. 並び順を組み替えたキーワードも対策したほうがいいの?
たとえば「SEO キーワード」と2語以上のキーワードを選んだ場合は、順番を入れ替えた「キーワード SEO」でも検索して、検索結果画面が変わるのかどうかを確認しましょう。
ほとんど変わらないのであれば、同じキーワードと考えても問題ありません。
しかし、両者の検索結果がかなり異なる場合は、それぞれ別のキーワードとして考え、別々にコンテンツを作成する必要があります。
Q. マニュアルのように決まった対策方法はないの?
キーワードの対策方法は、千差万別です。
その企業によって対策方法は違いますし「これが正解!」とは言い切れないのが、SEOの奥深いところです……。
本記事で書いたランクエストでの方法も、絶対に正しいとは言い切れませんが、これまでの実績を鑑みて、成功した例が多かった方法をご紹介しています。
Q. ペルソナは絶対に設定したほうがいいの?
ペルソナを設定する・しないは自由に選択できますが、設定したほうが上位化しやすいといえます。
せっかく汗水たらしてコンテンツを制作しても、ターゲットに刺さらなければ、思ったような効果がでないかもしれません。
ペルソナ設定は難しい作業ですが、挑戦してみてくださいね。
Q. 1つの記事に複数のキーワードで対策してもいいの?
対策する検索キーワードは、1記事につき1つにするのがおすすめです。
キーワードによってユーザーの検索意図が異なるため、複数にすると確実にユーザーに刺さるコンテンツを作るのが難しくなります。
複数のキーワードを対策したい場合は、それぞれの検索キーワードごとにコンテンツを用意して、それぞれの記事を内部リンクでつなげるのも有効です。
キーワード選定を極めてWebページの上位化を成功させよう

本記事では、SEOにおけるキーワードの基礎知識や選定の手順、おすすめのツールなどをご紹介しました。
Webページを上位表示させるためには、適切なキーワードを選定することが重要です。
SEO対策を行う目的に合わせて、ターゲットとペルソナを設定し、ユーザーのニーズにマッチするキーワードを選びましょう。
とはいっても、初めてでは難しいことも多々あるかと思います。
そんなときは、弊社のSEOサービス、ランクエストの無料診断からご相談ください。
ランクエストでは、お客様の課題や状況に合わせた最適なプランをご提案いたします。