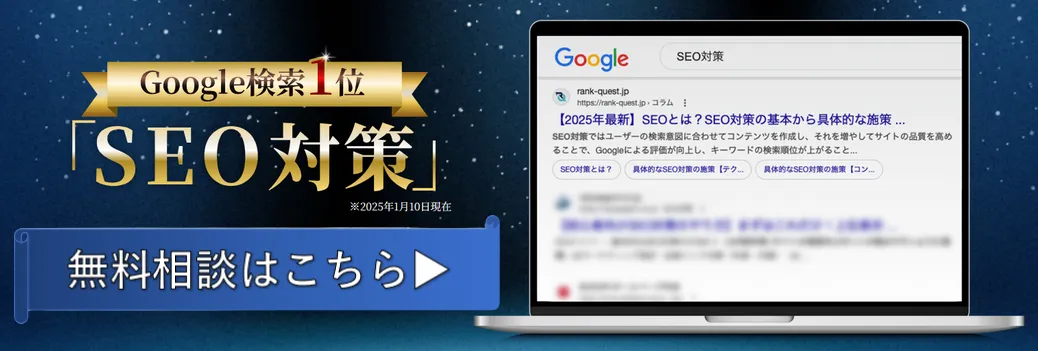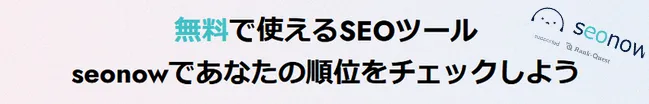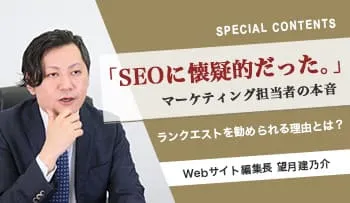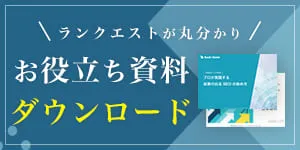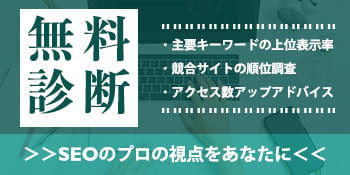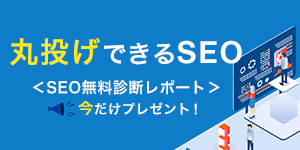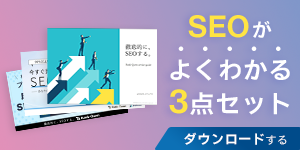「上位化にはテクニカルSEOが重要と聞いたことがあるけど、何をするのかはよくわからない」と疑問に思っている方もいらっしゃるでしょう。
“テクニカル”と聞くと一見難しそうですが、ご安心ください!
実は今日からでも実施できる対策なのです。
本記事では、テクニカルSEOの概要や対策方法などをご紹介します。
テクニカルSEOへの理解を深めて、サイトを上位化させたいとお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次

今すぐ無料で、
あなたのSEO対策費用を
シミュレーション!
簡単な質問に答えるだけで、
最適なSEOプランと費用が無料でわかります。

SEO対策を
行ったことはありますか?

テクニカルSEOとは
テクニカルSEOは、検索エンジンをターゲットにしたSEO対策の総称です。
Webサイトの情報を検索エンジンに正確に伝えるために、サイトの内部構造を整備するテクニカル(技術的)なSEO対策なので、こう呼ばれています。
検索エンジンに正しいかたちでサイトを認識してもらうのは上位化の第一歩であるため、サイトを運営するうえでテクニカルSEOは欠かせない施策の一つです。
テクニカルSEOはなぜ重要なのか

テクニカルSEOは、検索エンジン最適化において欠かせない要素です。その重要性は検索エンジンによるサイトの評価と、ユーザーの検索行動との密接な関係にあります。
テクニカルSEOは、いわばサイトの基礎工事のようなものです。クローラーがサイトをスムーズに巡回し、コンテンツを正確に理解できるように環境を整えるのが役割です。
たとえばサイトの構造を整理し、内部リンクを適切に配置するなどの施策は、クローラーがすべてのページを効率良く巡回できるよう促します。
またページの読み込み速度を改善や、モバイル端末への対応強化などでUX(ユーザーエクスペリエンス)が向上すると、検索エンジンからの評価も上がります。
なおテクニカルSEOが不十分だと、サイトは検索エンジンから低い評価を受けるため注意が必要です。
検索結果の下位に表示されたり、一部のページが表示されないといった事態も起こり得ます。またサイトへの流入が減少するため、PVやCVRにも影響を与えるでしょう。
サイトの評価を高め検索流入を最大化するためには、テクニカルSEO対策が必要不可欠です。
テクニカルSEOとコンテンツSEO の違い
意味
テクニカルSEOとコンテンツSEOは、どちらも検索エンジン最適化(SEO)につながる手法ですが、目的が大きく異なります。
テクニカルSEOは、いわばサイトの「土台作り」です。検索エンジンがサイトを正しく理解し評価できるように、サイトの技術的な部分を最適化します。
一方、コンテンツSEOはサイトの「中身」を充実させる施策です。ユーザーが求める良質なコンテンツを提供し、上位表示を狙います。
テクニカルSEOはサイトの技術的要素の面で、コンテンツSEOは良質なコンテンツの作成でSEO効果を高めます。
ターゲット
テクニカルSEOとコンテンツSEOは、どちらも検索エンジン最適化(SEO)を目標としていますが、ターゲットが異なります。
テクニカルSEOのターゲットは、検索エンジンのクローラーです。クローラーがサイトを正確に評価できるように、サイトの技術的な部分を最適化します。
具体的には、サイトマップの作成やサイト構造の整理といった、クローラーがスムーズにサイトを巡回できるように促す施策です。
一方、コンテンツSEOは検索エンジンを利用するユーザーに焦点を当てています。ユーザーの検索意図を満たす良質なコンテンツを提供し、サイトへの流入を増やすのが狙いです。
具体的には、ブログ記事の作成や製品ページの充実などがコンテンツSEOに該当します。
つまりテクニカルSEOは検索エンジンの仕組みが対象で、コンテンツSEOは検索エンジンを利用するユーザーが対象のSEO手法です。
方法
テクニカルSEOとコンテンツSEOではそれぞれ意味や目的が異なるため、下記のように対策も異なります。
|
テクニカルSEOの対策方法 |
コンテンツSEOの対策方法 |
|
|
テクニカルSEOは、サイトの技術的要素を整えるのが役割です。そのため、XMLサイトマップの作成やモバイルフレンドリー化といったクローラーに焦点を当てています。
一方、コンテンツSEOはユーザーを目的としたSEO施策です。記事の構成や見出しの最適化など、いずれもユーザーに焦点を当てた手法になっています。
難易度
テクニカルSEOとコンテンツSEOの難易度ですが、それぞれ特徴があるため一概にどちらの方が難しいとは断言できません。
|
テクニカルSEOの特徴 |
コンテンツSEOの特徴 |
|
|
HTMLやプログラミングの知識があれば、テクニカルSEOはさほど難しいとは感じないでしょう。初期段階の難易度は高めですが、その後は安定した状態を維持できます。
一方、文章作成が得意ならコンテンツSEOが取り組みやすいでしょう。ただし継続的に良質なコンテンツを提供する必要があるため、長期的な対策が求められます。
テクニカルSEOの6つのメリット
テクニカルSEOには、SEO対策初心者の方でも実行しやすいというメリットがあります。
次で詳しく解説しますので、参考にしてみてください。
メリット①必要な施策が明確である
テクニカルSEOは、Googleが公開している「Google検索の基本事項(旧ウェブマスターガイドライン)」で手法が明らかになっています。
そのため、どのような施策を打つべきか試行錯誤する必要がなく、すぐに実践しやすいのがメリットです。
「Google検索の基本事項(旧ウェブマスターガイドライン)」は、こちらから確認できます。
参照:Google「Google検索の基本事項(旧ウェブマスターガイドライン)」
ご自身のWebサイトと照らし合わせて、足りない点を確認してみましょう。
メリット②施策の効果がわかりやすい
施策の効果がデータで明確に把握できるのも、テクニカルSEOのメリットの一つです。
効果を確認するには、Googleが提供している「Googleサーチコンソール」などの解析ツールを使用します。
ツールでは、クローラーの巡回やインデックスの状況などを閲覧することができるので、現状をすぐに把握して、今後の対策に役立てられます。
メリット③クローラビリティが良くなる
テクニカルSEOの最大のメリットは、クローラビリティの改善につながることです。
クローラビリティとは、検索エンジンのクローラーがサイトをスムーズに巡回し、コンテンツを正確に把握できる度合いを指します。
テクニカルSEOでサイトの構造をシンプル化したり、XMLサイトマップを作成したりといった対策を施すことで、クローラーが迷わずにサイト内を巡回できるようになります。
サイトの階層構造が複雑だと、クローラーはどのページを優先的に巡回すべきか判断できません。スムーズに巡回できないことで、重要なページを見落とす恐れもあります。
テクニカルSEOでクローラビリティを効率化すれば、サイトの評価が高まり検索結果の上位に表示にもつながります。
クローラビリティの改善は、サイトの土台を作るテクニカルSEOにとって最大のメリットと言えるでしょう。
メリット④アクセシビリティが良くなる
テクニカルSEOは、アクセシビリティの改善にも効果的です。アクセシビリティが向上すれば、検索エンジンからの評価も高まり上位表示されやすくなります。
たとえば画像の最適化やCSS/JavaScriptの圧縮などは、読み込み速度が改善するためアクセシビリティの向上に効果的です。
テクニカルSEOもアクセシビリティも、最終的にはユーザーの利便性向上につながるため、Googleからの評価も高まります。
なぜなら「Googleが掲げる10の事実」にもある通り、SEO対策の根本はユーザーファーストにあるためです。
テクニカルSEO対策は検索エンジンにサイトを正しく評価してもらうだけでなく、アクセシビリティの向上にもつながるのが利点です。
メリット➄ユーザビリティが良くなる
テクニカルSEOはサイトの使いやすさ、つまりユーザビリティの改善にも効果的です。
たとえばレスポンシブデザインの実装は、スマートフォンやタブレットなどのデバイスでサイトが最適に表示されるよう調整します。
テクニカルSEOでレスポンシブデザインを実装すれば、ユーザーは自身のデバイス環境に左右されず、快適にサイトを閲覧できます。
ユーザビリティの向上でユーザー体験が改善されると、結果的にサイト評価が高まりPVやCVRにも好影響を与えるでしょう。
メリット⑥重要なページがランクインしやすくなる
テクニカルSEO対策により、検索エンジンがサイトの最も重要なページを正確に特定しやすくなり、上位表示する可能性が高まります。
たとえば複数のURLで同じ内容のページが公開されている場合、検索エンジンはどのページを正規のページとして扱うか判断に迷うことがあります。
そこで有効なのがcanonicalタグを挿入し、重要なページを指定する手法です。検索エンジンに「このページを正規のページとして扱ってください」と指示を出すのが目的です。
つまり正規URLを明示することで、検索エンジンが該当ページを探しているユーザーに対し関連性が高い情報を採用しやすくなります。
ユーザーの検索意図を満たす重要なページがランクインすれば、結果としてGoogleにも評価されるでしょう。
テクニカルSEOの2つのデメリット
テクニカルSEOにはメリットだけではなく、以下のようなデメリットも存在します。
- 難易度の高い施策がある
- コンテンツの量を確保しなければいけない
テクニカルSEOは初期段階での設定が複雑で、専門知識がないと取り組みにくいのが課題です。では、それぞれのデメリットを詳しく見ていきましょう。
難易度の高い施策がある
テクニカルSEOは下記のように初期段階での作業が多く、難易度は比較的高めです。
- XMLサイトマップの作成・送信
- robots.txtの設定
- ページの読み込み速度の改善
- モバイルフレンドリー化
- 内部リンク構造の最適化
- HTTPS化
- 構造化データの導入
- 重複コンテンツの対策
- URL構造の最適化 など
いずれも一般知識では対応が難しい作業が多くあります。一度設定すればその後は安定した運営を維持できますが、初期段階の難易度が高いのがデメリットです。
コンテンツの量を確保しなければいけない
検索エンジンは、ユーザーの検索意図を満たす高品質な情報を豊富に含んだサイトを高く評価します。
そのためテクニカルSEOに着手する前には、まずサイトのコンテンツ量を確保しなければなりません。
コンテンツ量が豊富だと、 検索エンジンがサイトを「ユーザーの求める情報を網羅している」と判断します。
コンテンツ量が少ないとユーザーの役に立たないサイトだと判断され、検索結果の上位に表示されにくくなります。
テクニカルSEOの着手のためには、土台となるコンテンツを固めなければならないことを覚えておきましょう。
テクニカルSEOを構成する3つの対策要素

テクニカルSEOは、「クローラー対策」と「インデックス対策」に大別されます。
クローラー対策とは
クローラー対策とは、クローラーがWebサイト内を回遊しやすくなるように環境を整えることを指します。
サイトやページがインデックスされるためには、クローラーの巡回が必須なので、しっかりと対策しなければなりません。
関連記事:クローラー(Crawler)とは?上位化のための対策を紹介
インデックス対策とは
クローラーが巡回してきたときにWebサイトの情報を正しく認識してもらえるよう、内部情報を改善するのが、インデックス対策です。
検索エンジンにアプローチするための施策ですが、結果的にはユーザーにとっても使いやすいサイト作りに貢献します。
関連記事:Googleインデックス登録とは?登録方法やリクエスト方法を徹底解説
ページエクスペリエンス対策とは
ページエクスペリエンスとは、ユーザーがサイトを訪問した際に感じる体験の質のことです。ページエクスペリエンスの良し悪しは、検索ランキングの評価基準に影響します。
ページエクスペリエンスを高めるためにはページの読み込み速度を改善し、安全な閲覧環境をユーザーに提供しなければなりません。
具体的には画像の最適化やコードの圧縮、HTTPS化などです。いずれもページの表示速度の改善と安全性を高めるため、ページエクスペリエンスの向上につながります。
6つのクローラー対策
ここからは、クローラビリティを向上させるための対策を、6つ紹介します。
URLの正規化
同じ内容のコンテンツが複数ある場合は、URLを一つにまとめて正規化する必要があります。
なぜなら、クローラーが重複した内容のコンテンツを巡回してしまうと、ほかのページのクロールが遅れる可能性があるためです。
正規化の方法としては、サイトマップに正規ページのURLを設定したり、重複しているページに正規ページを表示させるコードを入力したりすることが挙げられます。
サイト階層構造を最適化する
サイト階層構造の最適化は、クローラーの巡回効率を上げるため効果的な手法です。
検索エンジンのクローラーは、サイトを満遍なく巡回して情報を収集します。階層構造がシンプルであれば、その分クローラーは効率良くサイト内を巡回できるのです。
またクローラーだけでなく、ユーザーにとっても階層構造がシンプルであるほど、目的のページに辿り着きやすくなります。
クローラーにサイト内の情報をより正確に把握させるためにも、シンプルかつ分かりやすいサイト構造を目指しましょう。
簡潔なURL名にする
テクニカルSEOにおいて、URLの簡潔化は推奨される手法の1つです。ただし、単に簡潔化するのではなく、検索意図と関連性のある単語を含めるのがポイントです。
|
URLを簡潔化するおもな理由 |
URLを簡潔化する際の注意点 |
|
|
URLの簡潔化には多くにメリットがあり、検索エンジンにもユーザーにも効果的です。検索意図と関連のあるキーワードを含み、分かりやすいURL名を作成しましょう。
URL にローマ字表記や日本語を使わない
Googleの検索エンジンはURLの単語を英語として判断します。そのため、URLにローマ字表記や日本語を使うのは推奨されません。
たとえば「ノートパソコン」なら、「no-to-pasokoonn」ではなく「laptop-pc」(laptopだけでも可)と英語で記載します。
ローマ字や日本語の表記は検索エンジンに誤解を与える恐れがあるため、英語表記に統一しましょう。
2単語以上はハイフンを付ける
2単語以上の長い単語は、ハイフンを付けて区切りましょう。URLではスペースが使えないため、ハイフンで区切るのが一般的です。
前述のノートパソコンで例を紹介するなら、「新型ノートパソコン」であれば「new-laptop -computer」や「new-laptop」などと記載します。
これで検索エンジンが、「新型ノートパソコン」であると正しく認識します。
不要なパラメータを削除する
URLに含まれる不要なパラメータは削除し、URLを簡素化しましょう。不要なパラメータを防ぐことで、クローラーの認識向上につながります。
繰り返しになりますが、URLはターゲットキーワードを含むシンプルかつ分かりやすいものにすべきです。
意味のない単語や記号などは削除し、クローラーやユーザーが分かりやすいURLを作成しましょう。
絞り込みパラメータを含むURLを robots.txtでブロックする
robots.txtは絞り込み検索の質を高める効果があり、重要なページにクローラーを集中させやすくなります。
たとえば大規模なECサイトでは、商品やカテゴリーの組み合わせにより無数のURLが生成されます。
そのため、すべてのページをクローラーに巡回させると効率が悪く、重要なコンテンツへのアクセスが遅れてしまうのです。
クローリングするURLをrobots.txtで減らせば、検索エンジンへのインデックス反映が早まり重要なページが優先的にクロールされるようになります。
robots.txtはサイトの規模が大きくなるほど、その効果を発揮するツールと言えるでしょう。
ページ表示速度(コアウェブバイタル)を改善する
テクニカルSEOにおいて、ページ表示速度(コアウェブバイタル)の改善は効果的です。
Googleはページ表示速度を検索ランキングの重要な要素としており、ページ表示速度が速いサイトは検索結果の上位に表示されやすくなります。
ページ表示速度の改善に有効な対策は、おもに以下の通りです。
|
コアウェブバイタルに有効な対策 |
効果 |
|
画像の最適化 |
画像サイズの圧縮や、適切なフォーマットの選択で画像の読み込み時間を短縮できる |
|
JavaScriptとCSSの最適化 |
不要なコードの削除や外部ファイルの分割により、レンダリング時間を短縮できる |
|
サーバーの高速化 |
サーバーのスペックの向上やキャッシュの活用で、ページの応答時間を短縮できる |
|
コンテンツの軽量化 |
ページに不要な要素を削除し、ページのサイズを縮小する |
コアウェブバイタルの改善はユーザー体験の向上だけでなく、検索ランキングの向上にもつながるため積極的に取り組みましょう。
クロールエラーの確認と対策
クロールが巡回した際にエラーが発生すると、ページがインデックスされません。
クロールエラーの有無は、Googleサーチコンソールで簡単に確認することが可能です。
さらに、サーチコンソール内の「ページがインデックスに登録されなかった理由」という項目を見れば、エラーの原因も把握することができます。
サーチコンソールトップ(サマリー)>インデックス作成「レポート全体」から確認ができます。

原因が判明しだい対策し、再度インデックスのリクエストを送りましょう。
ソフト404エラーを改善する
テクニカルSEOにおいて、クローラーに対して行う重要な対策の1つにソフト404エラーの解消があります。
ソフト404エラーとは、存在しないページにアクセスした際に、サーバーの正常動作を示すHTTPステータスコード200を返してしまう現象です。
一見すると問題ないように思えますが、検索エンジンのクローラーはエラーページを有効なページと誤認するため、無駄なクロールを繰り返してしまう恐れがあります。
エラーを防ぐためには存在しないページにアクセスされた場合に、HTTPステータスコード404を返し、専用の404エラーページを表示するような設定が必要です。
クローリングする必要のないにページに何度もアクセスするのは、効率的とは言えません。ソフト404エラーを解消すれば、クローラーが重要なページに集中できるようになります。
リンク切れを改善する
リンク切れ(デッドリンク)の改善は、テクニカルSEOにおいて有効な手法です。
リンク切れが起きるおもな原因は、過去に公開していたページが削除やURLの変更、外部リンク切れなどです。
検索エンジンは、リンク切れが多いサイトを低品質と判断する傾向があります。サイトの評価を高めるためにも、リンク切れのチェックは重要です。
リンク切れは 「dead-link-checker.com」などの無料ツールでも、簡単にチェックできます。定期的にサイトをチェックし、リンク切れを無くすようにしましょう。
【関連記事】
Googleにインデックスされない原因と対処法を解説
Googleにクロールをリクエストするタイミングや手順を解説
Googleのクロール頻度とは?確認方法や仕組みを解説
XMLサイトマップ・内部リンクの活用
XMLサイトマップの活用も、クローラビリティを向上させる方法の一つです。
XMLサイトマップとは、Webサイトのページの内容をクローラーに伝えるファイルのことで、クロールやインデックスを促すのに役立ちます。
ファイルでクロールに伝えられる情報は、各ページのURLや優先度、最終更新日や更新頻度などです。
サイトマップは、XMLタグとURLで構成されているため、コードに不慣れな方には難解に見えますが、自動作成できるのであまり構える必要はありません。
「WordPress」のプラグインや、自動生成ツールなどで簡単な設定を済ませるだけで作成できるので、一度試してみましょう。
【関連記事】
サイトマップはSEO対策に必須!作成・確認方法をわかりやすく解説
内部リンクのSEO効果とは?最適な設置方法も紹介
モバイルフレンドリーへの対応
モバイルフレンドリーとは、スマートフォンをはじめとするモバイル端末からでも、Webサイトを快適に閲覧できるようにすることです。
2015年より、Googleのアルゴリズムに追加され、モバイルフレンドリーに対応すると検索順位が上がるようになりました。
また、Webサイトをスマートフォンで閲覧するユーザーが増加しているため、ユーザーにとって魅力的なサイトにするためにも重要な要素と言えます。
スマートフォンで見やすい文字サイズへの変更、CTAボタンの大きさの調整などを実施し、モバイルフレンドリーへの対応を目指しましょう。
自身のサイトが対応できているかどうかは、Googleが提供する「モバイルフレンドリーテスト」という無料ツールで確認できます。
関連記事:モバイルフレンドリーとは?対応方法やSEOへの影響を解説
10個のインデックス対策
ここからは、インデックスされたあとに上位化するための7つ対策を紹介します。
タイトルの改善
タイトルを設定する際は、対策キーワードをできる限り文頭に入れ込み、文字数を30文字以内に抑えましょう。
ユーザーは検索結果画面に表示された各コラムのタイトルを全文読むことはほとんどありません。
そこで、文頭にキーワードの入った完結な文言にすることで、ユーザーの目に留まりやすいよう工夫する必要があるのです。
ユーザーに自分の求めている情報が載っていると思ってもらえれば、クリック率が向上します。
また、クリック率が上がることで、検索エンジンからもキーワードに合ったコンテンツとして認識されるため、検索順位も上がる可能性があります。
関連記事:SEO効果を高めるタイトルの付け方とポイントを解説
見出しの改善
見出しというのは、記事の内容のまとまりごとに設定されたタイトルのことで、「h2」や「h3」といったタグをつけて設定されます。
見出しを改善するポイントは、タイトル同様、対策キーワードが先頭に来るように調整することです 。
ただし、こちらには文字数制限はありません。
また、目次で見出しを見ただけで、どのような内容が書いてあるのかわかるようにすると、ユーザーに読んでもらいやすくなります。
サイトの滞在率や読了率が上がれば、高品質なコンテンツと見なされて検索順位の向上にもつながります。
関連記事:SEOに強い!効果のある見出しの書き方のポイント12選
キーワードを設定する
テクニカルSEOにおけるインデックス対策の一環として、キーワードの設定は重要な役割を果たします。
たとえば「SXO」というキーワードで検索上位を目指したいとします。この場合、単に「SXO」の言葉がページ内に含まれていれば良い訳ではありません。
タイトルタグや見出しタグなど、検索エンジンが注目する箇所へ「SXO」というキーワードを適切に配置する必要があります。
検索エンジンがページ内容を正確に理解するためには、キーワードの設定が欠かせません。
なぜならキーワードを参考に検索エンジンはページと検索クエリとの関連性を評価し、より関連性の高いページを検索結果の上位に表示するためです。
ただし過度なキーワードの詰め込みは、検索エンジンからペナルティを受ける可能性があります。自然な文章の流れの中で、ユーザーに有益なキーワードを適切に配置しましょう。
メタディスクリプションタグを設定する
メタディスクリプションタグの設定は検索エンジンにページの内容を正確に伝え、ユーザーのクリック率を上げる重要な要素です。
メタディスクリプションとは、検索結果に表示されるページの説明文を指します。メタディスクリプションは検索エンジンがページの内容を理解するうえで、重要な手がかりです。
また検索エンジンだけではなく、ユーザーが検索結果からどのページをクリックするかを決める際にも影響を与えます。
たとえば「Webライター」というキーワードで検索した場合、上位サイトのメタディスクリプションには「初心者」や「副業」などのキーワードが多く見受けられます。
これらのキーワードはユーザーの検索意図であり、その検索意図を満たすキーワードを意識的に盛り込んでいるためです。
メタディスクリプションは検索結果に表示される際に、ユーザーの目に触れる最初の情報となります。
魅力的なメタディスクリプションを作成すれば、ユーザーのクリック意欲を高めサイトへの流入を増やせます。
リンク設置方法の改善
コンテンツ内にリンクを設置する際は、適切なアンカーテキストと、リンクが切れたときの対応を用意しておかなければなりません。
アンカーテキストとは、リンク先の内容を表す文章のことです。
ユーザーはもちろんのこと、クローラーもアンカーテキストを読み取ってリンク先が適切かどうかを判断するので、手を抜かずに書きましょう。
また、貼りつけたリンクが切れたときのために、404エラーや301リダイレクトも設定しておきます。
404エラーは、遷移先のページが存在しないことを示すもので、通常は発生するとユーザーの離脱率が上がってしまいます。
しかし、オリジナルの404エラーページを作成し、別ページに誘導する文章を差し込むことで、エラーが出ても離脱を防げるのです。
301リダイレクトは、サイトのURLを更新した際に必要になる転送処理です。
設定しておくと、ユーザーが古いURLにアクセスしようとした場合、自動で新URLに遷移させてくれます。
さらに、既存ページの評価を新規ページに引き継ぐ役割もあるため、検索エンジンの観点からも重要な意味があります。
画像設置方法の改善
画像の設置方法一つとっても、インデックス対策を意識する必要があります。
アイキャッチとして挿入する画像に、商品名やキャッチコピーなどのテキストを盛り込んでいる方は多いのではないでしょうか。
しかし、画像にテキストが含まれていると、クローラーが情報を正しく認識しづらくなってしまいます。
テキストは画像内ではなく、HTMLタグで構成するようにしましょう。
また、クローラーは画像のファイル名からも画像の情報を読み取ろうとします。
その際にファイル名にローマ字が含まれていると、英語として読み取られ、キーワードとの関連性を認識してもらえません。
ファイル名は英単語をハイフンで区切った形式で書くと、適切に認識されます。
クローラーは、imgタグのalt属性に記載されている説明文も、画像の理解に利用しています。
そのため、画像の内容をわかりやすくalt属性に記述するのもインデックス対策として効果的です。
関連記事:画像のSEO対策9選!最適なデータ形式や注意点も解説
重複コンテンツの確認
外部のWebサイトとコンテンツ内容が被っていると、Googleにコピーコンテンツと判断され、評価が下がってしまいます。
定期的に似たコンテンツがないかリサーチしたり、コンテンツを更新したりして、差別化を図りましょう。
自社サイト内でも似たコンテンツを量産していると、コピーだと判断される可能性があるので、コピペチェックツールで一致率を確認してからアップロードするのがおすすめです。
構造化データの実装
構造化データとは、クローラーのサイトに対する理解を手助けするデータ形式のことです。
構造化データを設定することを「構造化マークアップ」といい、設定しておくとWebサイト内の情報をクローラーに正確に把握してもらえるようになります。
たとえば、コンテンツ内に更新日の日付を記載していても、構造化マークアップをしていなければ、その日付は更新日としてクローラーに認識してもらえません。
構造化することで初めて、ただのテキストではなく更新日として情報を受け取ってもらえるのです。
ほかに構造化マークアップしたほうがよい情報の例としては、商品ページやFAQページ、サイト内に掲載している動画などが挙げられます。
構造化が成功すると、リッチリザルトとして検索結果画面のトップに表示されることもあり、SEO的に大きな効果を発揮できます。
なお、構造化ができているかどうかは、Googleが提供するツール「リッチリザルトテスト」を利用すると簡単にわかるのでお試しください。
参考:Google「リッチリザルトテスト」
インデックス登録エラーの確認と対応
せっかく新規ページをアップロードしても、うまくインデックスされないケースがあります。
一定時間が経ってもインデックスが確認できない場合は、Googleサーチコンソールでインデックス登録エラーを確認してみましょう。
エラーに関する情報は、メニュー画面「カバレッジ」から閲覧できます。
「エラー」という項目をクリックするとエラーの発生日が、「詳細」という項目を押すとエラーした原因が見られるので、それぞれ確認してみてください。
なお、エラーの原因には以下のようなものが考えられます。
エラーの例
- URLがGoogleに登録されていない
- robots.txtにブロックされている
- noindexタグにより除外されている
- ページにリダイレクトがある
エラーを確認したら迅速に対処し、インデックスを再リクエストしましょう。
必要に応じてnoindexタグを設定する
noindexタグで特定のページをインデックスから除外することは、テクニカルSEOにおいて効果的な手段です。
検索エンジンのクローラーは、noindexタグが付与されたページをインデックス対象外と判断します。これにより無駄なクローリングを減らし、クローラーの効率化を図れるのです。
また低品質なページや一時的なページなどをインデックスから除外すれば、検索結果の質が向上しUXも改善します。
- 重複コンテンツ
- 一時的なページ
- 内部検索結果ページ
- ログイン後のページ
- 低品質なページ
上記のようなページがあれば、必要に応じてnoindexタグを設定すると良いでしょう。
6つのページエクスペリエンス対策
ページエクスペリエンス対策を、6つ紹介します。
- インタースティシャル広告の扱い
- 常時SSL化(https化)の設定
- パンくずリストや目次を設置する
- サイト設計に基づいたカテゴリーを設計する
- サイトに最適なUXパターンを選択する
- サイト内検索を実装する
コンテンツSEOにおいて、ページエクスペリエンス対策はサイトの評価を高める重要な要素です。では、1つずつ詳しく見ていきましょう。
インタースティシャル広告の扱い
インタースティシャル広告の適切な扱いは、ページエクスペリエンス対策において重要です。
「Google検索セントラル」においても、下記のようにインタースティシャル広告について言及しています。
多くのモバイルページが、テキストやコンテンツを拡大しなくても読みやすくなっている一方で、煩わしいインタースティシャルが表示されるページを見かけることも多くなっています。元々のコンテンツはページ上に存在しており、Google によるインデックス登録も可能ですが、視覚的にはインタースティシャルによって覆い隠されてしまうことがあります。検索結果をタップしたのに、すぐには期待していたコンテンツにアクセスできないということで、ユーザーもイライラするでしょう。
インタースティシャル広告が表示されるとユーザーは目的のコンテンツを見るまでに時間がかかり、ストレスを感じやすくなります。
結果としてサイトから離れてしまい、離脱率が高まる可能性があるでしょう。ユーザー体験の悪いサイトは、検索結果の下位に表示される傾向にあります。
インタースティシャル広告は表示頻度を減らしたり、表示タイミングを工夫するなどしてユーザーのストレスにならないようにしましょう。
常時SSL化(HTTPS化)の設定
常時SSL化(HTTPS化)の設定も、ページエクスペリエンス対策において有効な手法です。
常時SSL化によりサイトとユーザー間の通信が暗号化されるため、情報漏洩のリスクが大幅に減少します。
ユーザーが安心して個人情報を入力したり、オンラインショッピングを楽しめるためサイトの信頼度向上につながるでしょう。
またGoogleは、HTTPSのサイトをより高く評価する傾向にあります。
導入コストや設定作業はある程度必要ですが、長期的な視点で見ればサイトの信頼性や検索順位の向上につながります。未設定の場合は導入を検討しましょう。
パンくずリストや目次を設置する
パンくずリストや目次の配置も、SEO施策において効果的です。検索エンジンがサイトの構造を深く理解するためには、パンくずリストや目次の設定が欠かせません。
パンくずリストは、現在のページがサイト内のどこに位置しているのかを階層構造で示すものです。
パンくずリストがあることで、ユーザーはサイト内での現在地を把握しやすくなります。また検索エンジンにとっても、サイトの構造を把握するための手がかりとなります。
目次も同様にページ内の情報を整理し、ユーザーが目的のセクションに素早くアクセスできるようにするものです。
さらにパンくずリストや目次内のリンクは、サイト内の関連するページを繋ぎ内部リンク構造を強化します。
内部リンクの最適化は検索エンジンにもユーザーにも効果的な施策のため、ページエクスペリエンス対策としても有効です。
サイト内にパンくずリストや目次を適切に配置し、検索エンジンにもユーザーにもしいサイト設計を目指しましょう。
サイト設計に基づいたカテゴリーを設計する
テクニカルSEOにおけるページエクスペリエンス向上のためには、サイトの設計段階からコンテンツのカテゴリーを適切に分けるべきです。
たとえば「SEO」をテーマとしたサイトを構築する場合、関連するキーワードとして「SEO 被リンク」「SEO アンカーテキスト」といった細分化されたテーマが考えられます。
これらのキーワードで作成されたコンテンツは、それぞれが属する適切なカテゴリーに分類しましょう。
なぜならサイト設計に基づいたカテゴリーに配置することで、ユーザーが目的の情報をよりスムーズに探し出せるためです。
またユーザーだけではなく、検索エンジンもカテゴリー分けされたサイトの方が構造を正確に理解できます。さらに各ページとの関連性が把握しやすいのも、メリットです。
なお関連性の高いコンテンツをまとめれば、情報の整理が容易になりサイトの管理もしやすくなるでしょう。
サイトに最適なUXパターンを選択する
多くのユーザーが慣れ親しんでいるUXパターンを採用することで、ユーザーはサイトを直感的に操作でき、ストレスなく情報を取得できます。
使いやすいUXパターンはユーザーの滞在時間にも影響するため、サイトに長く滞在することで検索エンジンからの評価も高まります。
またすでに実績のあるUXパターンを導入すれば、ゼロからデザインする手間が省けるため開発期間を短縮できるでしょう。
サイトの目的(情報提供、ECサイトなど)や扱うコンテンツの特徴に応じて、ユーザーにとって使いやすいUXパターンを選択しましょう。
サイト内検索を実装する
サイト内検索の実装はユーザーの利便性の向上につながるため、ページエクスペリエンス対策として効果的です。
サイト内検索でキーワードを入力すれば、ユーザーが目的の情報に対し迅速にアクセスできるようになります。
またサイト構造が複雑な場合でも、サイト内検索を実装すればユーザーが迷わずに目的のページを見つけられるでしょう。
なおサイト内検索の結果ページには、関連性の高いページへのリンクが貼られます。内部リンク構造が強化されるため、検索エンジンからの評価向上にもつながります。
テクニカルSEOの進め方のコツ
テクニカルSEOの進め方のコツを、4つ紹介します。
- クローラー対策から始める
- 検索インデックスを確認しながら進める
- チェックリストを活用する
- 効果測定する
では、それぞれ詳しく見ていきましょう。
クローラー対策から始める
テクニカルSEOを進めるうえで、最初にすべきことはクローラー対策です。
ページがインデックスされるためには、検索エンジンがサイトをクローリングしなければなりません。
検索エンジンが正しくサイトをクローリングできるよう、まずはクローラー対策から始めましょう。
具体的にはリンク階層を浅くしたり、XMLサイトマップを設置するなどのクローラー向けの対策に着手します。
サイトのクローリングが正しく実行されたら、次はインデックスの最適化に取り組みます。
検索インデックスを確認しながら進める
Googleサーチコンソールを使い、サイト内のページが正しくインデックスされているかを確認しましょう。
Googleサーチコンソール内のURL検査にて、インデックスされているかどうかすぐに分かります。
この時URLを正規化したり、重複コンテンツを無くすといったインデックス向けの対策も並行して実施すると効果的です。
チェックリストを活用する
テクニカルSEOを効率よく進めるために、チェックリストを活用しましょう。対策する項目をリストアップし、チェックリストをもとに1つずつ項目を改善します。
以下のように項目ごとに分けて、細かくチェックリストを作るのがポイントです。
|
チェック項目 |
実施内容 |
|
クローリングとインデックスに関する項目 |
|
|
ページの表示速度に関する項目 |
|
|
モバイルフレンドリーに関する項目 |
|
|
構造化データに関する項目 |
|
|
セキュリティに関する項目 |
|
|
その他 |
|
上記の項目のすべてを一度に実施するのは難しいため、自社サイトの現状をもとに優先順位を付けて改善しましょう。
効果測定する
チェック項目をもとに対策を実行したら、その後の効果測定も合わせて実施します。効果測定の結果をもとに、改善に必要な項目を洗い出しましょう。
テクニカルSEOに限らず、新しい取り組みを実行する際にはPDCAサイクルを回すのが基本です。検証と改善を繰り返し、ユーザーとって有益なサイトへと成長させましょう。
テクニカルSEO対策におすすめのツール
最後にテクニカルSEO対策におすすめのツールを、7つ紹介します。
- Google Search Console(サーチコンソール)
- Screaming Frog SEO Spider
- Lumar(旧:Deepcrawl)
- dead-link-checker
- TACT SEO
- ANATOMY
- KEYWORD FINDER
上記のツールを参考に、自社サイトと相性の良いツールを探してみましょう。では、それぞれ詳しく解説します。
Google Search Console(サーチコンソール)
Google Search Consoleはサイトの状況を把握し、改善するための無料ツールです。Google検索におけるサイトの表示状況や検索キーワード、エラーなどを確認できます。
おもな機能や特徴は、以下の通りです。
|
おもな機能 |
特徴 |
|
検索パフォーマンス |
サイトの検索順位やクリック数、表示回数などを分析し、SEO対策の効果を測定できる |
|
インデックス |
サイトがGoogleにどのようにインデックスされているかを確認し、インデックスの問題を解決できる |
|
サイトのエラー |
クロールエラーやモバイルフレンドリーに関する問題など、サイトのエラーを特定できる |
|
セキュリティ問題 |
サイトがハッキングやマルウェアに感染していないか確認できる |
|
構造化データ |
構造化データの導入状況を確認し、リッチスニペットの表示状況を改善できる |
Screaming Frog SEO Spider
Screaming Frog SEO Spider は、イギリスのソフトウェア開発会社が提供するツールです。リンク切れやリダイレクトの調査など、テクニカルSEOに活かせる機能が備わっています。
おもな機能や特徴は、以下の通りです。
|
おもな機能 |
特徴 |
|
リンク切れ、エラー、リダイレクト |
404エラーやサーバーエラーなどを瞬時にクロールして特定できる |
|
ページタイトルとメタデータ |
ページタイトルとメタディスクリプションを分析し問題点を特定できる |
|
重複コンテンツ |
完全な重複URLや、ページタイトル、ディスクリプション、ヘッダーなどの部分的に重複した要素を発見できる |
|
XPathでデータを抽出 |
CSSパス、XPath、または正規表現を使用して、ウェブページのHTMLから任意のデータを収集できる |
|
ロボットとディレクティブの確認 |
robots.txt、メタロボット、またはX-Robots-Tagディレクティブ(noindexやnofollowなど)によってブロックされたURLを表示する |
>>Screaming Frog SEO Spider の公式サイトはこちら
Lumar(旧:Deepcrawl)
Lumarはサイトの内部構造を深く掘り下げ、SEO対策の効率化を支援するツールです。サイトの隅々までを調べ上げ、潜在的な問題点を洗い出します。
具体的にはサイトマップの調査や各ページのクロール状況など、SEO対策において重要な情報を自動で収集し、分かりやすく可視化します。
おもな機能や特徴は、以下の通りです。
|
おもな機能 |
特徴 |
|
SEO内部評価指標 |
250以上のSEO内部評価指標を簡単かつ簡潔に把握できる |
|
ページレンダリングサービス |
JavaScriptを使用したサイトもクロールできる |
|
クロールデータの蓄積 |
サイトのクロールデータを蓄積することで、急な自然検索トラフィックの減少が起こった際に原因を調査できる |
|
スコアリング |
SEOの可視性やユーザー体験など、サイトの状態をさまざまな指標でスコア表示できる |
|
通知機能 |
問題点が発生したらメール、Slack、Teams などへ通知でき、通知したい項目の選択やカスタマイズも可能 |
dead-link-checker
dead-link-checkerは、サイト内に設置した内部リンクのリンク切れを確認できるツールです。
調査方法はシンプルで、確認したいサイトのURLを検索窓に入れて「チェック」をクリックするだけです。
調査に少々時間がかかるのが欠点ですが、無料で使えるためリンク切れをチェックするだけなら便利なツールと言えるでしょう。
TACT SEO
TACT SEOはSEO業務の大半を自動化し、効率的なSEO対策を支援するツールです。
内部SEOの問題点などを一括で取得できるため、指示に従い施策を実行すればSEO評価の高いコンテンツを作成できます。
おもな機能や特徴は、以下の通りです。
|
おもな機能 |
特徴 |
|
SEO分析調査の自動化 |
キーワード順位、被リンク数、競合分析など、SEOに必要な分析調査を自動で実行し、レポートを作成できる |
|
SEO課題の抽出 |
サイトの内部構造やコンテンツを分析し、SEOの課題を迅速に特定できる |
|
記事作成業務の効率化 |
キーワード選定や文章構成を支援し、記事作成にかかる時間を大幅に削減できる |
|
キーワード選定の効率化 |
競合分析や検索ボリュームに基づいて、最適なキーワードを提案できる |
|
伴走支援プラン |
SEOの専門家が、TACT SEOの導入から運用までをサポート |
ANATOMY
ANATOMYは、直感的な操作でサイト分析を視覚化できるSEOツールです。アクセス解析とテクニカルSEO分析に強みがあり、SEO専門家さながらにサイトを細かく分析できます。
おもな機能や特徴は、以下の通りです。
|
おもな機能 |
特徴 |
|
GA4対応の統合型分析 |
アクセス解析とSEO分析を1つのツールで統合し、効率的な分析を実現 |
|
直感的な操作性 |
シンプルで分かりやすいインターフェースを採用 |
|
URL変更への対応 |
サイトのURLが変更されても、過去のデータを遡って分析できる |
|
ページのグループ化 |
ページをグループ化し、より詳細に分析できる |
|
Web画面履歴の自動取得 |
ユーザーのWeb画面履歴を自動的に取得し、行動分析に活用できる |
KEYWORD FINDER
KEYWORD FINDERは、キーワード選定や記事作成など、サイト全体のSEO管理に役立つ機能が豊富に搭載されたSEO対策ツールです。
おもな特徴は、以下の通りです。
|
おもな機能 |
特徴 |
|
キーワードの自動発見 |
検索ボリュームや難易度を考慮して、効果的なキーワードを自動的に取得できる |
|
キーワードマップ |
ユーザーが求めているトピックを視覚的に把握できる |
|
競合サイトとのキーワード比較 |
競合サイトが対策しているキーワードや人気のキーワードを分析できる |
|
コンテンツのSEOチェック |
コンテンツがSEO対策されているか簡易的にチェックできる |
|
記事の自動生成 |
AIを活用し、記事を効率的に作成できる |
テクニカルSEOを正しく対策して上位化を目指そう
いかがでしたでしょうか。
テクニカルSEOとは、検索エンジンをターゲットにしたSEO対策の総称であり、Webサイトの情報を検索エンジンに正確に伝えるために必要な対策です。
手法が明確にされているので、すぐに実行できる点や、Googleサーチコンソールで成果が定量的に把握できる点が優れています。
一方で、検索アルゴリズムのアップデートに合わせて更新が求められたり、条件によっては対策が適用できなかったりするのが難点です。
『ランクエスト』では、15年の経験を活かした徹底的なSEO施策を提供しています。
テクニカルSEO対策からコンテンツの作成まで、SEOに関わることなら丸ごとお任せいただけますので、上位化を目指したい企業様は、ぜひお問い合わせください。
SEOの外注(SEO代行)をご検討の方はこちら
SEOコンサルサービスをご検討の方はこちら
SEO対策費用についてはこちら
SEO会社をご検討の方はこちら