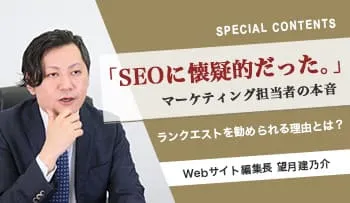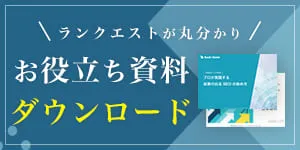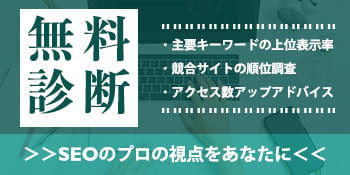カテゴリーとは、Webサイト内の関連性のあるコンテンツをまとめたグループです。適切に設定することで、ユーザビリティが向上し、間接的にSEOにも良い影響を与えます。
この記事では、カテゴリーがSEOに必要な理由や設定する際のポイントを解説していきます。
サイト構造の最適化を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
SEOにカテゴリーが必要な理由
カテゴリーページは、Wenサイト内のコンテンツを整理し、わかりやすく一覧表示するページです。ページを適切に仕分けすることで、視認性が高く、シンプルな構造のサイトを構築できます。
カテゴリー分けがSEOに必要な理由は以下の2点です。
- ユーザビリティの向上
- クローラビリティの向上
また上記を理解するために、階層構造について知る必要があります。
それぞれ詳しく解説していきます。
階層構造とは?
階層構造は、Webサイト内のコンテンツを分類して構成する、サイトの骨組みです。
トップページを基点とし、カテゴリーページや記事ページなど、ページの役割ごとにグルーピング後、設置する階層を決定します。以下は、シンプルなオウンドメディアの階層構造の例です。
|
第1階層(親階層) |
トップページ |
|
第2階層(小階層) |
カテゴリーページ |
|
第3階層(孫階層) |
記事ページ |
基本的にカテゴリーページは小階層に含まれ、内包される記事ページが、それぞれの孫階層として配置されます。階層構造の深さに制限はないため、第4・第5階層と伸ばせます。
しかし、深すぎるとユーザーとクローラーの回遊性を損ねるため、第3階層までに収めるのが理想とされています。
カテゴリー分けを行う際は階層構造が深くならないように意識し、必要最低限のページのみ作成することが大切です。
ユーザビリティの向上
適切にカテゴリー分けされたシンプルな階層構造のWebサイトは、ユーザーがコンテンツを見つけやすくなります。同じテーマのコンテンツを同一ページに配置することで、関連するコンテンツがわかりやすくなるためです。
また以下のような工夫をすれば、回遊性を高められます。
- メニューに各カテゴリーへのリンクを配置する
- パンくずリストでユーザーに現在地を伝える
ユーザーの滞在時間の増加につながり、間接的にSEO評価を高められます。
クローラビリティの向上
Googleのクローラーは、内部リンクを辿ってWebサイトを回遊します。そのため、カテゴリーで階層構造を明確にするとクロールの効率が上がり、次のメリットが生まれます。
- インデックスされるのが早くなる
- クローラーがページを見落とさなくなる
インデックスの速度が上がると、SEO評価も早く受けられるため、記事ページを適切なカテゴリーに分類しましょう。
SEOに効果的なカテゴリー階層を設定するポイント
SEOを意識したカテゴリー階層を設定するポイントは、以下の5つです。
- 適切なグルーピングをする
- 子カテゴリーまでに留める
- 内包するページがカテゴリーを横断しないようにする
- カテゴリー名に対策キーワードを含める
- パンくずリストを設定する
それぞれ詳しく解説していきます。
適切なグルーピングをする
カテゴリーを分ける際は、同じジャンルの記事を1つにまとめましょう。同ジャンルのコンテンツが1ページにまとめられていれば、ユーザーの潜在ニーズを満たすことが可能です。
反対にグルーピングが曖昧だと、かえってユーザビリティが低下します。
たとえば「Webデザイン」のカテゴリーの中に、SEO対策について解説した記事があると、ユーザーを混乱させてしまいます。サイトに対する信憑性を失う原因になるため、カテゴリー分けは慎重に行いましょう。
子カテゴリーまでに留める
記事をさらに細分化したい場合、子カテゴリーを作ることができます。たとえば、以下のようなイメージです。
| 親カテゴリー | 子カテゴリー |
|---|---|
| Webマーケティング | SEO対策 Web広告 SNSマーケティング |
親カテゴリー内の記事数が多い場合、子カテゴリーを使えば、わかりやすく整理できます。
また子カテゴリーの中に、孫カテゴリーを作ることも可能です。上記の例だと、SNSマーケティングの中に「Twitter」や「Facebook」を作るイメージです。
しかし、階層構造を深くしすぎるとクローラビリティの低下を招き、ページがインデックスされない恐れがあります。
そのため、カテゴリー分けの段階で子カテゴリーまでに留まるように設計しましょう。
内包するページがカテゴリーを横断しないようにする
同じページが複数のカテゴリーに属していると、ユーザーの混乱を招きます。一度確認したページが、別のカテゴリーページにも存在していると、異なるページなのか判断に迷うためです。
記事のテーマによっては、複数のカテゴリーに属してもよい場合はありますが、より関連性の高い方だけに含めましょう。
カテゴリー名に対策キーワードを含める
カテゴリー名にSEOの対策キーワードを含めると、クローラーがページ内容を把握しやすくなります。また、カテゴリーページそのものが検索結果で上位に表示される可能性もあります。
そのため、内包する記事のジャンルを明確に表す対策キーワードを選定することが重要です。
しかし、類似あるいは重複しているカテゴリー名が複数存在すると、クローラーやユーザーの混乱を招くため、注意しましょう。
パンくずリストを設定する
パンくずリストとは、ユーザーにWebサイト上での現在地を伝えるための地図です。通常、ページの上部に内部リンクとして表示されています。設定すれば、ユーザーがページの階層構造を瞬時に把握できるため、ユーザビリティの向上につながります。
またパンくずリストを設定する際は、構造化マークアップを施すことが重要です。
検索エンジンにパンくずリストの内容を伝えることができるため、リッチスニペットとして検索結果に表示される可能性があります。クリック率の向上が見込めるため、必ず設定しましょう。
SEOに適さないカテゴリーの例
カテゴリーは、設定を誤るとSEOに悪影響を与える可能性があります。
よくある失敗例は、以下の2つです。
- ユーザーに馴染みがないカテゴリー名になっている
- 内容が重複している
それぞれについて詳しく解説していきます。
ユーザーに馴染みがないカテゴリー名になっている
カテゴリー名に馴染みがないと、ユーザーは内包されているページがイメージできません。ユーザーが情報を求めて、サイト内をくまなく巡回することはほとんどありません。
そのため、カテゴリー名がわかりにくいとアクセスしてもらえる確率が減り、機会損失を招きます。
専門用語の使用は避け、ユーザーが検索で使用するキーワードなど、わかりやすい言葉を選びましょう。
内容が重複している
内容が重複しているカテゴリーが存在すると、ユーザーを困惑させてしまいます。
たとえば「Webサイト制作」と「ホームページ制作」というカテゴリーがある場合、どちらも同じような内容になるはずです。
上記の場合「Webサイト制作」として1つにまとめるのが理想です。カテゴリーを分ける事情がある場合は、Webサイトの種類ごとに子カテゴリーを作成するなどの工夫をしましょう。
カテゴリーの変更はSEOに悪影響を与える可能性がある
記事ページのURLにカテゴリーを含めている場合、それも変わってしまいます。たとえば、以下のようなイメージです。
| カテゴリー | URL | |
|---|---|---|
| 変更前 | SEO対策 | https://example.com/seo/how-to-seo/ |
| 変更後 | Webマーケティング | https://example.com/web-marketing/how-to-seo/ |
Googleは、URLでサイトを認識しています。
そのため、カテゴリーを変更すると新しいページとして認識され、SEO評価もリセットされます。上位表示されていたページが大きく順位を落とす可能性もあります。
一度低下した順位は元に戻るとは限らないため、なるべく変更しないようにしましょう。
やむを得ない場合は、301リダイレクトでURL正規化を行うなどの対策をとれば、順位低下のリスクを抑えられます。
SEO評価向上のためにカテゴリー設定を最適化しよう
カテゴリー分けは、ユーザーとクローラーの回遊性を向上させる上で重要です。
間接的にSEO評価に影響するため、サイト構築段階から慎重な設計が求められます。
作成の際は、内容の重複や階層構造が深くなることを避け、ユーザーにわかりやすい名前のカテゴリーを作成しましょう。
弊社のSEOサービス「ランクエスト」では、お客様ごとに専任のコンサルタントがつき、戦略立案からコンテンツ制作、効果測定まで、すべて対応いたします。SEO対策にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。