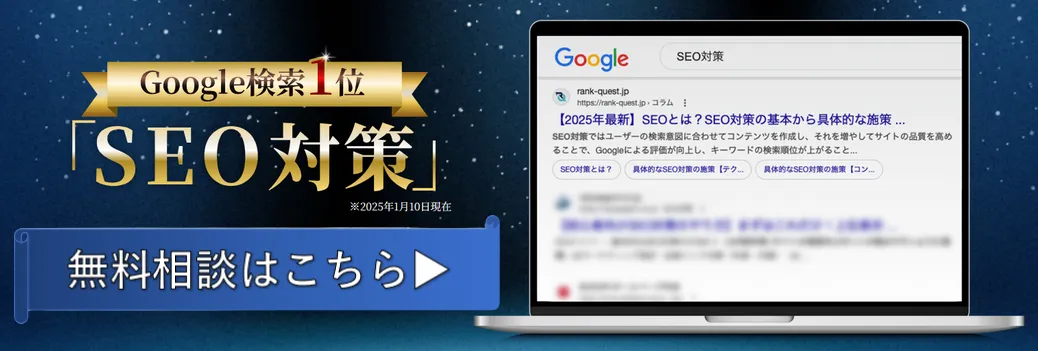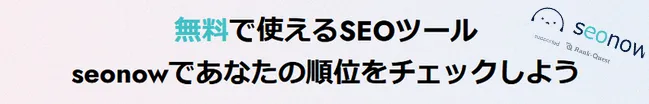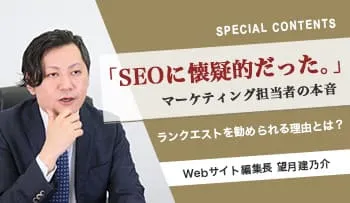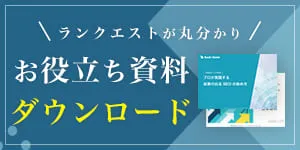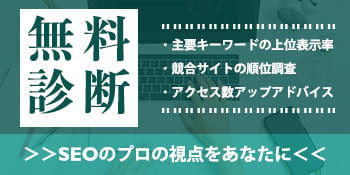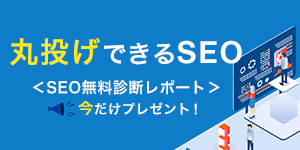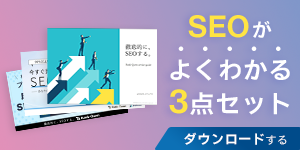Googleの理念を知ることは、根本的な活動方針はもちろん、Googleが今後何を目指して事業を展開していくのかを理解するきっかけになります。
また、WEB担当者としてSEO対策に取り組んでいるのであれば、検索エンジンのアルゴリズムのもととなっている理念の把握は欠かせません。
本記事では、Googleの理念、ならびにSEO対策への活用方法を徹底解説します。
Googleへの理解を深め、検索エンジンに評価されるSEO対策を実施したい方は、最後までご覧ください。
目次

今すぐ無料で、
あなたのSEO対策費用を
シミュレーション!
簡単な質問に答えるだけで、
最適なSEOプランと費用が無料でわかります。

SEO対策を
行ったことはありますか?

Googleの理念とは
「Google の使命は、世界中の情報を整理し、世界中の人がアクセスできて使えるようにする」というのが創業当初からのGoogleの理念です。
これは現在でもGoogleの経営理念(ミッション・ステートメント)として、Googleが生み出す価値や文化、社員の行動に根付いています。
Googleが掲げる 10 の事実
さらにGoogleは、この理念を具現化するために「10の事実」を掲げています。
具体的な内容は、以下の10項目です。
- ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。
- 1つのことをとことん極めてうまくやるのが一番。
- 遅いより速いほうがいい。
- ウェブ上の民主主義は機能する。
- 情報を探したくなるのはパソコンの前にいるときだけではない。
- 悪事を働かなくてもお金は稼げる。
- 世の中にはまだまだ情報があふれている。
- 情報のニーズはすべての国境を越える。
- スーツがなくても真剣に仕事はできる。
- 「すばらしい」では足りない。
参照元:Google「Google が掲げる 10 の事実」
Googleは会社設立から数年後に、この「10の事実」を策定しました。
これらの項目をつねに見直し、事実に変わりがないかを確かめています。
最新のGoogleアルゴリズムの内容
Googleは常に検索アルゴリズムを改善しており、新たな変更が行われる可能性があります。そのため、最新のSEO情報に常に目を向け、サイト運営に反映していくことが重要です。
2023年11月3日に実施されたGoogleコアアルゴリズムアップデートでは、以下の項目が主な変更点として挙げられています。
コンテンツの品質の重視
Googleは、検索結果の品質を向上させるために、コンテンツの品質をより重視するようになりました。具体的な内容は以下のとおりです。
- 独自性やオリジナリティ
- 正確性や信頼性
- 有益性や役立ち度
- 読みやすさやわかりやすさ
ユーザーのニーズへの対応
Googleは、ユーザーのニーズをより正確に理解し、それに応えるコンテンツを評価するようにしました。具体的な内容が以下のとおりです。
- 検索意図を的確に捉えているか
- 検索結果に期待する情報を提供しているか
- 検索結果に満足しているか
サイトの信頼性の評価
Googleは、サイトの信頼性もより重視するようになりました。具体的な内容が以下のとおりです。。
- 権威性や信頼性
- 安全性や安心感
- 運営状況や継続性
コンテンツの質を高め、ユーザーのニーズを的確に捉えることが、SEO対策の重要ポイントといえます。
理念にもとづいたサービス
毎日の生活のなかで、Googleのサービスを利用しない日はないと言っても過言ではないかもしれません。
代表的なサービスは、以下のとおりです。
豊富なGoogleのサービス
- 検索エンジンChrome
- Google Maps
- Google翻訳
- Gmail
- YouTube
- Google Play
- Googleフォト
- Googleカレンダー
- Googleドライブ
- Google Pixel
Googleのサービスがこれほどまでに世界中に普及し、信頼されているのは、理念にもとづいてサービスを提供しているからです。
ここからは、数多くのGoogleのサービスのなかから3つを厳選して解説します。
検索エンジンChrome
検索エンジンChromeは、Googleの原点である検索サービスです。
質の高い有用な検索結果と使いやすさから、世界でも日本国内でも圧倒的なシェアを誇っています。
生活するうえでここまで欠かせないサービスになれたのは、表示される検索結果がユーザーファーストだからです。
これは、10の事実の1つ目の項目「ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。」を実践していると言えます。
Google Maps
Google Mapsは、外出時に手放せません。
目的地の名称や住所を入力するだけで、現在地からの経路を瞬時に表示してくれます。
また、目的地への経路を調べるだけではなく、現在地周辺のカフェや観光スポットを探すという使い方もできます。
検索結果には、ユーザーが投稿した口コミが記載されているので、どの飲食店や観光地を訪れるか選ぶ際の参考になるでしょう。
Google Mapsを利用するのは自宅の外にいるときが多いので、10の事実のうち5つ目の項目「情報を探したくなるのはパソコンの前にいるときだけではない。」に該当します。
Google翻訳
現在では、外国語で書かれたコンテンツに出会う機会が増えました。
グローバル化が進んでいるので、英語から日本語に訳すのはそれほど難しくないという方もいらっしゃるでしょう。
しかし、フランス語やタイ語、アラビア語からの翻訳となるといかがでしょうか?
そんなときに活躍するのが、100以上の言語に対応しているGoogle翻訳です。
10の事実の8つ目の項目「情報のニーズはすべての国境を越える。」をまさに体現しています。
YouTube
YouTubeは、娯楽や学習、情報収集など、さまざまな目的で利用できる、便利なプラットフォームとなりました。
月間アクティブユーザー数は、2024年1月時点で29億人、アップロードされている動画の数は1兆本を超えています。
YouTubeは、ユーザーが好きなコンテンツを簡単に見つけられるように、多様なジャンルのコンテンツを揃えています。また、ユーザーの視聴履歴や検索履歴を基に、おすすめのコンテンツを表示するなどの機能を提供しています。
まさしく、10の事実の1 つ目の項目「ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる」を表現しているといえるでしょう。
YouTubeは世界中の人々が情報やエンターテインメントを楽しむためのプラットフォームとして、ますます成長を続けていくでしょう。
10の事実から得られるSEO対策への活用方法
SEO対策を実施するうえで、Googleの理念、そして10の事実にもとづいた施策を講じることは欠かせません。
検索エンジンを利用するユーザーのほとんどは、Googleの検索エンジンを利用しているからです。
以下の表に、世界の主な検索エンジンのシェアをまとめてみました。
世界の検索エンジンのシェア
| 検索エンジン | シェア率 |
| 93.1% | |
| bing | 2.7% |
| Yahoo! | 1.1% |
参照元:statcounter「Search Engine Market Share Worldwide May 2022 – May 2023」
続けて、日本国内の検索エンジンのシェアは以下のとおりです。
日本の検索エンジンのシェア
| 検索エンジン | シェア率 |
| 77% | |
| Yahoo! | 13.9% |
| bing | 8% |
参照元:statcounter「Search Engine Market Share Japan May 2022 – May 2023」
なお、Yahoo!はGoogleの検索エンジンと同じアルゴリズムを採用しています。
つまり、世界でも日本国内でも、Googleは検索エンジンとして実質90%程度のシェアを誇っているのです。
上記の内容から、「SEO対策=Google対策である」と言い換えられます。
そこでここからは、10の事実の各項目に対して、SEOコンサルタントの見解や、徹底的にSEO対策を行うランクエストの作業内容、案件の事例をふまえて解説していきます。
1.ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。
10の事実のなかでも最初の項目である「ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。」は、Googleがもっとも重要だと考えている理念だと伺えます。
SEO対策の経験があれば、聞き覚えがある方も多いのではないでしょうか?
Googleはつねに、ユーザーを第一に考え、サービスを展開しています。
検索ユーザーが、無料で有益な情報を得られる、使いやすいWebサイトにいち早くたどり着けるよう、アップデートを繰り返してきました。
実際に、Google検索セントラル内で、SEOの基礎として「有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成」を説明しています。
「Google の自動ランキングシステムは、検索エンジンでのランキングを上げることではなく、ユーザーにメリットをもたらすことを主な目的として作成された、有用で信頼できる情報を検索結果の上位に掲載できるように設計されています」と記載されています。
ユーザーを第一に考えたコンテンツであれば、検索エンジンのランキングを操作することを目的にはしません。
最近ではE-E-A-Tという、Experience(経験)・Expertise(専門性)・Authoritativeness(権威性)、・Trustworthiness(信頼性)の4つが優れているコンテンツが評価されています。
素人より専門家が発信している内容のほうが信頼でき、経験がない方よりも実体験がある方のほうが、その情報に関して詳しいと判断できるからです。
つまり、深い知識や実体験を明示し、ユーザーが有益だと感じてくれるかを判断軸にコンテンツ制作を行えば、”結果的に”SEOで上位化し、利益が得られるということです。
また、ユーザーに焦点を絞るということは、有益な情報を与えるだけではありません。
ハッキングされないような配信の安全性や、スマートフォンやタブレット端末にも対応した表示といった検索体験が優れているのかも重要です。
ほかの検索体験には、ユーザーに関連のある広告の適切な表示や、ページ内のメインコンテンツの見つけやすさなどがあります。
上記の内容は、「ページ エクスペリエンスの Google 検索結果への影響について」でGoogleが公式に解説しています。
2. 1つのことをとことん極めてうまくやるのが一番。
辞書で「とことん」を調べてみると、「最後の最後」「徹底的に」という意味だとわかります。
上記をふまえて、Googleの2つの考えを見出すことができます。
1つは、ユーザーにとって有益な情報を提供するのに徹するということであり、これは前述したようにSEO対策において極めて重要です。
もう1つは、専門性を高くするという解釈です。
多くの情報を1つのページ内に詰め込むと、ユーザーが情報にたどり着けなかったり、途中で探すのをあきらめたりするおそれがあります。
一方、必要な情報のみを記載し特定の内容に特化すれば、最終的に「特定の内容の百科事典」のようなWebサイトに仕上げられます。
つまり、その特定の内容に興味があるユーザーは、すべての情報を1つのサイト内で見つけやすくなり、理解できるというわけです。
たとえば、ランクエストで対策しているきぬた歯科の事例を見ていきましょう。
歯科医院なら、虫歯治療や親知らずの抜歯などの一般的な歯科治療のことも、コンテンツとして発信したほうがよいと思われるかもしれません。
しかし、きぬた歯科はインプラント治療の実績が圧倒的に多い歯科医院です。
そこでランクエストでは、インプラント治療の情報にだけ焦点を絞って発信するという施策を実施しました。
具体的には、TOPページや治療の症例、お役立ち情報もインプラントについてのみを発信しつづけました。
インプラントについて”徹底的に”情報発信すると、結果はどうなったのでしょうか。
なんと「インプラント」(Google月間検索数90,500回)で9位、「インプラント 費用」(Google月間検索数60,500回)で1位の検索結果を獲得できたのです。(※2023年6月5日時点)
3.遅いより速いほうがいい。
3つ目の項目は、ユーザーが検索してから回答にたどり着くまでのスピードを表しています。
象徴するように、Googleの検索画面には検索窓しかなく、余計な情報が一切ありません。
これは、ユーザーの貴重な時間を奪わずに、検索時に最速で回答にたどり着けるようにするためだと考えられています。
また、SEO対策を行ううえでのWebページの応答スピードも意味しています。
Googleは、ユーザーが必要な情報を検索結果に瞬時に提供したいと考えています。
実際にGoogleが提供している「PageSpeed Insights」という開発ツールをご存じですか?
このツールを使うと、自身のWebページのスピードを定量的に判断できるほか、スピードを速くするためのアドバイスももらえます。
Webページの表示スピードが速くなれば、Googleがユーザーにとってより一層使いやすい検索エンジンになっていきます。
このようなツールを無料で提供しているのは、Webサイトの保有者に対してもユーザビリティの高い、表示速度の優れたサイトを運営してほしいという願いが込められているからではないでしょうか。
なお、応答スピードはPCだけではなく、スマートフォンやタブレット端末などのすべてのデバイスからもチェックすることが大切です。
4.ウェブ上の民主主義は機能する。
「ウェブ上の民主主義」とは、Googleのすべてのユーザー(国民)によるページ間のリンクを「投票」と見立てて、どのサイトがよいのかを評価することです。
Googleでは、200以上の基準を設けているPageRankアルゴリズムによって、それぞれのWebページの相対的な評価を行っています。
PageRankは「リンクがより多く集まっているWebページはより重要である」という考え方にもとづいて、Googleが独自に開発した評価指標の1つです。
自身のWebページにほかのサイトからの被リンク(外部リンク)がつくと、Googleが「このページは他サイトから紹介されるくらい信頼できるサイトだ」という評価を下します。
では、自身のWebページに”投票”してもらうにはどうすればよいのでしょうか?
答えは、「ユーザーにとって有益なコンテンツを作ること」です。
ほかのサイトが引用したくなるような、あるいは被リンクを貼りたくなるような情報を提示することで、自然に被リンクが増えていくからです。
さらに、リンクを貼ってくれているサイトのWebページの評価が高いほど、投票の重みが変わってきます。
高評価のサイトにも参照してもらえるような、有益な情報をユーザーに発信する必要があるというわけです。
ただし、お金でリンクを買って被リンクを増やすのは「ブラックハットSEO」とよばれ、逆に評価が下がってしまいます。
政治の世界でも、お金で票を買うのは禁止されているのと同じですね。
5.情報を探したくなるのはパソコンの前にいるときだけではない。
最近では、パソコンよりもスマートフォンで検索するほうが多いという方がほとんどなのではないでしょうか。
5つ目の項目は、スマートフォンで検索するユーザーが増える需要にあわせて、Googleも変化していくという意味です。
Googleはもともと、「ユーザーはパソコンでWebページを閲覧している」ことを前提に評価していましたが、2018年に「ユーザーはモバイルでWebページを閲覧している」ことを前提の評価基準に変更しました。
それが「モバイルファーストインデックス(MFI)」です。
SEO対策を実施するうえで、自身のWebサイトをモバイル表示に対応させることが必須となっています。
「モバイルフレンドリーテスト」というGoogleの開発ツールを使うと、ページの URL を入力するだけで、モバイル端末での使いやすさをテストでき、そのスコアが表示されます。
6.悪事を働かなくてもお金は稼げる。
Google検索セントラル内の「Googleウェブ検索のスパムに関するポリシー」で、隠しテキストや隠しリンク、キーワードの乱用などを禁止行為として挙げています。
なぜなら、これらの行為はユーザーやGoogleのクローラーを欺く行為と考えられているためです。
「Google のポリシーに違反しているサイトは、検索結果での掲載順位が下がったり、まったく表示されなかったりすることがある」とも説明しています。
SEOで上位化させるために無理やりキーワードを詰め込んで読みづらい記事を作ったり、お金を稼げるように大量の広告を掲載したりするのは、ユーザーから嫌われる行為です。
そのため、ユーザーファーストのGoogleもそれらの行為を嫌います。
悪事を働かなくても、ユーザーのことを第一に考えて、有益で利便性の高いWebサイトを提供していれば、結果的にお金は稼げます。
7.世の中にはまだまだ情報があふれている。
Googleは、画像検索や音声検索でもユーザーに情報を届けられるようになってきました。
ユーザーが本当に求めている情報を提供できるように、進化しつづけています。
音声検索を例に挙げて、SEO対策の話をしてみます。
たとえば「近くの美味しいラーメン屋」とGoogleで音声検索したとしましょう。
この場合、どのようなキーワードで、SEO対策すればよいのでしょうか?
答えは「○○(地名) ラーメン おすすめ」です。
あるいは、これらのキーワードに「ランキング」や「人気」を付け加えます。
「近くの」とついている時点で、Googleは位置情報をもとにユーザーの現在地近辺のラーメン屋を表示させます。
新宿駅にいる場合は、新宿駅付近のおすすめのラーメン屋を検索結果に表示させるといった具合です。
つまり、自身のページに訪れてほしいユーザーを細かく想像し、どのようなキーワードであれば、ページにたどり着いて満足してくれるのかを考えることが欠かせません。
実際に「近くの美味しいラーメン屋」で検索してみると、SEOで上位にあるページに「地名」「おすすめ」「ランキング」「人気」などのキーワードが含まれているとわかります。
さまざまな手段で情報を手に入れようとしている、あらゆるユーザーに情報を提供するためには、どうしたらよいのかを考えながらSEO対策を行う必要があります。
8.情報のニーズはすべての国境を越える。
冒頭で、Googleは「世界中の情報を整理し、世界中の人々がアクセスして使えるようにする」という理念を掲げていると説明しました。
言い換えると、”世界中の人々が世界中の情報にアクセスできる”状態を目指しているということです。
そのため、グローバル企業や、これから海外進出する企業がWebサイトを運用する際には、多言語サイトまたは多地域サイトであることを明示する必要があります。
もちろんGoogleの翻訳ツールを利用することで、知らない言語のコンテンツであっても母国語への翻訳は可能です。
詳細は、Googleが公式で伝えている「多地域、多言語のサイトの管理」を読むことをおすすめします。
9.スーツがなくても真剣に仕事はできる。
9つ目の項目は、まるでGoogleの働き方を象徴するような一文ですね。
「ビジネスの世界では、必ずスーツで働くという凝り固まった考え方ではなく、自由で柔軟な発想が新しいアイデアや価値を生み出せる」という意味だと解釈できます。
SEOの世界でも同じことが言えますが、スーツを着ないでSEO対策に取り組むという意味ではありません。
ほかのサイトを真似してただ同じコンテンツを作り、「この方法であれば、このキーワードで上位化できる」といった固定概念を持つのをまずはやめます。
そして実際にユーザーになりきって「このキーワードを検索するのが自分だったら、どんな情報がどんな順番で欲しいだろうか」と柔軟に考えることが大切です。
実は、ランクエストでも同じような考えのもと、SEO対策を実行しています。
もちろん上位化したいキーワードで検索し、実際にTOP10にあるページを参考にはします。
それにくわえて「TOP10のページには載っていないけど、必要な情報はほかにもないのか」を”徹底的に”考えて、記事を作っているのです。
実際にテストした結果、TOP10のページには載っていないものの、ユーザーに必要であると考えた情報を載せた記事が、そうではない記事に比べて上位化のスピードが速いことがわかりました。
被リンクや競合の対策状況などの外的要因も考えられますが、少なくともユーザーファーストを意識した結果だと考えています。
10.「すばらしい」では足りない。
Googleは、10番目の事実の文頭で「Google にとって一番であることはゴールではなく、出発点に過ぎません。」と記載しています。
SEO対策に置き換えるのであれば、キーワードで1位を取ることはゴールではなく、スタートであると捉えられるのではないでしょうか。
さらに「Google は、全世界のユーザーがまだ具体的にイメージしていないニーズを予測し、新たなスタンダードとなるサービスを作り出しています。」とも記述しています。
本当に必要な情報、そして潜在的なニーズを予測したものをかたちにして提供すれば、ユーザーが有益だと判断し、結果的にGoogleにも評価されます。
10の事実の1つ目の項目である「ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。」を行動に移すためのヒントを、この10番目の事実から読み取れるでしょう。
SEOコンサルタントが考える10の事実のなかでもっとも大切なこと

1つ目の項目「ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。」がSEOを行ううえでもっとも大切なことだと私は考えています。
最初にある理念だからというのも理由の一つですが、日々検索をしている当事者だからこそ大切だと感じています。
私自身、使いづらいサイトや、表示に時間がかかるサイトに出会うと、見るのをやめて別のサイトに移ってしまうことがほとんどです。
使いづらい場合はすぐに気がつく一方で、使いやすいときは無意識に別のページに移りながら、スムーズに必要なページにたどり着くことができます。
なかなか気がつけない「なぜ使いやすいのか」を認識できると、ユーザーが求めているサイトへと成長させられます。
また、SEOは上位化している競合との差分を埋めていくことが定石ではありますが、順位はあくまでも相対評価です。
つまり、現状評価されているページあるいはサイトが1位になっているだけで、それよりもユーザーにとって有用で信頼性の高いコンテンツを作成できれば勝てるというわけです。
競合を見るのではなく、このクエリで検索するユーザーになりきって、必要な情報を提供し、サイトのデザインを整えるなどの工夫を施せば、SEOで上位化できるようになります。
これは文字で書くと一見簡単に思えるかもしれませんが、実践するとなると非常に難しい作業です。
たとえば、不動産投資についてのコンテンツを作成することになったとします。
不動産投資のことを考えて「自分が不動産投資を始めようと思っている人だったら、どのように行動するだろうか」といったふうに、ユーザー像を描くことから始めます。
不動産投資の知識がなければ、そもそも何を書けばよいのか悩んでしまうでしょう。
あるいは、知見があるからこそ見えていないユーザー心理があるかもしれません。
より具体的なユーザー像を描くには、専門知識がある方に話を伺ったり、実際に使っている方のリアルな声を聞いたりするのがおすすめです。
さらに、以下の項目を”徹底的に”考えることが「ユーザーに焦点を絞る」ことだと考えています。
ユーザーに焦点を絞るためのポイント
- ユーザーが本質的に何を求めているのか
- このページにたどり着いたら次にどのような情報を知りたいのか
- このページの前に知りたかった情報は何か
- サイト自体は一見してわかりやすいデザインや設計になっているのか
何度も何度もユーザーになりきって、”徹底的に”考え抜いて実行してみると、その先に「他のものがみな後からついてきている」状態になっているのではないでしょうか。
Googleの理念に基づいてSEO対策すべき理由
SEO対策を行う上では、Googleの理念に基づいた施策を講じることが大切です。理由は以下の2つです。
- ユーザーファーストなサイトを構築するため
- 検索エンジン(Google)からの信頼を獲得するため
それぞれ詳しく解説していきます。
ユーザーファーストなサイトを構築するため
Googleの理念は「世界中の情報を整理し、世界中の人々がアクセスできて使えるようにすること」です。この理念に基づくと、SEO対策は、ユーザーが求める情報をわかりやすく提供するための施策と言えます。
具体的には施策の施策があげられます。
- ターゲットキーワードを明確にして、ユーザーの検索意図を把握する
- 専門性・権威性・信頼性の高いコンテンツを制作する
- 読みやすいコンテンツを制作する
これらの対策を実施することで、ユーザーが求める情報をわかりやすく提供できるようになります。
検索エンジン(Google)からの信頼を獲得するため
Googleは、検索結果の品質を保つために、検索アルゴリズムを常に改善しています。その中で、検索ユーザーにとって価値のあるコンテンツを提供するサイトは、検索結果で上位表示されるようになっています。
有効な施策の具体例が以下のとおりです。
- 高品質なコンテンツを制作する
- モバイル対応を徹底する
- アップデート対策を実施する
これらの対策を実施することで、検索エンジンから信頼されるサイトとなります。
ブランド力の向上につなげるため
ブランド認知度は、一般の人々があなたのブランドや製品をどれだけ認識しているか、またはそれらをどれだけ思い出すことができるかを測定する指標です。ブランド認知度が高いと、消費者はあなたのブランドを信頼し、製品やサービスを購入する可能性が高くなります。
ブランド認知度の向上に寄与するSEO対策には以下のようなものがあります。
- SERPs(Search Engine Results Pages)での高いランキング
- 高品質なコンテンツの提供
- キーワード戦略
- ソーシャルメディアとの統合
ブランド認知度だけでなくWebサイトのトラフィックを増加させ、コンバージョンを促進します。
基本的なSEO対策は3種類
基本的なSEO対策とは、検索エンジンからの評価を高め、上位表示を目指すための施策のことです。SEO対策の種類は下記の3つです。
- 内部SEO対策
- 外部SEO対策
- コンテンツSEO対策
それぞれの詳細を解説していきます。
内部SEO対策
内部SEO対策とは、自社サイトやページの内部構造やコンテンツを改善する施策です。検索エンジンは、サイトの内部構造やコンテンツを評価して、検索結果の順位を決定しています。そのため、内部SEO対策を実施することで、検索エンジンからの評価を高めることができます。
内部SEO対策の具体的な施策は、以下のようなものが挙げられます。
- タイトルタグやメタディスクリプションの充実
- 内部リンクの適切な設定
- ページの読み込み速度の改善
- モバイル対応の強化
外部SEO対策
外部SEO対策とは、他のWebサイトから自社サイトやページへのリンクを獲得する施策です。検索エンジンは、リンクの数や質を評価して、検索結果の順位を決定しています。そのため、外部SEO対策を実施することで、検索エンジンからの信頼性を高めることができます。
外部SEO対策の具体的な施策は、以下のようなものが挙げられます。
- プレスリリースの発行
- ソーシャルメディアの活用
- インフルエンサーとのコラボレーション
- ブログやメディアへの寄稿
コンテンツSEO対策
コンテンツSEO対策とは、検索ユーザーのニーズを満たすコンテンツを制作する施策です。検索エンジンは、コンテンツの質を評価して、検索結果の順位を決定しています。そのため、コンテンツSEO対策を実施することで、検索ユーザーの満足度を高めることができます。
コンテンツSEO対策の具体的な施策は、以下のようなものが挙げられます。
- ターゲットキーワードの選定
- 検索意図の把握
- 専門性・権威性・信頼性の担保
- 読みやすいコンテンツの制作
今後のGoogleはどうなっていくのか
ここまでGoogleの理念、ならびに10の事実に対するSEOコンサルタントの見解などを解説してきましたが、今後はどのようなサービスの展開が予測されるのでしょうか。
次で詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
直近の検索エンジンにおいて想定されるGoogleのアップデート
昨今のアップデートのトレンドでは、より信憑性の高い一次情報が上位化される傾向が見られています。
その傾向は、人々のお金や健康、暮らしに影響を及ぼすYMYL(Your Money or Your Life)というジャンルに顕著に表れています。
ここから考察されるSEO対策において重要視されるのは、ユーザーが真に求める情報をいかに正しく提供していけるのかということです。
具体的には、ほかのサイト上にすでにある情報を二次転用したものよりも、自らの実体験による一次情報が記載されているコンテンツが評価されていくと言われています。
さらに、専門知識を持つ方が執筆あるいは監修すると、コンテンツの専門性が高まり、Googleに高評価されるようになります。
また、最近話題のOpenAIの「ChatGPT」はすでに多くのユーザーが情報収集に利用しており、実際に使ったことがある方も多いのではないでしょうか?
Googleでも対話型AIサービス「Google Bard」を公開しています。
Google Bardは、情報収集する検索エンジンでは満たせないような、メールを作成したり、アイデアを出したりといった、クリエイティブなタスクに対応するためのサービスです。
回答の精度が今後ブラッシュアップされていくと、情報収集を目的としたユーザーの検索をサポートする手段にもなり得ると予測されます。
もしそうなれば、Google検索結果の画面に、現在の強調スニペットのような、AIによる回答が表示されることが想像できます。
くわえて、検索履歴から推察される、ユーザーが次に必要な情報を率先して回答する「検索コンシェルジュ機能」のようなものが現れるかもしれません。
これらは想像の域を出ない内容となりますが、Googleが今後より一層AIの領域に力を入れていくことは間違いないと考えています。
詳細は、「Google と AI : 私たちの基本理念」も合わせてご確認ください。
長期的な目線で見た検索行動の変化にともなうGoogleの展望
実際にGoogle Bardにて、今後のGoogleのサービスではどのようなことができるのかを
聞いてみました。
AIからの回答は、以下のとおりです。
Googleは、常に新しいサービスを開発し、既存のサービスに新しい機能を追加しています。今後のGoogleサービスでは、以下のようなことができるようになるでしょう。
人工知能(AI)を活用したサービスがさらに進化します。例えば、Google検索は、AIを活用して、ユーザーの検索意図をより正確に理解し、より関連性の高い検索結果を表示できるようになります。また、Google翻訳は、AIを活用して、より自然な翻訳を実現できるようになります。
仮想現実(VR)や拡張現実(AR)を活用したサービスが普及します。例えば、Googleストリートビューは、VRやARを活用して、ユーザーが世界中の場所をまるでその場にいるかのように体験できるようになります。また、Googleアシスタントは、VRやARを活用して、ユーザーにより自然な形で情報を提供できるようになります。
モバイルデバイス向けのサービスがさらに充実します。例えば、Googleマップは、モバイルデバイス向けに、より使いやすく、より便利な機能を追加します。また、Googleドライブは、モバイルデバイス向けに、より多くのファイル形式をサポートするようになります。
これらの新しいサービスは、私たちの生活をより便利で、より豊かにしてくれるでしょう。
引用元:Google Bard「今後のGoogleのサービスではどのようなことができる? 2023年6月5日時点の回答文」
前述したAIを活用したサービスのグレードアップに留まらず、VR・ARの活用や進化するデバイスに合わせた利便性の追求を期待できそうですね。
ランクエストではSEOのコンサルティングを行っているので、ユーザーの利便性という観点から将来のGoogleの検索画面を予想してみます。
そもそもユーザーが検索する前から、Googleによる自発的なアシストを受けられるのではないかと考えます。
たとえば、以下のようなサービスも実現可能になるのではないでしょうか。
Googleで将来的に実現できるかもしれないサービス
| 情報源 | 実現可能性のあるサービス |
| スマートフォンのヘルスアプリの情報や料理レシピの検索履歴 | 「初夏のダイエットにおすすめの簡単レシピを検索してみませんか?」とレコメンドしてもらえる |
| SNSのフォローや過去に調べたアーティストの情報 | 「あなたの好きなアーティストがお住まいの地域でライブチケット販売をスタートしますが、チケットを購入しませんか?」とレコメンドしてもらえる |
上記のようなサービスがすべて実現されるかはわかりませんが、Google は今後もユーザーの生活をより便利で豊かなものにしてくれるでしょう。
Googleの理念にもとづいて本質的なSEO対策を実施しましょう
本記事では、Googleの理念、ならびにSEO対策における活用方法を解説しました。
Googleは理念にもとづいて、つねにユーザーを第一に考えサービスを展開しています。
今後もその姿勢は変わらずに、生活をより豊かにしてくれるはずです。
また、SEO対策に取り組むのであれば、検索エンジンを提供しているGoogleの理念と10の事実にもとづいた施策の実行が欠かせません。
理念への理解を深め、ユーザーにとって有益なコンテンツを作っていきましょう。
SEOサービス「ランクエスト」では、専任のコンサルタントがつき、戦略立案からコンテンツ制作、効果測定まですべて対応いたします。
Googleの方針を考えながら、徹底的にSEO対策しますので、お困りの方はぜひご相談ください!