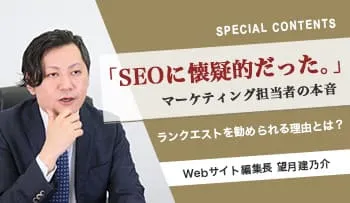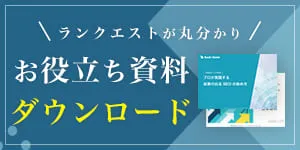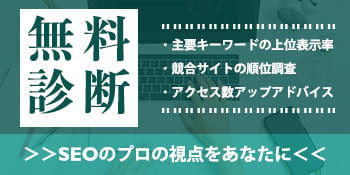直帰率は、ユーザーが1ページだけ閲覧した後、そのまま離脱した割合です。SEOに直接関係はありませんが、数値が高いとコンテンツに改善が必要な可能性があるため、定期的に確認しなければいけません。
しかし、詳細や重要性について理解していない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、直帰率の概要や改善方法について解説していきます。
Webサイトの回遊性を高めたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
直帰率とは?
直帰率とは、Webサイトに訪れたユーザーが他のページに遷移せずに離脱した割合です。Googleアナリティクスの指標の1つで、以下の手順で確認できます。
- Googleアナリティクスを開く
- サイドメニューの「行動」をクリック
- サイドメニューの「サイトコンテンツ」をクリック
- サイドメニューの「すべてのページ」をクリック
直帰率を確認すれば、全てのセッションの内1ページしか見られなかった割合がわかります。コンテンツの内容が適切か確認する目安となるため、ページごとに確認しましょう。
直帰率と離脱率の違い
直帰率と混同されやすい指標として、離脱率があります。それぞれの違いは以下のとおりです。
|
直帰率 |
ユーザーが1ページしか見ずにWebサイトから離脱した割合 |
|
離脱率 |
ユーザーが別のサイトに移動したり、ブラウザを閉じたりした割合 |
離脱率は、ユーザーが閲覧したページ数に関わらず、Webサイトから出ていった割合です。つまり、直帰率は離脱率の一部ということになります。
アクセス解析を行う上で、数値の用途が異なるため違いを理解しておきましょう。
直帰率の目安
一般的に直帰率の目安は40〜60%程度と言われています。
しかし、コンテンツやWebサイトの種類によっても異なるため、厳密には目安は存在しません。たとえばカテゴリーページなど、他のページへの移動の起点となるページでは直帰率が高いと問題です。
一方で問い合わせフォームが搭載されているLPなど、1ページで簡潔するコンテンツの直帰率が高くなるのは自然です。
ページごとに直帰率を下げる必要があるか吟味し、臨機応変に改善しましょう。
直帰率とSEO対策の関係
直帰率はSEO対策と直接的な関係はありません。
しかし、WebサイトがSEOに最適化されているかを見極める指標になります。たとえば直帰率が高いページが複数ある場合、導線の設計に問題があると推測できます。改善してユーザビリティが向上すれば、滞在時間を増やすことも可能です。
間接的に上位表示につながるため、定期的に数値を確認しましょう。
直帰率が高いことが必ずしも悪い訳では無い
直帰率の高さが問題になるのは、ユーザーに複数のページの閲覧してほしい場合のみです。
一方で、網羅的に情報を提供しているようなコンテンツなどでは、直帰率の高さは問題にならないとGoogleも言及しています。
直帰率の高さが問題になるかどうかは状況によります。
直帰率の高さが問題になるのは、ユーザーがサイト内の複数のページを閲覧することが必要な場合です。たとえば、サイトのトップページがサイト内の他のページ(ニュース記事、商品ページ、購入手続きなど)の入り口として機能している状況で、多くのユーザーがトップページのみを閲覧しているとすると、高い直帰率は望ましくありません。
一方で、ブログのような 1 ページのみのサイトや、その他の 1 ページのみのセッションが想定されるようなコンテンツを提供している場合、直帰率の高さはまったく問題になりません。
性質を見極め、必要なページのみ改善しましょう。
直帰率が高い理由
直帰率が高い場合、以下4つの原因が考えられます。
- ページの表示速度が遅い
- モバイルフレンドリーになっていない
- ユーザーニーズとコンテンツ内容の乖離
- Webサイトの導線設計が悪い
それぞれ詳しく解説していきます。
ページの表示速度が遅い
ページの表示速度が遅いと、ユーザーはストレスを感じます。
より快適に閲覧できるサイトを探して、すぐ離脱するため、直帰率が上がる要因となります。
モバイルフレンドリーになっていない
モバイルフレンドリーとは、スマホでの閲覧にWebサイトを最適化することです。
近年、インターネットの閲覧に最も使われているのはスマホです。そのため、PC用のページしか用意していない場合、ユーザーは見づらさを感じます。
直帰の可能性があがるため、必ずモバイルフレンドリーを意識したサイトを制作しましょう。
ユーザーニーズとコンテンツ内容の乖離
検索から訪れたユーザーに対して、ニーズと乖離したコンテンツを提供している場合、直帰されてしまいます。
検索結果にはコンテンツが複数表示されているため、必要な情報を容易に探せるためです。事前に検索意図を調査し、適切なコンテンツを制作しましょう。
Webサイトの導線設計が悪い
導線設計が悪いと、目的のページがどこにあるのかわからないなどの問題が生じます。
ユーザーがページを探すのを諦めて、他のWebサイトに移動するため、直帰率が上がる原因になります。関連するページに移動させたい場合、わかりやすくリンクを設置するように意識しましょう。
直帰率の改善方法
直帰率は、以下5つの方法で改善できます。
- サーバーの表示速度を改善する
- JavaScriptやCSSを調整する
- レスポンシブデザインを採用する
- コンテンツの内容を見直す
- Webサイトの導線設計を最適化する
それぞれ詳しく解説していきます。
サーバーをスペックを上げる
Webサイトの表示速度が遅い場合、サーバーのスペック不足が考えられます。
レンタルサーバーを利用している場合、プラン変更だけで対応できるため、より高速表示ができるスペックにアップデートしましょう。
JavaScriptやCSSを調整する
JavaScriptやCSSを多用している場合、ページの読み込みに時間がかかります。
削減できるものがないか、より短い処理に変更できないか確認しましょう。
レスポンシブデザインを採用する
レスポンシブデザインとは、閲覧デバイスに合わせて自動的に最適なレイアウトを表示するWebデザインです。
閲覧環境によるユーザビリティの低下を防げるため、直帰率の上昇を防げます。実装も簡単なため、モバイルフレンドリーにする上でおすすめな方法です。
コンテンツの内容を見直す
画像を差し替えたり、文章をリライトすると直帰率の改善が見込めます。具体的には、以下のような施策を行いましょう。
- インフォグラフィックやピクトグラムを使用する
- 文章をわかりやすい言葉でリライトする
- 遷移先が目立つように装飾する
ページ内でのユーザー体験が向上すれば、他のページも見てみたいと思ってもらえる可能性が高くなります。見やすく、読みやすいコンテンツになるように改善を行いましょう。
Webサイトの導線を最適化する
ナビゲーションやコンバージョンの設計を見直せば、ユーザーがサイトを回遊しやすくなります。以下の変更や追加を行いましょう。
- グローバルナビゲーションの見直し
- サイドバーの活用
- フッターナビゲーションの最適化
- 内部リンクの装飾の見直し
- バナーやモーダルの活用
まとめ:直帰率の改善が必要なページを見つけて適切に対応しよう
直帰率は、ユーザーが他のページに遷移せずに離脱した割合です。Googleアナリティクスで確認でき、数値が高いほど改善が必要です。
しかし、直帰率が高いことが必ずしも悪いわけではありません。コンテンツの性質に応じて改善が必要なページを見極め、適切な対応を行いましょう。
弊社のSEOサービス「ランクエスト」では、お客様ごとに専任のコンサルタントがつき、戦略立案からコンテンツ制作、効果測定まで、すべて対応いたします。SEO対策にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。