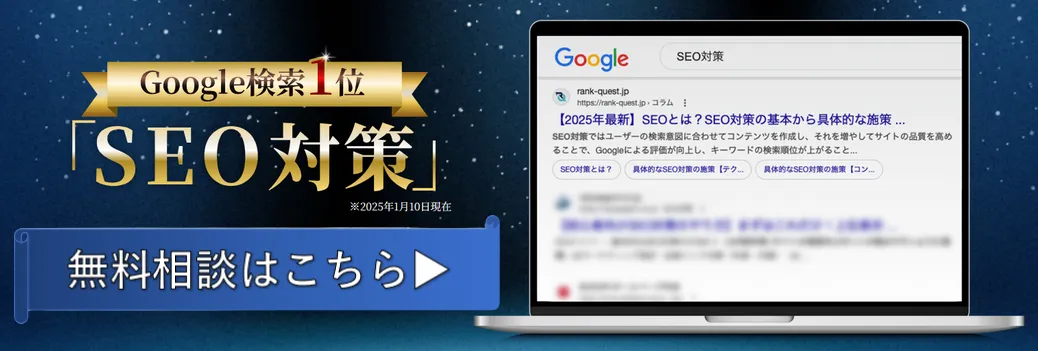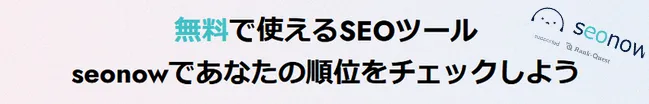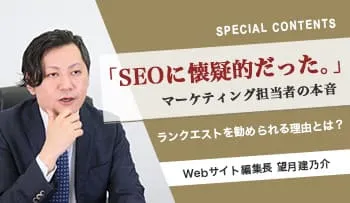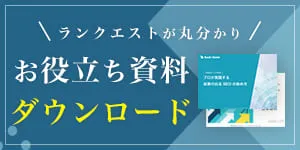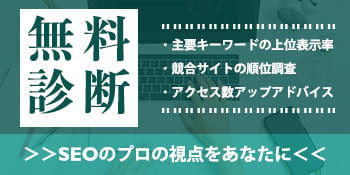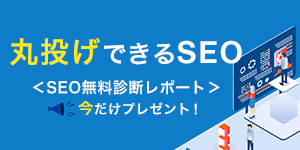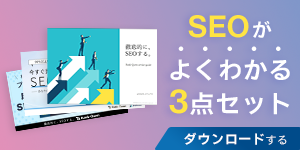インハウスSEOとは、SEO対策を内製化することです。最初は多くの社内リソースを使いますが、軌道に乗せれば低予算で多くの利益を得られるため、取り組む企業が増えています。
しかし、概要や取り組み方がわからない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、インハウスSEOのメリットや実行方法を解説していきます。
広告からの脱却を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
目次

今すぐ無料で、
あなたのSEO対策費用を
シミュレーション!
簡単な質問に答えるだけで、
最適なSEOプランと費用が無料でわかります。

SEO対策を
行ったことはありますか?

インハウスSEOとは?
インハウスSEOとは、自社でSEO対策に取り組むことです。外注費用を抑え、人件費のみで行えるため、利益率の高い集客方法です。
SEO対策は、Googleのガイドラインに則り適切な知識を身につければ、誰でも行えます。そのため、インハウスSEOに取り組む企業が増えています。
アウトソーシング(外注)との違い
SEOアウトソーシングとは、外部の専門企業やコンサルタントに委託することです。
特定の期間中に集中的なSEO対策が必要、社内にSEOの専門知識を持つ人員がいない場合などに有効です。
外部の専門家へ委託すれば短期間で効果的な施策を実行でき、専門的な知識や経験に基づいたアドバイスも受けられます。
なおSEOアウトソーシングを検討する際は、企業なら取引実績や成功事例、個人なら経歴やこれまでの実績などを比較検討するのがポイントです。
インハウスSEOのメリット
インハウスSEOには、以下3つのメリットがあります。
- 対策費用を抑えられる
- PDCAを回しやすい
- 車内でノウハウやデータを蓄積できる
- コミュニケーションコストが下がる
それぞれ詳しく解説していきます。
対策費用を抑えられる
インハウスSEOでは、外注費用がかかりません。対策に必要な作業は、大きく分けると以下の3つです。
- Webサイトの構築
- コンテンツ制作
- アクセス解析
Webサイトとコンテンツの制作は、WordPressなどの無料CMSを利用すれば、自社でも行えます。そのため、年間10,000〜20,000円程度のドメインサーバー代のみで運用可能です。
アクセス解析に関しても、GoogleアナリティクスやGoogleサーチコンソールなど、無料で使えるツールがあります。使い方さえ覚えれば、誰でも分析と改善が行えるため、費用をかけずにSEO対策に取り組めます。
しかし、いずれも専門知識を必要とするため、多大な学習コストを要することは理解しておきましょう。
関連記事:WordPressとは?機能やメリット・デメリットをわかりやすく解説
PDCAを回しやすい
インハウスSEOでは、社内で施策を完結できます。そのため、改善すべきポイントや施策に不備があった場合に、スムーズに連携できます。
各作業の担当者も明確なため、早期に課題解決が可能です。
社内でノウハウやデータを蓄積できる
インハウスSEOを行うことで、以下のようなデータとノウハウを車内に蓄積できます。
- 検索順位やアクセスデータ
- SEOやマーケティングの知識
- アクセス解析やサイトの解析のスキル
特に順位やアクセスのデータは、市場や業界の動向を掴むために貴重なデータです。競合が知り得ない情報を独自に入手し、戦略を立案できるため、大きな強みになります。
また、SEOに精通したスタッフが社内に増えることも、メリットといえるでしょう。
コミュニケーションコストが下がる
インハウスでSEO対策を進めれば、外部業者との打ち合わせや進捗報告といった手間を省けます。
委託費用がかからないため、契約内容や成果で費用が変動しないのもポイントです。また外部業者の指示取りに対策が進まないといった、コントロールの難しさもありません。
インハウスSEOのデメリット
インハウスSEOのデメリットは、以下の3つです。
- 承認を得られないこともある
- 膨大な社内リソースを使う
- 自社に適したスタッフの採用が必要
- SEOに精通したスタッフの育成や採用が必要になる
- 成果が出るまでに時間がかかる
- 最新情報をキャッチアップしにくい
それぞれ詳しく解説していきます。
承認を得られないこともある
インハウスSEOは短期的な成果だけではなく、中長期的な視点での投資と施策実行が不可欠です。
そのため短期的な成果を求められる企業では、SEO施策への予算承認が難しいケースも少なくありません。
インハウスSEOの承認を得るためには、期待できるトラフィックやコンバージョン数の増加といった具体的な数値をシミュレーションし、経営陣に提示しましょう。
数値をもとにしたシミュレーションでSEO施策の重要性が理解されれば、インハウスSEOの承認を得られやすくなります。
膨大な社内リソースを使う
SEO対策には、継続的なコンテンツ制作やアクセス解析、改善作業が必須です。そのため、長期的に作業を任せられるスタッフの確保が必要です。
また、効率的に成果を上げるためには、専門のチームを作らなければいけません。社内リソースが潤沢ではない場合、中途半端な施策となり失敗に終わる可能性が高いため、外注も検討してみましょう。
自社に適したスタッフの採用が必要
SEO対策は単に知識があれば良いというものではなく、Googleのアルゴリズムの仕組みを理解し、サイト構造やコンテンツを最適化するスキルが求められます。
そのため効果的なSEO対策を実施するには、豊富な経験と専門知識を持つSEO担当者が必要不可欠です。
SEO対策で必要な知識を習得し、サイトに合わせて戦略を立案できるようになるためには、それなりの時間と経験を要します。
短期的な成果を急いでいたり、専門的な知識が不足している場合は外部企業や個人への委託を検討しましょう。
SEOに精通したスタッフの育成や採用が必要になる
SEO対策は、闇雲に行なっても成果は出ません。そのため、Googleの検索エンジンやWeb制作に関する知識やスキルなどを有した、SEOに精通したスタッフが必要です。
学習すれば誰でも身につけられますが、実務レベルになるには時間を要します。実行を急ぐ場合はSEOのスキルを持った人材の採用を検討しましょう。
成果が出るまで時間がかかる
SEO対策は、長期的に安定した成果が得られる施策です。継続してコンテンツを発信することで、徐々に成果が現れるため、以下のケースでは向いていません。
- 結果を急いでいる
- 短期的な運用を想定している
上記に該当する場合は、広告の方がおすすめです。
SEO対策を行う際は、時間がかかることを社内の全員が認識し、余裕を持って取り組むことが大切です。特に最初のうちは、上位表示されるのに時間がかかるため、不安なら広告も併用するなど工夫しながら運用しましょう。
最新情報をキャッチアップしにくい
SEO対策では常に変化する検索エンジンのアルゴリズムに対応し、効果的な施策を継続的に実施しなければなりません。
そのためインハウスSEOでは社内担当者がWebマーケティングの最新情報を常に把握し、自社サイトに最適な施策を落とし込む必要があります。
アウトソーシングSEOであれば、専門知識を持った企業や人材が常に最新情報をキャッチアップしてくれます。
一方インハウスSEOの場合は通常業務をこなす傍らで、最新のSEOトレンドやアルゴリズムの変化を追わなければなりません。
繁忙期などで通常業務が忙しくなると、サイトのSEO対策までキャパシティが回らず、情報をキャッチアップできない可能性があります。
【関連記事】
東京・全国のおすすめSEO会社37選!業者の選び方や注意点も解説
SEO対策を外注するメリットは?外注すべきタイミング、業者の選び方、費用を解説
インハウスSEOに向いている企業
インハウスSEOに向いている企業には、以下の特徴があります。
- 社内でSEOの重要性が理解されている
- SEOに詳しいスタッフがいる
- SEOに取り組んでいる競合が少ない
それぞれ詳しく解説していきます。
社内でSEOの重要性が理解されている
SEOは、以下の理由から社内で重要性を理解してもらえないことも多いです。
- 多くの社内リソースがかかる
- 即効性がない
- 成果が理由を提示しづらい
インハウスSEOは、最初は多くの社内リソースを必要としますが、軌道に乗れば利益率の高い施策です。
しかし即効性がなく、成果が出る根拠が示しづらいこともあるため、社内で承認がおりないことも珍しくありません。
一方で、社内でSEOの重要性が理解されている場合は、協力してもらえる可能性が高いです。有利に施策に臨めるため、前向きな姿勢が見える際は積極的に提案しましょう。
SEOに詳しいスタッフがいる
インハウスSEOの成功には、専門知識を有した社内スタッフが不可欠です。競合に勝つためには、専門的なSEO知識とスピーディーな対策が求められます。
そのため、SEOを学びながら対応したり、他の業務と兼任したりすると、成果を上げるのが難しいです。該当する社員がいない場合は、専任のスタッフを採用するなどの対策を打ちましょう。
SEOに取り組んでいる競合が少ない
SEOに取り組んでいる競合が少ないと、成功する確率が上がります。競合サイトの数が少ないほど、上位表示されやすくなるためです。
また、SEOには先行優位性があります。先に上位表示してしまえば、有利に施策を展開できるため、早めに対策を行いましょう。
インハウスSEOの取り組み方
インハウスSEOは、以下の流れで取り組みます。
- 戦略設計
- 人員、予算の調達
- Webサイト構築とコンテンツ制作
- PDCAを回す
順番に詳しく解説していきます。
戦略設計
インハウスSEOが成功するかは、戦略設計で決まります。SEO対策で達成したい目標がブレると、その後の施策も曖昧になります。
たとえば、SEO対策を依頼したい企業の集客が目的の場合、コンバージョンは資料のダウンロードや電話問い合わせなどになります。
一方で採用が目的の場合は、SEOを使った認知拡大やブランディング、求人エントリーがコンバージョンになります。明確な目標設定をして、スムーズに運用するためにも戦略設計を行いましょう。
人員、予算の調達
目標が決まったら、達成に必要な期間から逆算し、必要な人員や予算を捻出します。インハウスSEOに必要なリソースは、以下のようなものがあります。
-
- Webサイトの構築
- SEOディレクション
- コンテンツ制作
- アクセス解析ツールの費用
特にWebサイトの構築は、外注か内製かで大きく費用が変わります。予算を避けない場合は、WordPressなどの無料CMSを利用すれば、コストを削減できます。
また社内リソースが足りない場合、外部ライターにコンテンツ制作を依頼する方法もあります。社内リソースと外注費用を照らし合わせて、より少ないコストで効率的に運用できるように計算しましょう。
Webサイト構築とコンテンツ制作
施策の準備が整ったら、対策に必要なWebサイトやコンテンツの制作を始めます。構築段階で、内部対策やユーザビリティを意識すれば、その後の対策を有利に進められます。
また、コンテンツはSEOにおいて最も重要です。成果を急いで内容が記事を量産しても、成果は出ません。必ず監修するスタッフを用意し、検索1位が狙えるコンテンツを継続して制作しましょう。
関連記事:コンテンツとは?テーマの決め方とマーケティングを成功させるコツを解説
PDCAを回す
SEOは、分析と改善を繰り返して初めて成功します。ツールを使ってアクセス解析をしながら、状況に応じた施策を継続して打ち出すことが重要です
新たな知識を身につけたり、A/Bテストを行なったりしながら、根気強く改善していきましょう。
また、必要に応じて社外の専門家にアドバイスを求めるのも効果的です。
インハウスSEOの段階とやるべきこと
インハウスSEOの段階とやるべきことは、以下の通りです。
- 導入フェーズ:支援会社を選ぶ
- 運用フェーズ:FBをもらいながらノウハウを蓄積する
- 卒業フェーズ:自社のみで運用する
インハウスSEOを進める段階を、「導入」「運用」「卒業」の3つのフェーズに分け、それぞれのフェーズでやるべきことを解説します。
では、1つずつ詳しく見ていきましょう。
導入フェーズ:支援会社を選ぶ
自社のSEOに関する知識が乏しい場合、いきなりインハウスSEOを始めても失敗する可能性が高いでしょう。
自社知識が乏しいのであれば、まずは外部のコンサルティング会社に相談し、SEOの基礎知識やノウハウを学ぶのが一般的です。
コンサルタントから指導を受けつつ自社のサイトの現状を分析し、改善点と施策を学習すれば、徐々にインハウスでSEO対策できるようになります。
運用フェーズ:FBをもらいながらノウハウを蓄積する
運用フェーズではコンサルティング会社からのフィードバック(FB)を参考に、社内の担当者が実際にSEO施策を実行しノウハウを蓄積します。
具体的には、自社サイトのコラム記事でFBを参考にSEO対策を実施し、検索順位の上昇や流入数の増加に繋げるといった具合です。
運用フェーズでは、社内担当者がSEOの具体的な効果を実感するのが大切です。より深い理解へとつながることで、将来的にはインハウスでSEO対策を完結できるようになります。
卒業フェーズ:自社のみで運用する
運用フェーズで十分な経験と実績を得られれば、外部業者のコンサルティングをなくしSEO対策の内製化を検討しましょう。
下記の表を参考に、インハウスSEOに完全移行しても問題ないか確認してみましょう。
|
項目 |
内容 |
|
SEOの基本知識 |
|
|
Web解析ツール |
|
|
Web制作の基本知識 |
|
|
その他 |
|
インハウスSEOは、専門的な知識やスキルが求められる高度な業務です。自社で完全に内製化するのであれば、最低でも上記の知識や技術は習得しておく必要があります。
インハウスSEOの担当者が取り組むべき業務
インハウスSEOが取り組むべき業務は、おもに以下の通りです。
- 目標設定
- 社内折衝
- キーワード調査・選定
- コンテンツの企画・作成
- コンテンツのリライト
- 内部対策
- 効果計測
- 外部リンク対策
- サイト改善
- コンバージョン率の最適化
インハウスSEOはやるべき項目が多いため、ある程度の時間と労力を要します。インハウスSEOで失敗しないためにも、上記の項目を確実にこなすのが重要です。
では、それぞれの業務を詳しく解説します。
目標設定
インハウスSEOの目標設定は、具体的な数値目標で設定しましょう。たとえば、「月間検索流入を10%増加」「特定ページのCV率を1%向上」などです。
加えて、短期的な目標と長期的な目標の両方を設定するのもポイントです。短期的な目標は、モチベーションを維持し進捗状況を可視化するために役立ちます。
長期的な目標は、最終的に達成したい状態を明確にすることでSEO施策の方向性を定められます。
なお、目標は達成可能でかつ挑戦的なものを設定しましょう。高すぎる目標は、モチベーションの低下につながるためです。
またKPI(Key Performance Indicator)を設定し、定期的に数値を計測することで目標への達成度を可視化することも大切です。
社内折衝
社長や部長といった権限者への社内折衝も、欠かせない業務です。なぜならSEOは単独で実施するものではなく、さまざまな部署との連携が必要になるためです。
たとえばSEO対策を進めるうえで必要な予算を確保するためには、上層部へのプレゼンや関係部署との交渉が欠かせません。
また開発チームと連携して、サイトの技術的な改善を依頼するといったケースも考えられるでしょう。
社内折衝を円滑に進めSEOの重要性を社内に周知すれば、よりスムーズに施策を進められます。各部署の役割を明確にし、連携体制の構築を疎かにしないのがポイントです。
キーワード調査・選定
SEOにおけるキーワード選定は、サイトの成功を左右する重要な要素です。ターゲットユーザーの検索意図を理解し、自社サイトに最適なキーワードを選定しましょう。
キーワード選定のプロセスは、大きく分けて4つのステップに分けられます。
|
手順 |
内容 |
|
1.ターゲットユーザーの検索意図を明確化する |
潜在ニーズと顕在ニーズから、ターゲットユーザーの検索意図を明確化する |
|
2.サイトのメインテーマと関連するキーワードを洗い出す |
関連語取得ツールなどを活用し、競合サイトがどのようなキーワードで上位表示されているか調査する |
|
3.キーワードをグルーピングする |
洗い出したキーワードを、テーマや検索意図ごとにグループ化する |
|
4.キーワードを絞り込み優先順位をつける |
検索ボリューム、競合の強さ、自社のコンテンツとの関連性などを考慮して、優先順位の高いキーワードを絞り込む |
なおキーワード選定で重要なのは、自社サイトとの関連性とターゲットユーザーの検索意図の両方を満たすことです。
関連語取得ツールや競合調査を使えば、多くのキーワードを探せます。ただし、それらすべてのキーワードを網羅的に対策するのは、現実的ではありません。
自社の強みや特徴を活かせるキーワードに焦点を当て、優先順位をつけて対策しましょう。
コンテンツの企画・作成
SEOで上位表示させるコンテンツを作成するためには、読者の心に響く、質の高いコンテンツを制作しましょう。
キーワードを詰め込んだだけの記事ではなく、読者の検索意図を的確に捉え悩みや疑問を解決するようなコンテンツを目指します。
コンテンツを作成するうえで最も重要なのは、自社のターゲットユーザーが抱える悩みや、達成したい目標への理解です。
ユーザーがどのような言葉で検索しているのか、どのような情報を探しているのかを徹底的に分析します。
そのうえで、ユーザーの検索ニーズを満たす情報を提供するコンテンツを企画し、作成しなければなりません。
では、実際にユーザーの検索意図はどのように分析すべきなのか詳しく解説します。
検索意図を考える
ユーザーの検索意図を考えることは、効果的なコンテンツ作成やSEO対策を実施するうえで重要です。
以下のポイントを参考に、ユーザーの検索意図を分析してみましょう。
|
検索意図を考えるうえでやるべきこと |
内容 |
|
キーワードの多角的分析 |
|
|
ユーザーのペルソナ設定 |
|
|
検索結果の調査 |
|
|
ユーザー行動データの分析 |
|
|
仮説の検証 |
|
「Googleが掲げる10の事実」にもある通り、ユーザーファーストを徹底するうえで検索意図の深堀りは欠かせません。
なおユーザーの行動は一定ではなく、常に変化するものです。定期的に分析し、コンテンツを継続的に改善しましょう。
タイトル(title)タグを正しくつける
SEOでサイトの集客力を高めるためには、タイトル(title)タグの最適化が欠かせません。
titleタグとはWebページのタイトルを指定するためのHTMLタグで、検索結果に表示されるページタイトルとして重要な役割を果たします。
titleタグの適切化は検索エンジンにページの内容を正確に伝え、より多くのユーザーに発見してもらうために必要不可欠です。
効果的なtitleタグを設定するには、ターゲットとするキーワードを適切な位置に盛り込み、ユーザーの興味を引くような魅力的なタイトルを作成します。
具体的には、下記の対策が効果的です。
- ターゲットキーワードはタイトルの先頭に配置
- タイトルタグの内容とページ内容は一致させる
- 検索結果画面での文字数を考慮し、titleは30文字前後でおさめる
なおキーワードを詰め込みすぎると不自然な文章になり、検索エンジンから低い評価を受ける可能性があるため注意しましょう。
メタディスクリプションを分かりやすく書く
SEOでサイトの集客力を高めるためには、titleタグだけでなく、メタディスクリプションの最適化も必要です。
メタディスクリプションとは、検索結果ページでタイトルの下に表示されるページ内容を簡潔に説明する文章のことです。
ユーザーは、検索結果に表示されたタイトルとメタディスクリプションを参考に、自分の探している情報がページに含まれているかを判断します。
そのためメタディスクリプションには、ページの内容を正確かつ魅力的に伝え、クリック意欲を高めるような文章を記載しなければなりません。
検索したキーワードを含め、ページの重要なキーワードを自然な形で盛り込みましょう。titleタグと同様に対策すれば、よりSEO効果を高められます。
なおメタディスクリプションはPCやスマートフォンでの表示を考慮し、100文字程度を目安に記載すると効果的です。
画像検索に対応する
文章だけではなく画像検索からも自社サイトへの流入を促し、SEO効果を高めましょう。
画像検索で自社の画像を上位表示させるためには、「alt属性」と呼ばれる画像の説明文を適切に設定します。
alt属性は、視覚障がいを持つユーザーが画像内容を理解するための補助的な役割を担います。また、検索エンジンが画像の内容を把握するうえでも欠かせない要素です。
そのためalt属性には、画像の内容を簡潔かつ正確に表すキーワードを含めます。
たとえば猫の画像なら、「かわいい・猫・寝顔」といったように、具体的なキーワードを複数組み合わせて記述しましょう。
具体性を持たせたキーワードを複数盛り込むことで、より多くの検索キーワードにマッチする可能性が高まります。
コンテンツのリライト
インハウスSEOにおいて既存コンテンツのリライトは、検索エンジンからの評価を高めサイトの集客力を向上させるうえで欠かせない施策です。
SEOにおけるリライトとは、公開済みの記事を検索エンジンの評価基準に合致するように書き直すことを指します。
検索エンジンは日々アルゴリズムを更新しています。そのため一度、上位表示された記事であっても、アルゴリズムが原因で検索順位が低下してしまう可能性があるのです。
リライトでは最新のSEOトレンドを踏まえ、記事の内容や構成を改善します。具体的にはキーワードの選定や配置を見直したり、文章の構成を整理したりといった作業です。
リライト後は記事の検索順位やアクセス数を計測し、効果検証します。また効果検証の結果で順位に改善が見られない場合は、複数回リライトすることもあります。
内部対策
SEOの内部対策とは、自社サイトそのものを最適化し検索エンジンからの評価を高めるための施策です。
サイトの構成やコンテンツの質、技術的な側面といったさまざまな要素を改善し、検索結果での表示順位を向上させます。
|
〜内部対策の例〜
|
上記のように、内部対策の施策は多岐に渡ります。外部対策(他サイトからのリンク獲得など)と並ぶ、SEO成功の鍵となる重要な要素です。
なおSEOに効果的な内部対策については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:SEOの内部対策とは?目的・効果や35種類のアプローチ方法を解説
効果計測
SEO対策の効果を最大限に引き出すためには、実施後の効果測定が必要不可欠です。SEO対策の実施前と後を比較し、施策の影響を数値で把握するのが重要です。
SEO効果測定では、おもに以下の3つの指標に注目します。
|
注目する指標 |
内容 |
|
検索順位 |
特定キーワードによる自社サイトの表示順位を確認する |
|
自然検索経由セッション数 |
検索エンジン経由での訪問者数を確認する |
|
自然検索経由CV数 |
自然検索経由でのユーザーが目標とするアクションを起こし回数を確認する |
なお効果測定を実施するためには、Google Analyticsなどのアクセス解析ツールが必要不可欠です。
また効果測定の結果は関係者の全員が共有できるよう、定期的にレポートを作成し共有しましょう。
外部リンク対策
SEO対策では自社サイトへのリンクとなる「外部リンク」が重要な役割を果たします。
外部リンクには「外部被リンク」と「外部発リンク」の2種類がありますが、とくに前者がSEOに大きな影響を与えます。
外部被リンクとは、他サイトから自社サイトへ貼られるリンクのことです。Googleは質の高いサイトからの被リンク数を、評価基準の1つにしています。
なぜなら被リンクが多いサイトは信頼性が高く、有益な情報を持っていると判断されるためです。良質な被リンクが多いサイトは、検索結果の上位に表示されやすくなります。
ただし不自然なリンク獲得は違反行為となり、サイトの評価を下げます。良質なコンテンツの作成や他サイトとの関係構築など、正当な手段で被リンクを獲得しましょう。
なお被リンクによるペナルティについては、以下の記事で詳しく解説しています。
サイト改善
サイト改善のために有効な方法は、おもに以下の4つです。
- 内部リンクを最適化する
- 重複コンテンツを避ける
- ページスピードを改善する
- スマートフォンでの表示を確認する
社内折衝が終わり本格的にインハウスSEOに着手したら、上記を基準にサイトを改善すると効果的です。では、1つずつ詳しく解説します。
内部リンクを最適化する
内部リンクとは、自社サイト内のページ同士を互いに繋ぐリンクのことです。内部リンクの最適化により、検索エンジンがサイト構造を深く理解できるようになります。
また内部リンクが最適化されたサイトはユーザー体験が高まり、サイトの滞在時間の向上にもつながります。
加えて重要なページへの内部リンクを集中させることで、該当ページへのアクセスを増やせるのも魅力です。CV率が高まることで、自社の収益につながるメリットも生じます。
重複コンテンツを避ける
サイト内に重複コンテンツがあると、検索エンジンのクロール率が下がります。無駄なクロージングをさせないためにも、重複コンテンツは削除すべきです。
検索エンジンのクローラーは、基本的にサイト内のすべてのページをクロールします。
重複コンテンツが多いと同じ内容のページを何度もクロールすることになり、クロール効率が低下します。結果、低品質なサイトと判断されサイト評価にも悪影響を及ぼすのです。
また同じ内容のページが乱立したサイトは、ユーザーにとっても使い勝手の悪いサイトです。サイトの離脱率が高まる原因にもなるため、重複コンテンツは避けましょう。
ページスピードを改善する
SEO対策において、ページの表示速度も重要な要素の1つです。サイトの各ページの表示速度が遅い場合、検索エンジンから評価が下がる原因となります。
ページの表示速度を改善するためには、おもに以下の4つの対策が有効です。
|
ページスピードの対策方法 |
内容 |
|
サーバーとの通信回数の削減 |
|
|
画像の最適化 |
|
|
データ通信量の削減 |
|
|
表示領域内のコンテンツの最適化 |
|
ページの表示速度は、ユーザー体験の向上につながる重要な要素です。検索エンジンからの評価も高まるため、意識的に取り組みましょう。
スマートフォンでの表示を確認する
スマートフォン表示の最適化も、SEO対策では重要な要素となります。
Googleは2018年に「モバイルファーストインデックス」を導入し、スマートフォン版のページを優先して評価するようになりました。
つまりスマートフォンで快適に閲覧できないサイトは、サイトの評価が下がり検索順位にも影響する可能性があります。
レスポンシブデザインやモバイルフレンドリーテストを活用し、スマートフォンでの表示に問題がないか確認しましょう。
コンバージョン率の最適化
SEOで集めた多くの訪問者を成果へと繋げるためには、コンバージョン率の最適化(CRO)が欠かせません。
CROとは、サイトを訪れたユーザーが購入といったアクションを起こす割合を最大化するための施策です。
単に多くの訪問者を獲得するだけでなく、いかに訪問者を顧客へと転換させるかが重要になります。
具体的にはサイトの構造をより分かりやすくしたり、購買意欲を刺激するようなデザインに変更したりなどです。
SEOで多くのユーザーをサイトに誘導し、CROで求めるアクションを起こしてもらうことが、CVR率を高めるポイントです。
インハウスSEO以外の選択肢
インハウスSEO以外の選択肢を、2つ紹介します。
- セミインハウスSEO
- アウトソースSEO
自社の予算や状況に応じて、最適な方法でSEO効果を高めるのが効果的です。では、1つずつ詳しく解説します。
セミインハウスSEO
セミインハウスSEOとは自社だけで内製化するのではなく、SEO対策の一部を外部の専門業者に委託する、いわばハイブリッドな手法です。
セミインハウスSEOのメリットとデメリットは、以下の通りです。
|
セミインハウスSEOのメリット |
セミインハウスSEOのデメリット |
|
|
「SEO対策の基礎知識はあるが専門的な知識は不足している」といった場合には、セミインハウスSEOが効果的です。自社に足りない部分を外部委託でサポートできます。
アウトソースSEO
組織の体制としてインハウスSEOが困難な場合は、完全に外部業者にSEO対策を委託するアウトソースSEOを検討しましょう。
アウトソースSEOのメリットとデメリットは、以下の通りです。
|
アウトソースSEOのメリット |
アウトソースSEOのデメリット |
|
|
SEO対策に専任の人材がいなかったり、高度な分析や戦略が必要な場合はアウトソースSEOを検討しましょう。
アウトソースSEOを検討する際は、ぜひ弊社ランクエストまでご相談ください。
作成したSEOコラムの投稿作業だけでなく、内部対策の反映や新規ページの制作、ユーザビリティを改善するUI/UXのアップデートなど、あらゆるSEO対策に対処します。
インハウスSEOが成功すれば低予算で大きな利益が得られる
インハウスSEOで成功すれば、高い利益率で集客や採用を内製化できます。運用が社員の教育にもなり、競合が持っていない独自のデータやノウハウを得ることも可能です。
しかし、成果が出るまでに時間がかかるため、社内の承認が得られないことも多いです。また運用序盤には多くの社内リソースやSEOに精通した人員が必要になるため、対策を行なっても成果は出ません。
この記事を参考に、インハウスSEOのメリットとデメリットを理解した上で、計画的に対策を行いましょう。
弊社のSEOサービス「ランクエスト」では、お客様ごとに専任のコンサルタントがつき、戦略立案からコンテンツ制作、効果測定まで、すべて対応いたします。SEO対策にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
SEO対策とは?はこちら
SEOの外注(SEO代行)をご検討の方はこちら
SEOコンサルサービスをご検討の方はこちら
SEO対策費用についてはこちら
SEO会社をご検討の方はこちら