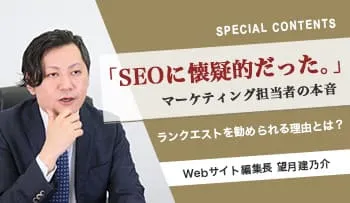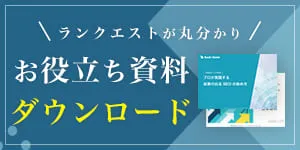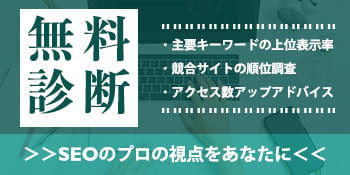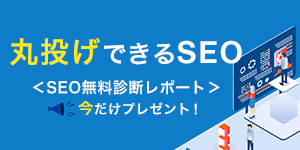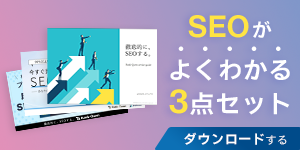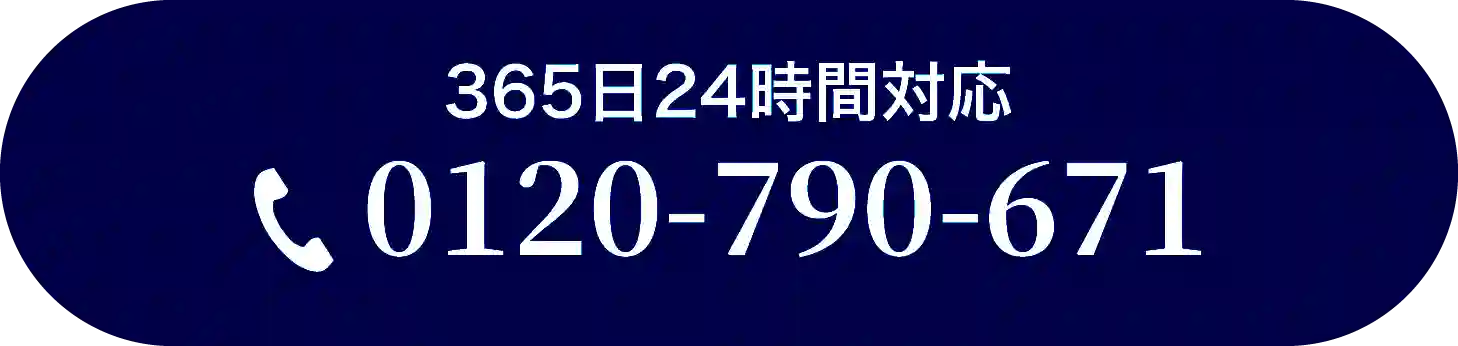目次
モバイルフレンドリーとは?SEOにおける重要性も解説
モバイルフレンドリーという言葉をよく耳にするものの、詳細までは分からないという方は多いのではないでしょうか。
モバイルフレンドリーはSEOにも深く関係しているため、Web集客を行ううえでは理解が必須です。
本記事ではモバイルフレンドリーの概要から必要な理由、具体的な対策方法など、包括的に解説しています。
SEOからの集客を増やしたい方は、ぜひ参考にしてください。

今すぐ無料で、
あなたのSEO対策費用を
シミュレーション!
簡単な質問に答えるだけで、
最適なSEOプランと費用が無料でわかります。

SEO対策を
行ったことはありますか?

モバイルフレンドリーとは
モバイルフレンドリーとは、スマホやタブレットなどのモバイル端末で、Webサイトが快適に閲覧できる状態を指します。
具体的には、以下のような点に配慮されたWebサイトのことです。
- 文字が小さすぎて読みにくくないか
- リンクやボタンがタップしやすい間隔で配置されているか
- ページの読み込み速度が遅くないか など
モバイルフレンドリーに対応すれば、ユーザーがWebサイトを閲覧しやすくなり、行動が活性化します。
対応すれば直帰率や離脱率が改善されたり、お問い合わせにつながりやすくなったりと、SEOに良い影響を間接的にもたらします。
モバイルフレンドリーにすべき理由
以下4つの理由から、モバイルフレンドリーの対応は必須とされています。
- スマートフォンユーザーが増加しているため
- ユーザーエクスペリエンスを向上させるため
- 検索ランキングに直接影響するため
- PV数が増加するため
それぞれ詳しく解説します。
理由①スマートフォンユーザーが増加しているため
モバイルフレンドリーへの対応が必須な理由は、スマホユーザーの数がPCを上回っているからです。
総務省が2024年に行った調査によると、日本国内でインターネット閲覧時の使用するデバイスにスマホと答えた人は91%に上ります。
スマホが2022年、2023年から3年連続で上昇している一方で、PCユーザーは年々減少しています。
SEOの原理原則はユーザーファーストです。
そのため、Webサイトのモバイルフレンドリー対応が必須になるのも自然な流れといえます。
理由②ユーザーエクスペリエンスを向上させるため
Webサイトがモバイルフレンドリーに対応すると、ユーザーエクスペリエンス(UX)の向上につながります。
UXとは、ユーザーがWebサイトを利用する際に感じる使いやすさや満足度のことを指します。
つまり、ユーザー体験のことです。
UXが向上すると、ユーザーが快適にWebサイトを閲覧できるようになるため、滞在時間や回遊率が向上し、直帰率が低下します。
また、直感的に操作できるWebサイトはユーザーにストレスがかからないため、信頼性の向上にも寄与します。
UXの向上には、文字サイズやボタン配置の最適化、ページの読み込み速度改善などが有効です。
間接的なSEO評価の向上や問い合わせの獲得や商品購入などのコンバージョンの増加など、さまざまな恩恵が期待できます。
理由③検索ランキングに直接影響するため
モバイルフレンドリーへの対応は、検索順位に直接影響します。
Googleは現在、PC版の検索結果もスマホ用のWebサイトの評価を基準に決定しているためです。
| 2024 年 7 月 5 日以降は、スマートフォン用 Googlebot のみでウェブサイトをクロールし、インデックスに登録します。コンテンツをスマートフォンでまったく閲覧できないウェブサイトは、インデックス登録の対象外となります。 |
つまり、モバイルフレンドリーではないWebサイトは、インデックスすらされないおそれがあります。
インデックスされたとしても、Googleの意向に即さないコンテンツであるため、上位表示は難しいでしょう。
仮に上位に表示されても、スマホユーザーの利便性が低いと、SEO評価も徐々に低下していきます。
したがってSEOを意識するうえでは、Webサイトのモバイルフレンドリー対応は欠かせません。
Googleの意向を理解し、スマホファーストなWebサイトを構築しましょう。
理由④PV数や滞在時間が増加するため
Webサイトがモバイルフレンドリーになると、PV数や滞在時間が増加します。
スマホ用にWebサイトを最適化すると、UXが改善され、ユーザーの快適性や回遊性が向上するためです。
ユーザーの行動が活発になれば、SEO評価の向上も期待できるため、さらなるアクセス増加も見込めます。
反対に、スマホでの視認性や操作性が悪いと、ユーザーは離れていきます。
PVや滞在時間の低下が、間接的に順位の低下やコンバージョンの減少につながるため注意が必要です。
モバイルフレンドリーに対応すれば、SEOに良いサイクルが生まれ、Webサイトの集客力が向上します。
小さな画面でも見やすく、直感的に操作できるWebサイトを構築するのがポイントです。
SEOにおけるモバイルフレンドリーの重要性
SEO(Search Engine Optimization)とは、検索エンジンからの自社サイトの評価を高め、検索結果で上位表示を狙う施策のことです。
SEOにおいて、モバイルフレンドリーへの対応は重要な要素となっています。
理由となるのがGoogleが2025年4月に開始した、モバイルフレンドリーアップデートです。
モバイルフレンドリーアップデートにより、モバイル版の検索結果において、スマホで見やすいWebサイトの順位が引き上げられました。
これにより、モバイルフレンドリー対応がSEO評価に直接的な影響を与える要素の一部となりました。
また、SEOにおいてモバイルフレンドリーが重要な理由に、ページエクスペリエンスが評価指標になっていることも挙げられます。
ページエクスペリエンスは、ユーザー体験を評価する指標で、Webサイト全体で優れた体験を提供することを推奨しています。
評価を落とさないためには、以下のような項目の最適化が必要です。
| 項目 | 概要 |
| モバイルフレンドリー | スマホでの閲覧に最適化されているか |
| Core Web Vitals | ページの表示速度など数値が良好な状態を保てているか |
| セキュリティ | SSL化などユーザーが安心して閲覧できる環境になっているか |
| 広告体験 | 大量の広告を挿入したり、インターステイシャル広告など視認性を下げる広告が使用されたりしていないか |
| Webサイト構造 | ユーザーがメインコンテンツとサブコンテンツを簡単に区別できるような設計になっているか |
ページエクスペリエンスの要因の1つとなっていることからも、モバイルフレンドリー対応がSEOにおいて重要であることが分かります。
対応は一朝一夕では難しいため、以下の記事も参考にSEOの基礎部分から見直しを行いましょう。
モバイルファーストインデックスとは
モバイルファーストインデックス(MFI)とは、GoogleがWebページを評価する際に、モバイル版のコンテンツを基準にインデックスする仕組みのことです。
2018年3月26日から段階的に展開を開始し、2023年10月31日にすべてのWebサイトの移行が完了しました。
また、2024年7月4日にはPCによるクロールが終了し、以降はスマホ用のページでSEO評価が行われています。
| 現在依然としてパソコン用 Googlebot でクロールされている少数のウェブサイトも、2024 年 7 月 5 日以降は、スマートフォン用 Googlebot でクロールされるようになります。 |
モバイルファーストインデックスにより、モバイルでの表示や操作性が不十分なサイトは、検索順位を上げるのが難しくなりました。
Googleは以下の対応を行い、運営するサイトがモバイルファーストインデックスに最適化されているか確認するように推奨しています。
- モバイルフレンドリーに対応する
- Googleがモバイルページにアクセスしてレンダリングできるようにする
- PCとモバイルでコンテンツの内容を同一にする
- PCとモバイルの両方に構造化データを設置する
- PCとモバイルページでメタデータを統一する
- 広告の配置場所を確認する画像や動画コンテンツのサイズやファイル形式を最適化する
参考:モバイルサイトとモバイルファースト インデックスに関するおすすめの方法|Google検索セントラル
モバイルファーストインデックス以降のSEO対策では、スマホのデザインを基準にWebサイトを作成することも増えています。
具体的な対応方法は、以下の記事で詳しく解説しているため参考にしてください。
モバイルフレンドリーテストツールの終了について
かつてGoogleは、モバイルフレンドリーテストを提供していましたが、2023年12月1日に提供を終了しています。
しかし、モバイルフレンドリーがSEOに直接的な影響を与える以上、定期的な確認は不可欠です。
そのため、Googleサーチコンソールなどの別のツールを用いて、対応状況を確認する必要があります。
具体的な方法は、次項で詳しく解説します。
モバイルフレンドリーかどうかをチェックする方法
以下3つのツールを使えば、モバイルフレンドリーの対応状況を確認できます。
- Googleサーチコンソール
- Google PageSpeed Insights
- Lighthouse
いずれもGoogleが提供している無料ツールであるため、手軽に利用できます。
使い方をツールごとに詳しく解説します。
方法①Googleサーチコンソール
Googleサーチコンソールは、Webサイトの問題点や検索エンジン上でのユーザーの動きを分析できるツールです。
「ウェブに関する主な指標」という機能があり、Webサイトの閲覧時に発生している問題を確認できます。
確認方法は、以下のとおりです。
- Googleサーチコンソールにログイン
- サイドバーの「ウェブに関する主な指標」をクリック
- 「モバイル」項目の「レポートを開く」をクリック
- 表示される問題点を確認する
なお、ステータスは「良好」「改善が必要」「不良」の3つがあり、良好ではないページがあった場合に問題点として報告されます。
データは日々更新されるため、定期的に確認することが大切です。
Googleサーチコンソールの使い方は、以下の記事で詳しく紹介しているため参考にしてください。
方法②Google PageSpeed Insights
Google PageSpeed Insightsは、Webページの表示速度に関係する「Core Web Vitals」の計測ツールです。
ページの表示速度はユーザーの満足度に直結するため、モバイルフレンドリーにおいても、重要な要素となっています。
Google PageSpeed Insightsを使えば、PCとモバイルそれぞれの改善点を確認できます。
確認方法は、以下のとおりです。
- 「Google PageSpeed Insights」にアクセスする
- 計測したいWebサイトのURLを入力する
- 「携帯電話」タブ内の指標を確認する
各指標が点数付きで表示されるため、直感的に問題点を特定可能です。
エラーが出ている箇所は、原因と理由が合わせて表示されるため、その後の改善対応もスムーズに進められます。
Google PageSpeed Insightsを使って定期的に改善点を見つければ、中長期的に優れたUXを提供できるでしょう。
Google PageSpeed Insightsの詳細な使い方は、以下の記事で詳しく解説しているため参考にしてください。
方法③Lighthouse
Lighthouseは、「Google PageSpeed Insights」をGoogle Chromeの拡張機能として利用できるツールです。
初回のみインストールの手間がありますが、その後は手軽に利用できるため、モバイルフレンドリーテスト終了以降広く使われています。
分析は、Google Chromeに「Lighthouse」をインストールした後、以下のいずれかの方法で行えます。
①拡張機能から使用する
- 分析したいWebサイトを開く
- 右上のLighthouseのアイコンをクリックする
- 「Device」項目の「Mobile」にチェックを入れる
- 「Generate report」をクリック
- 「携帯電話」タブ内の指標を確認する
②デベロッパーツールから使用する
- 分析したいWebサイトを開く
- 「F12」を押す or 右クリックすると表示される「検証」をクリック
- デベロッパーツール上部の「Lighthouse」タブをクリック
- 設定を以下に調整
- モード:ナビゲーション(デフォルト)
- デバイス:モバイル
- カテゴリ:すべてチェック
- 「ページ読み込みを分析」をクリック
- 表示される数値を確認する
拡張機能から起動すると、難しい操作が不要で使いやすくなっています。
デベロッパーツールからの起動は少し難しいですが、問題点の検証にスムーズに移行できるため、プログラミングの素養がある方におすすめです。
Lighthouseがもっとも手軽にモバイルフレンドリーを検証できるツールであるため、インストールだけでも済ませておきましょう。
モバイルフレンドリーへの対応方法
モバイルフレンドリーに対応させるには、デバイスの種類に応じて、デザインのレイアウトや解像度を自動で調整する設計が必要です。
Googleはその手段として、以下3つの方法を提示しています。
- レスポンシブWebデザイン
- ダイナミックサービング
- セパレートタイプ
以下では、対応方法別の詳細を解説します。
レスポンシブWebデザイン
レスポンシブWebデザインとは、パソコンやスマホ、タブレットなど、デバイスの画面サイズに応じて自動で最適化されるデザインのことです。
デバイスごとにHTMLを分ける必要がなく、設計や維持管理が簡単な点がメリットとして挙げられます。
また、URLもすべてのデバイスで同一となるため、URL正規化などのSEO対策も簡単で、ユーザーの混乱を招きにくいのが特徴です。
Webサイトの運営者とユーザーの双方に使いやすい点から、モバイルフレンドリーにもっとも適した手法とされています。
| Google では、実装と維持が最も簡単なデザイン パターンとしてレスポンシブ ウェブ デザインをおすすめしています。 |
レスポンシブWebデザインについては、以下の記事でも詳しく解説しているため参考にしてください。レスポンシブデザインとは?
ダイナミックサービング
ダイナミックサービングは、同一URLでアクセスする端末ごとに異なるHTMLを提供する方式で、動的な配信とも呼ばれます。
すべてのデバイスでURLが同一となるため、SEO対策で不具合が起こりにくく、ユーザビリティも担保可能です。
しかし、実装にはデバイスに応じて最適なコンテンツを表示できるように、サーバー側で挙動を制御する必要があります。
構築の難易度や維持管理面で複雑性が増すため、特別な理由がなければレスポンシブWebデザインの選択をおすすめします。
セパレートタイプ
セパレートタイプは、内容が同じページに対して、PC用とモバイル用でURLを別々に用意する手法です。
たとえば、PC用は「https://example.com」、モバイル用は「https://example.com/mobile」といった形でURLを分けます。
端末ごとに完全に異なるHTMLやCSSを使用できるため、表示や操作性を高度に最適化可能です。
ただしURLが異なるため、URLを緻密に正規化しないとSEO評価が分散する、改修の際に作業量が増えるなどデメリットもあります。
セパレートタイプは、レスポンシブWebデザインが登場する以前は主流な方法でした。
しかし現在ではCSSが発展し、大半のデザインは共通のHTMLでも実現できるため、無理に選択する必要はないでしょう。
モバイルフレンドリーに対応したWebページを作成するポイント
モバイルフレンドリーなWebサイトを作成するには、単にレイアウトを調整するだけでは不十分です。
以下7つのポイントを意識し、最適化することでよりSEOに適したWebサイトに近づけられます。
- viewportの設定をしてスマートフォンの画面サイズに合わせる
- レスポンシブデザインを採用する
- ページの読み込み速度を速くする
- 読みやすい文字や文章にする
- タップしやすいボタンやリンクにする
- 情報をコンパクトに格納できるメニューを検討する
- クリエイティブ(広告)の見え方を確認する
ポイントごとに詳しく解説します。
ポイント①viewportの設定をしてスマートフォンの画面サイズに合わせる
viewportとは、スマホやタブレットなどの画面で実際に表示される、Webページの領域幅のことです。
viewportを正しく設定することで、デバイスの画面幅に応じてデザインやレイアウトが自動で調整されます。
意図通りのデザインで表示できるようになり、ユーザーがスクロールや拡大縮小を繰り返す手間も減らせます。
設定は、HTMLの内に以下のmetaタグを追加するだけです。
| <meta name=”viewport” content=”width=device-width, initial-scale=1″> |
content属性に記されている値は、以下の意味を持ちます。
| width=device-width | 表示幅をデバイスの画面幅に合わせる |
| initial-scale=1 | ズームレベルの初期値を1にする |
viewportの設定に不具合があると、エラーが出るおそれがあるため注意が必要です。
おもなエラーと原因、解決策を表にまとめました。
| エラー名 | おもな原因 | 解決策 |
| ビューポートが設定されていません | viewportが設定されていない | <head>内にviewportを追加する |
| ビューポートが「端末の幅」に収まるよう設定されていません | viewportの設定が固定幅になっている | initial-scaleを1にする |
厳密には、viewportだけではモバイルフレンドリーへの対応は完結しません。
しかし、正しく設定すればスマホ用に実装したCSSを正しく反映できます。
ポイント②レスポンシブWebデザインを採用する
レスポンシブWebデザインとは、画面サイズに応じてWebページのレイアウトや要素の表示を自動調整するデザイン手法です。
Googleも公式に推奨しており、構築や維持管理が簡単なことから、モバイルフレンドリーに対応しやすい利点があります。
レスポンシブWebデザインは、以下の手順で実装します。
- HTMLにviewportを記述する
- CSSファイルにmediaクエリを記述する
HTML側のviewportで、デバイスごとの表示幅を最適化し、CSSのmediaクエリで画面幅に応じて反映する装飾を出し分けます。
たとえば、以下のようにCSSを記述するとデバイスの画面幅が「640px以下」の時に画像がスマホ用のサイズになります。
| img { /*PC用の画像のサイズ*/
width: 1280px; } @media screen and (max-width: 640px) { /*スマホ用の画像のサイズ*/ width: 480px; } |
また、「display: none」を使用するなど、工夫をすればデバイスごとにコンテンツの出し分けも可能です。
CSSの記述により、柔軟なデザインを実装できるため、モバイルフレンドリー対応を検討する際はレスポンシブWebデザインがおすすめです。
ポイント③ページの読み込み速度を速くする
モバイルフレンドリーにおいて、ページの読み込み速度は重要です。
モバイル端末では、通信環境が低速であったり、契約プランによってデータ量が制限されることがあります。
つまり、PCでの閲覧環境に比べて通信環境に難がある可能性が高くなるため、より一層読み込み速度に気を遣う必要があるのです。
ページの読み込みが遅いとユーザーは離脱しやすくなり、SEOに悪影響を及ぼします。
以下のポイントを意識し、読み込みをできる限り軽くしましょう。
- 画像や動画のファイルサイズを圧縮する
- 不要なJavaScriptやCSSを削減する
- キャッシュを活用して再訪問時の表示を高速化する
SEOにおける表示速度の重要性は、以下の記事でも詳しく解説しているため参考にしてください。
ポイント④読みやすい文字や文章にする
モバイルフレンドリーに対応する際は、文章の読みやすさも意識しましょう。
スマホは画面幅が小さいため、PCでは2〜3行程度の文章が、6〜10行程度になることがあります。
対策を打たないと画面が文字だらけになり、ユーザーは読みづらさを感じます。
ユーザー体験を損ねて早期離脱が増えると、SEO評価が下がるおそれがあるため注意が必要です。
読みやすい文章を作成するために、以下のポイントを意識しましょう。
読みやすくするポイントを表にまとめました。
| ポイント | 内容 |
| 文字サイズ | 16px以上にする |
| 行間 | 文字サイズの1.5倍〜2倍に設定する |
| 段落 | 適度に改行を入れて区切る |
| 文字数 | 1文を60文字程度にまとめる |
| 見出し | 内容を端的にまとめる |
上記を意識すれば、コンテンツに適度な余白が生まれ、可読性が向上します。
ポイント⑤タップしやすいボタンやリンクにする
モバイル端末では指で画面をタップして操作するのが基本です。
クリックの際に画面に触れる面積が大きいため、ボタン同士が近すぎたり、リンクが小さすぎたりすると、ユーザビリティを損ねます。
ユーザーが離脱する原因になるため、意識して対策する必要があります。
注意すべきポイントは以下です。
- ボタンやリンクのサイズは指で押しやすい大きさに設定
- タップ対象の間隔を十分に空ける
- 重要なリンクは目立つ色や形状で表示
Googleは、ボタンのサイズを最低でも「48px × 48px」に設定し、間隔は「8px」以上空けることを推奨しています。
| 方法 1: タップ ターゲットが小さすぎる場合は、サイズを大きくする。タップ ターゲットが 48 x 48 ピクセルのものは、監査で不合格になることはありません。これ以上大きくしてはいけない要素(アイコンなど)がある場合は、padding プロパティを増やしてみます。
方法 2: margin などのプロパティを使用して、近すぎるタップ ターゲットの間隔を広げる。タップ ターゲット間の間隔は 8 ピクセルから始めるとよいでしょうが、特に非常に小さなターゲットの場合、監査に合格するには十分な間隔がない場合があります。 |
また、レイアウトやサイズに加えて、誤タップを防止するために目立たせる工夫も大切です。
PCとはデバイスとの操作方法が異なることを理解し、適切なデザインを施しましょう。
ポイント⑥情報をコンパクトに格納できるメニューを検討する
モバイルデバイスの画面には限られたスペースしかないため、メニューの数が多いと視認性を損ねます。
ユーザビリティを損ねないように、要素をコンパクトに格納する工夫が必要です。
モバイルフレンドリーに最適なメニューとして挙げられるのが、以下の2つです。
| メニュー名 | 概要 |
| ハンバーガーメニュー | 画面の端に三本線のアイコンを配置し、タップによって開閉できる。グローバルナビなどをひとまとめにする際に使用される。三本線がハンバーガーに見えることが名前の由来。 |
| アコーディオンメニュー | タップによって開閉できるメニュー。子カテゴリーなどをコンパクトにする際に使用される。開閉部分のデザインがアコーディオンの蛇腹部分に見えることが名前の由来。 |
必要に応じて使い分ければ、ユーザーが必要な情報にスムーズにアクセスできるようになります。
ポイント⑦クリエイティブ(広告)の見え方を確認する
モバイル端末の画面サイズはさまざまな種類があるため、意図せずクリエイティブがズレて表示されることがあります。
視認性が落ちるのはもちろん、ミスタップを誘発するおそれもあるため注意が必要です。
たとえば、ユーザーが画面をスクロールするためにタップした瞬間、突然現れた広告をクリックしてしまうケースです。
このような体験はユーザーに強いストレスを与え、信頼性の低下や離脱につながります。
そのため、以下のポイントを複数のデバイスで確認しましょう。
- 広告やバナーのサイズが画面幅に収まっているか
- タップ領域がほかの要素と重なっていないか
- 動的に表示されるクリエイティブが正常に位置調整されるか
すべてのデバイスでクリエイティブを意図通りに表示できれば、優れたユーザー体験を提供できます。
モバイルフレンドリーに対応したWebページを作成する際の注意点
モバイルフレンドリー対応を進める際に注意すべき点は、PC版とモバイル版でコンテンツ量を同じにすることです。
たとえば、スマホの小さな画面に合わせて、情報量を調整するのは避けましょう。
モバイルファーストインデックス以降のGoogleは、モバイル向けコンテンツの情報を軸にSEO評価を行います。
モバイル向けコンテンツの情報量が少ないと、検索順位に直接的な悪影響が出るおそれがあるため注意が必要です。
また、PCとスマホで情報量に差があると、デバイスごとに異なるユーザー体験を提供することになります。
Googleが提唱するユーザーファーストなWebサイトからは逸脱するため、SEOに適しているとはいえません。
情報の出し方を変える、文字サイズを画面サイズに合わせて調整するなど、情報量ではなくデザインで視認性を高める工夫をしましょう。
まとめ
スマホユーザーの増加に伴い、現代のSEOではモバイル向けコンテンツを軸に評価が行われます。
そのため、モバイルフレンドリーの対応は欠かせない施策です。
モバイルフレンドリーなWebサイトは、Googleから評価を得やすいのはもちろん、優れたユーザー体験の提供にもつながります。
直接的・間接的双方からSEOに影響するため、本記事を参考に必ず対応しましょう。
しかし、レスポンシブWebデザインの設計など、0からのモバイルフレンドリー対応には専門的な知識も必要です。
Rank-Questでは、4,300社以上のお客様のSEO対策を支援してきた経験から、現代のアルゴリズムに適した施策をご提案しています。
お客様ごとに必要なスマホ対応の具体策も、丁寧にご説明いたしますので、お気軽にお問い合わせください。