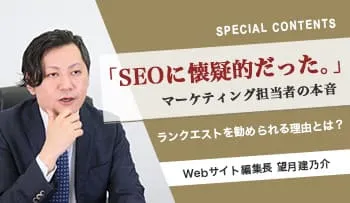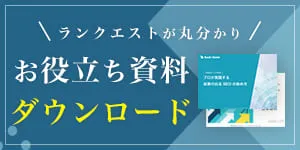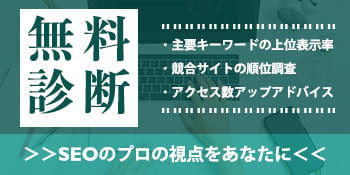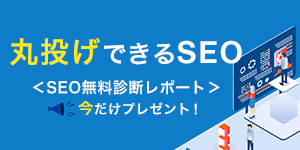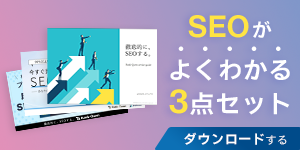Googleの検索結果にAIの回答が表示されるようになったけど、これが一体何なのかよくわからない…。
「AI Overviewsと以前聞いたSGEって、結局何が違うんだろう」と感じている方もいるかもしれません。
この新しい検索の形をいち早く理解し、日々の情報収集に賢く活用していきましょう。
この記事では、Google検索に新しく登場したAI機能について詳しく知りたい方に向け、
– AI Overviewsの基本的な仕組みと特徴
– SGEとの具体的な違い
– AIの回答が参照したサイトを確認する裏ワザ
上記について、解説しています。
AI Overviewsの仕組みがわかれば、これからの情報収集がもっとスムーズで快適になるはずです。
ぜひ最後まで読んで、新しい検索体験を使いこなしてください。
目次

今すぐ無料で、
あなたのSEO対策費用を
シミュレーション!
簡単な質問に答えるだけで、
最適なSEOプランと費用が無料でわかります。

SEO対策を
行ったことはありますか?

AIOverviewsとは何か?
AI Overviewsとは、Google検索を利用した際に、AIが質問に対する要約を自動で生成し、検索結果の最上部に表示してくれる画期的な新機能です。
これまでのように複数のWebサイトを一つひとつ開いて情報を探す手間が省け、まるでAIと対話するように素早く答えを得られるようになりました。
この機能が導入された背景には、ユーザーがより直感的かつ効率的に情報を得たいというニーズの高まりがあります。
インターネット上には膨大な情報が存在するため、本当に知りたいことへたどり着くまでに時間がかかってしまうケースも少なくありませんでした。
AI Overviewsは、そうした検索における手間や時間を大幅に短縮し、より質の高い検索体験を提供することを目的としています。
例えば、「ノートパソコンの選び方」と検索したとしましょう。
従来であれば、比較サイトやレビュー記事をいくつも読み解く必要がありました。
しかしAI Overviewsを利用すると、「価格」「スペック」「用途別」といった観点から、おすすめのモデルや選ぶ際の注意点をまとめた概要が最初に提示されるのです。
このように、複雑で多角的な情報が必要な検索に対しても、AIが整理した答えを直接示してくれる点が大きなメリットと言えるでしょう。
SGEとの関係性と役割
AI Overviewsとは、Google検索の結果最上部にAIが生成した概要を表示する新機能です。これは、かつて「SGE(Search Generative Experience)」という名称で試験運用されていた機能が正式版となったもので、両者は密接な関係にあります。具体的には、SGEは一部のユーザーが試用できる「Search Labs」内で提供されていた、いわばプロトタイプの名称でした。
そして2024年5月14日に開催された「Google I/O」を機に、その技術が「AI Overviews」として正式にサービスインしたのです。したがって、SGEはAI Overviewsの直接の前身といえるでしょう。その役割は、複雑な質問に対してウェブ上の複数情報を統合・要約して提示し、ユーザーが個別のサイトを閲覧する手間を省いて素早く答えを得られるようにすること。まずは米国で導入が始まり、検索体験を大きく変える存在として注目されています。
AIモデル「Gemini」の特徴
Googleが2023年12月に発表した最先端AIモデル「Gemini」は、テキスト情報に加えて画像、音声、動画、さらにはプログラミングコードまでをネイティブに理解できる「マルチモーダル性能」が最大の特徴でしょう。これにより、図表を含む資料の要約や、動画の内容に関する質疑応答といった、従来モデルより高度で複雑なタスクの実行を可能にしました。
Geminiには3つのサイズがあり、最も高性能な「Ultra」、汎用的な「Pro」、そしてスマートフォン上で効率的に動作する「Nano」が存在します。実際に「Google Pixel 8 Pro」にはGemini Nanoが搭載され、一部機能がオフラインでも利用できるのです。
性能面では、MMLUというAIの能力を測る主要ベンチマークで、Gemini Ultraは人間の専門家を上回るスコアを史上初めて記録しました。この技術はGoogle検索の「AI Overviews」などにも活用されています。
AIOverviewsの新機能と特長
AI Overviewsは、検索結果の最上部にAIが生成した要約を表示することで、あなたが知りたい答えへ一直線にたどり着けるようにサポートしてくれる画期的な機能です。
これまでのように、複数のWebサイトを一つひとつ開いて情報を探す手間が大幅に削減されるでしょう。
なぜなら、多くの人がインターネット上に溢れる膨大な情報の中から、信頼できる答えを短時間で見つけ出すことに難しさを感じているからです。
どのサイトが最も正確な情報を提供しているのか判断に迷ったり、広告に邪魔されたりした経験を持つ方も少なくないはず。
AI Overviewsは、こうした検索時のストレスを解消するために開発されたものなのです。
具体的には、「東京から大阪までの最安の移動方法」と検索したとしましょう。
従来であれば新幹線、飛行機、高速バスなど各交通機関のサイトを個別に見比べる必要がありました。
しかしAI Overviewsなら、それぞれの料金や所要時間を比較した上で、最もコストパフォーマンスの高い選択肢をまとめた形で提示してくれます。
これにより、複雑な比較検討の手間なく、最適な答えを瞬時に得られるのです。
多様なモードでの概要生成
AI Overviewsの真価は、単に情報を要約する機能にとどまりません。ユーザーの検索意図や理解度に合わせて、概要の生成モードを柔軟に変更できる点にこそ、その革新性があるのです。
例えば、複雑なトピックに対しては、より平易な言葉で説明する「Simpler」モードが利用できます。一方で、手順や詳細な分析を求める場合には、情報を段階的に分解して提示する「Break it down」モードが非常に有効でしょう。「初めての確定申告」のような検索では、初心者向けの簡単な概要と、各手続きを細かく解説した内容を使い分けることが可能となります。
2024年5月に開催されたGoogle I/Oで発表されたこれらの調整機能は、ユーザーが追加の検索をする手間を省くためのものです。これにより、一度の検索でより深い理解へと到達できる、対話的な検索体験が実現します。
複雑クエリへの対応力
AI Overviewsは、単一の問いに答えるだけでなく、複数の条件が組み合わさった複雑なクエリにも対応する能力を持ちます。これは「多段階の推論」と呼ばれる高度な技術が可能にしており、様々なウェブサイトから関連情報を集め、統合して一つの回答を生成する仕組みになっています。
例えば、「東京23区内で、ベジタリアンメニューがあり、かつ予算3,000円以内でディナーが楽しめるレストラン」といった込み入った質問にも、的確な答えを提示してくれるでしょう。ユーザーは複数のサイトを見比べる手間を省けるため、情報収集の時間を大幅に短縮できるのが最大の利点。これまでなら複数のタブを開いて行っていた比較検討作業が不要となり、リサーチの効率は格段に向上します。
このように、AI Overviewsはユーザーの課題解決をより直接的に支援する存在へと進化しているのです。
プラン作成のサポート機能
AI Overviewsは、複雑な計画立案を強力にサポートする機能を有します。例えば「家族4人で楽しむ3泊4日の北海道夏休み旅行プラン」と検索すれば、AIが具体的な旅程を自動で生成するのです。この提案には、富良野のラベンダー畑や旭山動物園といった人気スポット、レンタカーでの移動時間、さらには現地の名物料理が味わえるレストラン候補まで含まれているでしょう。
生成されたプランは単なるたたき台に過ぎません。気に入った項目を残し、興味のない部分を削除したり、別の候補に入れ替えたりと、GoogleドキュメントやGmailへエクスポートして自分だけのオリジナルプランへと簡単に編集できます。旅行計画のみならず、「1週間の糖質制限ダイエット献立」といった日常生活の課題に対しても、具体的なレシピや買い物リストを提示してくれるため、情報収集から計画整理までの時間を劇的に短縮させる可能性を秘めています。
動画検索と音声対応
AI Overviewsの進化は、テキスト情報にとどまらず、動画コンテンツの検索体験にも革新をもたらします。例えば、「壊れたレコードプレーヤーの直し方」といった具体的な質問に対し、AIがYouTubeなどの動画プラットフォームから最も適切な箇所を分析・特定してくれるようになるでしょう。ユーザーは長い動画を最初から見なくても、問題解決に直結するシーンへ直接アクセスできるのです。
2024年5月に米国で先行導入されたこの機能は、複雑な問いへの回答精度を高めています。さらに、Googleアシスタントのような音声AIとの連携強化も見逃せません。AI Overviewsが生成した回答を音声でスムーズに受け取れるようになれば、運転中や料理中といったハンズフリーの状況でも、必要な情報を効率的に得られるようになります。
こうしたマルチモーダルな対応は、情報検索の可能性を大きく広げる力を持っているのです。
GoogleSearchConsoleとの連携
Google Search Consoleとの連携は、AI Overviewsにおける自サイトのパフォーマンスを把握する上で不可欠です。
Search Consoleの「検索パフォーマンス」レポートに新たなフィルタ機能が実装され、AI Overviewsに表示された際のクリック数や表示回数を具体的に分析できるようになりました。これにより、通常のオーガニック検索とは別に、AI生成アンサー経由での流入を正確に計測することが可能となるのです。
このデータを活用することで、どのようなコンテンツがAIに引用されやすいのか、またユーザーの検索意図にどの程度応えられているのかを客観的に評価できるでしょう。例えば、表示回数は多いもののクリック率が低いページを特定し、コンテンツの改善に繋げる、といった具体的な施策立案に役立ちます。AI Overviewsの動向をデータで追い、戦略的に対応していくことが今後のSEOにおいて重要になると考えられます。
AIOverviewsの利用方法
AI Overviewsを利用するために、あなたが特別な設定や操作をする必要は一切ありません。
いつも通りGoogleで検索するだけで、AIが生成した回答が検索結果の最上部に自動で表示される仕組みになっています。
これまでと変わらない検索体験のまま、より素早く的確な情報を得られる点が大きな魅力でしょう。
なぜなら、AI OverviewsはGoogleの検索体験そのものを向上させるために導入された機能だからです。
ユーザーが何かを意識しなくても、複雑な質問や複数の意図を含む検索に対して、AIが最適な答えを要約して提示してくれます。
これにより、複数のウェブサイトを一つひとつ確認する手間が大幅に省けるのです。
具体的には、「東京で子連れにおすすめのランチスポットで、個室があって予算3,000円以内」といった条件で検索したとします。
するとAI Overviewsは、これらの条件を満たすレストランのリストや特徴を簡潔にまとめて提示してくれるでしょう。
さらに、その情報の参照元となったウェブサイトへのリンクも表示されるため、詳細を確認することも簡単です。
パソコンでの設定ガイド
パソコンでAI Overviewsの表示を任意に設定する公式な方法は、2024年時点の日本ではまだ提供されていません。
過去にはGoogleの試験機能「Search Labs」を通じて、AI Overviewsの前身にあたるSGE(Search Generative Experience)を有効化できましたが、この試験プログラムは2024年初頭をもって終了いたしました。
現在のAI Overviewsは、特定の検索クエリに対しGoogleの判断で自動的に表示される仕組みです。そのため、ユーザー側で設定画面から恒久的に表示をオフにすることはできません。ただし、AIによる要約が表示された際に、検索ツール内の「ウェブ」フィルタを選択すると、一時的に従来の検索結果のみの画面へ切り替えられます。
将来的にユーザーごとのカスタマイズ機能が導入される可能性もあるため、Googleアカウントの検索設定内にある「Labs」タブなどを定期的に確認してみるのがよいでしょう。
スマホでの設定ガイド
スマートフォンでAI Overviewsを設定する場合、現時点ではGoogleの試験運用プログラム「Search Labs」を利用する必要があります。
iPhoneやAndroidのGoogleアプリを開き、画面上部にあるフラスコ型のLabsアイコン、またはプロフィールアイコン内のメニューから「Labs」を探してみましょう。
次に、「SGE(生成AIによる検索体験)」などの項目を見つけ、トグルスイッチをオンに切り替えることでAIによる要約機能が有効になります。逆に機能を停止させたい際は、同じ手順でスイッチをオフにするだけで簡単に設定が完了します。
ただし、この機能は日本国内ではまだ一部ユーザーへの限定提供に留まるため、お使いの環境によっては設定項目自体が表示されないかもしれません。利用にはGoogleアカウントでのログインが必須であり、今後の本格的な展開が待たれる状況です。
SEOにおけるAIOverviewsの影響
AI Overviewsの登場により、従来のSEO戦略は大きな転換期を迎えるでしょう。
これまで検索順位で1位を獲得しても、AIの回答がその上に表示されるため、ウェブサイトへのトラフィックが減少する可能性があります。
一方で、AI Overviewsの参照元として自社サイトが引用されれば、新たな流入経路が生まれるチャンスでもあるのです。
その理由は、ユーザーが検索行動をAI Overviews内で完結させてしまうケースが増えると考えられるからです。
特に「〇〇とは?」のような、すぐに答えがわかる情報検索クエリでは、ユーザーはAIが生成した要約だけで満足してしまうかもしれません。
結果として、これまで多くのアクセスを集めていたページへのクリック数が、大幅に落ち込む事態も想定されます。
具体的には、「iPhone 修理方法」と検索したユーザーを考えてみましょう。
AI Overviewsが手順を分かりやすくリスト表示した場合、詳細な解説記事を読まずに自己解決できてしまいます。
これにより、修理方法を解説していたブログや修理業者のサイトは、潜在顧客を逃す可能性があります。
しかし、そのAIの回答に「〇〇ブログの記事を参考にしました」と引用されれば、逆に権威性を示し、ブランド認知を高める絶好の機会となるのです。
自然検索のクリック率への影響
AI Overviewsが検索結果の最上部に表示されるため、その下にある自然検索のクリック率(CTR)は大きな影響を受けると予測されます。
検索ユーザーがAIの生成した回答だけで疑問を解決し、個別のウェブサイトを訪問しない「ゼロクリック検索」が増加する可能性が高いでしょう。特に、言葉の定義や簡単な事実確認など、単一の答えが存在するクエリでこの傾向は顕著になると考えられています。海外の先行調査では、AIによる回答が表示された場合、オーガニック検索のCTRが20%以上も低下したというデータも存在します。
一方で、AI Overviewsの回答内で自社サイトが参照元として引用されれば、これまでになかった新しいトラフィック流入経路となるのです。これにより、質の高いユーザーを獲得する絶好の機会が生まれることも期待できます。
AIOverviewsに参照されるためのSEO戦略
GoogleのAI Overviewsで参照されるには、AIが情報を理解し、信頼できると判断するコンテンツ作りが不可欠となります。
まず、Googleが重視するE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)は、AIによる評価においても極めて重要になるでしょう。著者情報を明記し、独自の調査データや専門家の監修といった一次情報を提供することが求められます。
次に、構造化データの実装はAIの理解を助ける有効な手段です。特にFAQPageスキーマやHowToスキーマを活用し、質問と回答の形式をAIに明確に伝えることで、引用の可能性が高まるはず。
さらに、ユーザーの検索意図に対して、簡潔かつ直接的な答えをコンテンツの冒頭付近で提示する構成も、AIが要約を生成する上で参照しやすくなる要因と考えられます。
従来のSEOに加え、AIに「選ばれる」ための高品質で分かりやすい情報発信が、今後のWebサイト運営において一層重要な鍵を握ります。
AIOverviewsは日本でいつから利用可能?
2024年5月現在、AI Overviewsの日本での正式な導入時期はまだ発表されていません。
米国で先行して提供が開始されたばかりであり、日本で利用できるようになるまでには、もう少し時間が必要となる見込みです。
いち早く最新機能を試したい方にとっては、待ち遠しい状況でしょう。
Googleが新機能を導入する際は、まず英語圏でテストと改善を重ね、その後に他の言語や国へ展開する傾向があるためです。
日本語特有の表現や文化的な背景をAIが正しく理解し、質の高い回答を生成するには慎重な調整が求められます。
そのため、日本での導入には一定の準備期間が必要だと考えられるのです。
具体的には、AI Overviewsの前身であるSGE(Search Generative Experience)も、米国での発表から日本でのテスト開始まで約3ヶ月の期間がありました。
この前例を踏まえると、AI Overviewsも同様のスケジュール感で展開される可能性があります。
今後のGoogleからの公式アナウンスに注目が集まります。
AIOverviewsに関するよくある質問
AI Overviewsは非常に便利な機能ですが、まだ新しい技術であるため、使い方や仕組みについて多くの疑問が生まれるのは自然なことでしょう。
このセクションでは、AI Overviewsに関してよく寄せられる質問とその回答をQ&A形式で分かりやすくまとめました。
これまでの検索体験とは大きく異なるため、Webサイトの運営者にとってはトラフィックへの影響が気になったり、一般ユーザーにとっては情報の正確性に不安を感じたりするからです。
新しい技術に対する期待と不安が入り混じり、どのように向き合えば良いのか戸惑う方も少なくないでしょう。
具体的には、「AI Overviewsの回答を非表示にしたい」「生成される情報の信頼性は担保されているのか」「自分のサイトが表示されるにはどうすればいいの?」といった声が多く聞かれます。
これらの誰もが抱くような疑問に対して、一つひとつ丁寧にお答えし、あなたの不安や悩みを解消していきます。
AIOverviewsの導入時期はいつ?
AI Overviewsは、2024年5月14日に開催された開発者会議「Google I/O」で正式に発表され、まずはアメリカ国内での提供が始まりました。
Googleはこの機能を2024年末までに10億人以上のユーザーへ届ける目標を掲げています。
一方、日本国内での正式な導入時期は現時点で明確にされていません。しかし、その前身であるSGE(Search Generative Experience)は、試験運用プログラム「Search Labs」を通じて2023年8月30日から日本でも利用可能となっていました。このことからも、日本での本格展開に向けた準備は着々と進んでいると考えられます。
Googleは順次提供国を拡大する方針のため、日本でAI Overviewsが利用できるようになるのも、そう遠い未来ではないでしょう。
具体的なスケジュール発表が待たれる状況であり、検索体験の大きな変革が間近に迫っています。
AIOverviewsのクエリ表示の特徴
AI Overviewsは、ユーザーが複数の情報を組み合わせないと答えが見つからないような、複雑な検索クエリに応答する形で表示される傾向があります。
例えば、「幼児向けの栄養満点な1週間の献立」や「東京から日帰りで楽しめる初心者向けハイキングコース」といった、調査や計画が必要な質問に対して、関連情報を要約して提示してくれるでしょう。
また、「iPhone 15とPixel 8のカメラ性能を比較して」のような、複数の製品やサービスの長所と短所をまとめる必要があるクエリも、AI Overviewsが得意とする領域です。
これは、Googleが2024年5月に米国でサービスを開始した際の挙動からも見て取れる特徴でした。
一方で、「日本の首都」といった単純な事実確認や、特定のサイト名での検索では、従来型の検索結果が優先されることが多いようです。
AIOverviewsが参照するコンテンツの条件
AI Overviewsが参照するコンテンツには、いくつかの明確な条件が見られます。
Googleが提唱する品質評価の指針「E-E-A-T」、すなわち経験・専門性・権威性・信頼性を満たす情報源が優先される傾向にあるでしょう。
例えば、総務省や経済産業省といった公的機関、あるいは専門家が監修したウェブサイトは、信頼性の高さから選ばれやすいと考えられます。加えて、AIが内容を正確に解釈できるよう、問いに対して直接的な答えを提示するQ&A形式のページや、要点が整理された構成が重要になります。
構造化データを用いてコンテンツの意図を検索エンジンに伝えることも有効な手段の一つでしょう。
単なる情報の羅列ではなく、2024年のヘルプフルコンテンツアップデートでも示されたように、独自の一次情報や深い洞察を含む、ユーザーにとって真に価値あるコンテンツ作りが求められます。
まとめ:AI Overviewsを理解して未来の検索に対応しよう
– AI Overviewsの基本的な仕組み
– これまでのSGEとの違い
– AIの回答に自分のサイトを表示させる裏ワザ
上記について、解説してきました。
AI Overviewsは、Google検索のあり方を根本から変える可能性を秘めた、非常に大きな変化点です。
検索結果の最も目立つ場所に表示されるため、今後のサイト運営に与える影響は計り知れないでしょう。
この新しい技術の登場に、少し戸惑いを感じている方もいるかもしれません。
しかし、変化の全貌が見えない今だからこそ、まずはその特性を正しく知ることが何よりも重要になります。仕組みを理解することで、漠然とした不安は具体的な対策へと変わっていくはずです。
あなたがこれまで真摯に取り組んできたコンテンツ作りやサイト改善の努力は、決して無駄にはなりません。
むしろ、ユーザーを第一に考えるという基本姿勢は、これからのAI時代においてさらに価値を増すことでしょう。AI Overviewsは脅威であると同時に、質の高い情報を提供するサイトにとっては大きな好機にもなり得ます。
正しく対策を行えば、これまで以上に多くのユーザーに情報を届けられる可能性を秘めているのです。
この記事で触れたポイントを参考に、まずはご自身のサイトで何ができるかを考えてみましょう。
未来の検索で勝ち抜くための第一歩を、筆者も心から応援しています。
SEO対策とは?はこちら
SEOの外注(SEO代行)をご検討の方はこちら
SEOコンサルサービスをご検討の方はこちら
SEO対策費用についてはこちら
SEO会社をご検討の方はこちら