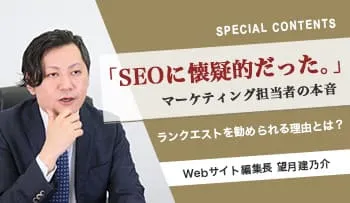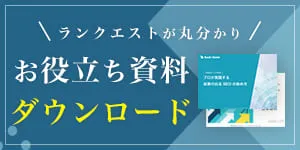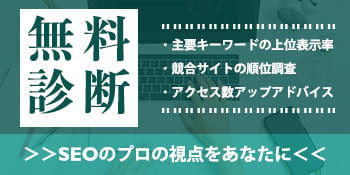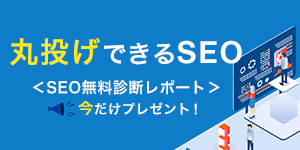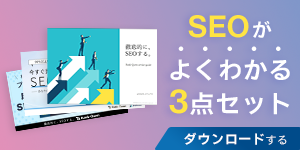AIライティングツールが注目を集め、記事作成や業務の効率化に活用したいと考える方も増えてきました。
しかし、「たくさんありすぎて、結局どれを選べば良いかわからない…」と感じているのではないでしょうか。
「AIが書いた文章って、本当にSEOで通用するのかな…」といった心配もあるかもしれません。
自分に合わないツールを選んでしまうと、時間も費用も無駄になりかねないです。
だからこそ、それぞれのツールの特徴や得意なことをしっかり見極めることが大切でしょう。
まずは、どのような選択肢があるのかを知ることから始めましょう。
この記事では、業務の効率化や質の高い記事作成を目指している方に向けて、
– 厳選したおすすめAIライティングツール
– SEO記事を作る際の重要な注意点
– 目的や予算に合わせたツールの選び方と比較結果
上記について、詳しく解説しています。
この記事を読めば、各ツールの強みと弱みが明確になり、あなたの目的を達成するための最適な相棒が見つかるはずです。
初めてAIツールを導入する方でも安心して選べるよう、丁寧に説明しました。
ぜひ参考にして、あなたにぴったりのツールを見つけてください。
目次

今すぐ無料で、
あなたのSEO対策費用を
シミュレーション!
簡単な質問に答えるだけで、
最適なSEOプランと費用が無料でわかります。

SEO対策を
行ったことはありますか?

AIライティングツールとは?その魅力と注意点
AIライティングツールとは、AI(人工知能)が文章を自動で作成してくれる便利なツールです。
記事作成やメール文など、文章作成にかかる時間を大幅に短縮したいと考えているあなたにとって、強力な味方になるでしょう。
キーワードや簡単な指示を与えるだけで、自然で質の高い文章を生成してくれる画期的な存在なのです。
このツールが注目される最大の理由は、圧倒的な作業効率の向上にあります。
ブログ記事を1本書くのに何時間もかかったり、良いアイデアが浮かばず手が止まってしまったりする経験を持つ方もいるかもしれません。
AIライティングツールは、そんな悩みを解決するために構成案の作成から本文執筆、リライトまで、文章作成のあらゆる工程をサポートしてくれます。
ただし、非常に便利な一方で、ツールの選び方や使い方にはいくつかの注意点も存在します。
その効果を最大限に引き出すためには、ツールの魅力と注意点の両方を深く理解することが重要でしょう。
以下で、AIライティングツールの具体的な魅力と、利用する上での注意点について詳しく解説していきます。
AIライティングの品質とその評価
近年のAIライティングツールは、GPT-4といった高性能な言語モデルの登場により、その品質が劇的に向上しました。かつて見られた機械的な翻訳文のような不自然さは影を潜め、実用レベルに十分達していると言えるでしょう。
ただし、生成される文章の質は、利用するツールやユーザーが与える指示の具体性によって大きく変わるのが実情です。
例えば、国内で人気の「Catchy」やSEOに特化した「Transcope」など、各ツールで得意分野が異なります。
そのため、まずは無料プランやトライアル期間を活用し、複数のツールを試してみることをおすすめします。評価する際は、「文章の自然さ」はもちろん、「情報の正確性」や「独自性」を厳しくチェックすることが肝心です。
AIは便利な反面、誤った情報を生成するケースも少なくないため、最終的なファクトチェックは人間の重要な役割となります。
AIライティングを利用する際の注意事項
AIライティングツールは非常に便利ですが、活用する上でいくつかの注意点を理解しておく必要があります。
まず、AIが生成する情報の正確性には常に注意を払うべきです。
学習データが最新でない場合や、事実と異なる内容を出力する可能性がゼロではないため、公開前には必ず人間の目でファクトチェックを行うことが不可欠でしょう。
次に、著作権の問題も無視できません。AIが意図せず他のウェブサイトのコンテンツと酷似した文章を生成してしまうリスクがあるからです。「CopyContentDetector」などのツールを用いて、オリジナリティを担保する作業を推奨します。
また、企業の機密情報や個人情報をプロンプトに入力するのは絶対に避けてください。
AIはあくまで強力なアシスタントと捉え、最終的な品質管理は人間が責任を持つという姿勢が重要となります。
AIライティングツールの選び方と用途別おすすめ
数多くのAIライティングツールの中から最適なものを見つけるには、まずあなたの「利用目的」を明確にすることが何よりも大切です。
SEO記事の作成、キャッチコピーの考案、メールマガジンの作成など、用途によって最適なツールは全く異なります。
「どれも同じように見えて選べない」と感じるかもしれませんが、それぞれのツールが持つ特性を理解することが後悔しないための第一歩でしょう。
なぜなら、各ツールで得意な文章の種類や搭載されている機能、そして料金プランに大きな違いがあるからです。
例えば、キーワードに基づいたSEOコンテンツ生成に特化したツールもあれば、より創造的なアイデア出しをサポートしてくれるツールも存在します。
もし自分の使い方に合わないツールを選んでしまうと、「費用対効果が悪かった」「かえって作業に時間がかかってしまった」といった残念な結果になりかねません。
あなたの目的を達成するためには、どのような基準でツールを比較検討すれば良いのでしょうか。
具体的には、「文章生成の専門性」「操作のしやすさ」「料金体系」といったポイントが重要になります。
以下で、それぞれの用途に合わせた選び方のポイントを詳しく解説していきましょう。
社内業務を効率化するための選び方
社内業務の効率化を目的としてAIライティングツールを選ぶなら、幾つか重要な視点を持つことが大切です。
まず、SlackやGoogle Workspaceといった既存ツールとのAPI連携が可能かを確認してみましょう。APIで連携できると、報告書作成や議事録要約といった定型業務の自動化が期待できます。次に、極めて重要なのがセキュリティ面ではないでしょうか。
社内文書を扱う以上、入力データをAIの学習に利用しない設定や、ISMS(ISO 27001)のような第三者認証の有無は必ず確認すべき項目でしょう。
また、チームで利用する際は、共同編集機能や作成したプロンプトの共有機能が業務効率を大きく左右します。これらの点を総合的に比較検討することが、自社に最適なツール選びの鍵となるのです。
マーケティング業務に最適なツールの選び方
マーケティング業務でAIライティングツールを導入する際、まず利用目的を明確にすることが成功の鍵となります。
例えば、ブログ記事で検索上位を目指すのであれば、SEOに特化した機能、具体的にはキーワード提案や競合分析ができるツールが不可欠でしょう。
次に、広告コピーやSNS投稿といった多様な用途に対応できるか、テンプレートの豊富さも確認してください。
特に、生成される日本語の自然さや、企業のブランドイメージに合わせたトーン調整機能は、ユーザーに響くコンテンツ作成において極めて重要な要素となります。「Catchy」は100種類以上の生成ツールを提供しており、選択肢の一つになるかもしれません。
最後に、料金体系の確認も忘れてはいけません。
月額固定制か、あるいは使用量に応じた従量課金制か、自社の利用頻度と予算に合ったプランを選びましょう。多くのツールが無料トライアル期間を設けているため、実際に試して自社との相性を見極めるのが賢明な方法です。
SEO対策に特化したツールの選び方
SEO効果を最大化するAIライティングツール選びでは、いくつかの重要なポイントがあります。
まず確認したいのは、キーワード分析や共起語の提案機能です。
例えば「SAKUBUN」のようなツールは、対策キーワードから関連語句を自動で抽出してくれるため、検索意図を網羅した質の高い記事作成に貢献するでしょう。
次に、SEOに最適化されたテンプレートが豊富かどうかも重要な選定基準となります。国産ツール「Catchy」には、記事タイトルやメタディスクリプション、見出し構成を生成する100種類以上のテンプレートが用意されており、作業効率を飛躍的に高めてくれます。
加えて、生成文章の独自性を保証するコピーコンテンツチェック機能の有無も必ず確認すべき点。これらの機能を比較検討することが、上位表示を狙うための最適なツール選びにつながります。
推敲や校正を効率化するための選び方
文章の推敲や校正を効率化するAIツール選びでは、チェック機能の深さが重要になります。
単なる誤字脱字の発見能力だけでなく、日本語特有の「ら抜き言葉」や冗長な表現を指摘し、より洗練された言い回しを提案してくれるか確認しましょう。
例えば、国内ツール「文賢」は100項目以上の視点で文章を多角的に分析してくれるため、品質向上に大きく貢献します。
また、作業フローを中断させない連携機能も選定の鍵です。GoogleドキュメントやWordのアドオンとして直接利用できるツールであれば、執筆から校正までをシームレスに行えます。
業界の専門用語などを登録できるカスタム辞書機能の有無も、ストレスなく使い続けるための重要な判断材料となるでしょう。
無料トライアルでこれらの機能の精度を体感し、自分の執筆スタイルに合うか見極めることが、最適なツール選びの近道です。
AIライティングツールの比較ポイント
あなたに最適なAIライティングツールを選ぶには、料金プランだけでなく、利用目的と生成される文章の質、そして搭載されている機能を総合的に比較することが非常に重要です。
なぜなら、価格だけで選んでしまうと「日本語が不自然で修正に時間がかかる」「求めていた機能がなかった」といった失敗につながりかねないからです。
あなたの作業効率やコストパフォーマンスに直結するため、利用目的を明確にして必要な機能を見極めることが、ツール選びで後悔しないための鍵となります。
具体的には、SEO記事の作成が目的なら、キーワード分析や構成案作成機能が搭載されたツールが便利でしょう。
一方で、SNS投稿やキャッチコピーのアイデア出しがメインであれば、多様なテンプレートを持つ『Catchy』のようなツールが適しているかもしれません。
無料プランやトライアル期間を活用し、操作感や文章の質を実際に試してから本格導入を決めるのが賢い選択です。
生成可能な文字数のチェック
AIライティングツールを選ぶ際、生成可能な文字数の確認は欠かせないポイントです。
ツールや料金プランによって、1ヶ月に使える文字数の上限や、一度に出力できる文字数に大きな違いがあるため、用途に合わないと不便を感じるかもしれません。
例えば、人気の「Catchy」はクレジット制を採っており、無料プランでは月10クレジットが付与されます。
一方、「SAKUBUN」は無料プランで月5,000文字まで試せるので、比較検討しやすいでしょう。3,000文字以上の長文ブログ記事を頻繁に作成するなら、文字数無制限の有料プランが視野に入ってきます。
逆に、X(旧Twitter)の140文字程度の投稿がメインであれば、無料プランでも十分活用できると考えられます。
ご自身の用途を明確にし、必要な文字量を満たすツールやプランを選択することが、後悔しないための重要な鍵となります。
効率的な事前学習への対応
AIライティングツールを最大限に活用する上で、効率的な事前学習は欠かせません。
優れた文章を生成させるには、ツールに適切な情報を与える必要があります。
例えば、最新のAIツールである「Claude 3 Opus」や「Gemini 1.5 Pro」は、非常に長い文章(コンテキスト)を一度に読み込めるのが特徴でしょう。
これにより、複数の参考記事URLや、数万文字に及ぶPDF資料を丸ごと読み込ませて、内容を深く理解させた上での執筆が可能となります。
おすすめの活用法として、競合上位3サイトの情報を読み込ませ、それらを網羅した独自のコンテンツ案を作成させる方法があります。
この一手間を加えるだけで、生成される文章の質は飛躍的に向上し、リサーチにかかる時間を70%以上削減することも夢ではありません。
自社の専門知識を反映させた高品質なコンテンツ作成が、驚くほど簡単になるのです。
共同編集機能の有無
AIライティングツールをチームで活用する場合、共同編集機能の有無は選定における重要な判断基準となります。
この機能があれば、複数人で同時に1つのドキュメントを編集でき、コンテンツ制作の効率が飛躍的に向上するでしょう。
例えば、マーケティングチームが広告文を作成する際、リアルタイムでフィードバックを反映させながらブラッシュアップを進められます。
海外製の「Jasper」や「Copy.ai」では、ビジネスプランやチームプランに加入することで、複数のユーザーがワークスペースを共有し、生成したコンテンツを管理することが可能です。
一方、国内で人気の「Catchy」は、2024年現在、主に個人利用を想定しており、共同編集機能は実装されていません。
個人の作業効率化を求めるのか、チーム全体の生産性向上を目指すのか、自社の目的に合わせて最適なツールを選ぶことが肝心です。
おすすめAIライティングツール16選
数あるAIライティングツールの中から、あなたに最適な一つを見つけ出すのは大変ですよね。
この記事では、SEO記事作成で本当に役立つおすすめのツールを、無料プランがあるものから高機能なものまで16個に厳選しました。
それぞれのツールの特徴を比較することで、あなたの目的や予算にぴったりのパートナーがきっと見つかるでしょう。
今回ご紹介する16のツールは、単に人気があるという理由だけで選んだわけではありません。
日本語文章の自然さや精度はもちろん、SEO対策機能の有無、操作画面の使いやすさ、そして継続して利用できる料金体系かといった複数の観点から総合的に評価しました。
そのため、どのツールもコンテンツ作成の強力な助けとなる、自信を持っておすすめできるものばかりです。
それでは、各ツールの強みや料金プラン、どのような方に向いているのかを詳しく見ていきましょう。
以下で、厳選した16のAIライティングツールを一つずつ丁寧に解説していきます。
サイボーグライティング
サイボーグライティングとは、AIと人間がそれぞれの長所を活かし、協働でコンテンツを生み出す執筆手法を指します。
AIに記事の構成案やたたき台を作成させ、人間はそれを基にリライトやファクトチェック、そして独自の視点を加える役割を担うのです。
例えば、AIライティングツールの「Catchy」でキャッチーな見出し案を複数抽出し、本文の下書きは「ChatGPT」に任せる、といった分業が可能となります。
これにより、執筆時間を最大で半分以下に短縮できるケースも珍しくありません。
AIが生成した文章には誤情報や不自然な表現が含まれることもあるため、最終的にブランドイメージを損なわないよう、人間による丁寧な推敲と感情を込めた加筆が不可欠といえるでしょう。
BLOGAI(ブロガイ)
BLOGAIは、ブロガーやアフィリエイターの収益化支援に特化して開発された国産AIライティングツールです。このツールの強みは、何と言ってもSEOに関する機能の豊富さにあります。キーワードを一つ入力するだけで、競合サイトの分析に基づいた最適な記事構成案をわずか数分で提案してくれます。生成される文章は、最新のGPT-4モデルを基盤としており、人間が書いたような自然で高品質な表現力が魅力といえるでしょう。月額料金は980円から利用できるプランがあり、コストを抑えたい個人ブロガーにも最適。さらに、WordPressとのAPI連携機能を使えば、生成した記事を下書きとしてワンクリックで投稿することも可能です。記事作成から公開までの作業を劇的に効率化してくれる、まさに次世代のライティングアシスタントなのです。
Catchy(キャッチー)
株式会社デジタルレシピが開発した「Catchy」は、特に日本語の自然な文章生成に定評があるAIライティングツール。
その最大の特徴は、キャッチコピーや記事タイトル、広告文、資料作成など100種類以上もの豊富な生成ツールを備えている点でしょう。
サービス名が示すように、読者の心を惹きつける魅力的なフレーズ作りを得意としており、マーケティングやブログ運営で即戦力となります。毎月10クレジットが付与される無料プランが用意されているため、まずは気軽に試せる手軽さも人気の理由。
さらに本格的な活用を考えるなら、月額9,800円から利用できるProプランなどもあり、ビジネスシーンの多様なニーズに応えてくれます。
直感的なインターフェースで、AIツールが初めての方でも安心して利用を開始できるでしょう。
EmmaTools(エマツールズ)
EmmaTools(エマツールズ)は、SEOに特化したコンテンツマーケティング支援ツールです。
単なるAIライティング機能だけでなく、競合サイトや自社サイトを分析する「3C分析」、キーワード調査、AIによる記事骨子や本文の生成、さらには公開前のSEOスコアチェックやコピーコンテンツチェックまで、コンテンツ制作の全工程を一つのツールで完結させる能力を持ちます。
この包括的な機能により、SEOで上位表示を狙う記事を効率的に、かつ高い品質で制作したいWeb担当者やメディア運営者に最適な選択肢となるでしょう。料金は月額33,000円(税込)のライトプランから利用可能。
SEOの専門知識に自信がなくても、データに基づいた的確なコンテンツ戦略を実行できる点が大きな魅力となっています。
SAKUBUN(サクブン)
株式会社Gakkenが開発した「SAKUBUN」は、特にSEOコンテンツ制作で強みを発揮するAIライティングツールです。
最大の特徴として、指定したキーワードで検索順位1位の記事をAIが分析し、その構成や内容を参考にした文章を生成する機能が挙げられます。
これにより、上位表示を狙った質の高い記事作成が効率的に行えるでしょう。ブログ記事やメルマガ、広告文など100種類以上のテンプレートが用意されているため、様々なライティング業務に対応可能です。
最新のAIモデルであるGPT-4oを搭載し、自然で精度の高い文章を生み出せるのも魅力の一つ。
また、ペルソナを細かく設定する機能を使えば、ターゲット読者の心に響く、より訴求力の高いコンテンツ制作が実現します。
個人ブロガーから企業のマーケティング部門まで、SEOでの成果を求める全ての人におすすめできるツールといえるでしょう。
ChatGPT(チャットジーピーティー)
米国企業OpenAIが開発したChatGPTは、AIライティングツールの代表格として世界中で利用されています。
自然な対話形式で指示するだけで、ブログ記事やSNS投稿、メール文面の作成から、企画のアイデア出し、難解な文章の要約、多言語への翻訳まで、非常に幅広いタスクをこなすことが可能。
その汎用性の高さは他のツールと比較しても際立っているでしょう。
無料でもGPT-3.5モデルを利用できますが、月額20ドルの有料プラン「ChatGPT Plus」にアップグレードすれば、より高精度なGPT-4や、2024年5月に登場した最新のGPT-4oといった高性能モデルが使える点も大きな魅力です。
まずは無料版で基本性能を試し、自身の目的に合うかを見極めるのが賢明な使い方と言えます。
AIWriter(エーアイライター)
AIWriterは、株式会社デジタルレシピが提供する国産のAIライティングツールで、特にSEOを意識した記事作成に強みを持っています。
最新のAIモデルであるGPT-4を搭載しており、質の高い文章生成が可能なのが大きな特徴でしょう。使い方は非常にシンプルで、キーワードを入力するだけでSEOに最適なタイトル案や構成案、さらには本文までを一括で生成してくれます。ブログ記事に限らず、SNS投稿や広告文、プレスリリースなど、100種類以上の豊富なテンプレートが用意されている点も魅力的なポイント。
無料のFreeプランでも毎月5,000文字まで利用できるため、初めてAIツールを試す方でも気軽に導入が可能です。
画面の指示に従うだけで直感的に操作できることから、個人ブロガーから企業のコンテンツ担当者まで、幅広い層の執筆業務を効率化するツールといえます。
PerplexityAI(パープレキシティエーアイ)
Perplexity AIは、従来の対話型AIとは一線を画す「AI検索エンジン」として機能するツールです。
特筆すべきは、生成された回答すべてに参照元のURL、つまり情報源を明記する点でしょう。
これにより、ユーザーは情報の信頼性を自身で容易に確認できます。
このツールは質問が入力されると、リアルタイムでウェブを検索し、最新の情報に基づいて要約された回答を生成するため、2024年時点のトレンドやニュースに関する問いにも的確に答えられます。
無料版でも十分に活用できますが、月額20ドルからのProプランではGPT-4やClaude 3といった、さらに高性能なAIモデルを利用することも可能です。
情報の正確性が不可欠なリサーチ業務や、専門的なレポート作成において、非常に強力な味方となってくれるでしょう。
ELYZAPencil(イライザペンシル)
ELYZAPencil(イライザペンシル)は、東京大学松尾研究室から生まれたAI企業elyzaが開発した、信頼性の高い国産AIライティングツールです。
日本のビジネスシーンに特化しており、2024年5月時点でメール作成や記事制作、プレスリリースなど89種類もの豊富なテンプレート(スキル)が用意されているのが大きな特徴。
国産ならではの自然で丁寧な日本語表現は、海外製ツールにはない強みといえるでしょう。
料金プランは非常にシンプルで、月間3,000文字まで無料で使えるFreeプランと、月額3,000円(税込)で文字数無制限になるProプランの2種類があります。
まずはクレジットカード登録不要のFreeプランで気軽に試せる手軽さが魅力です。
また、入力したデータはAIの学習に利用されないと明記されているため、セキュリティを重視する法人でも安心して活用することが可能となっています。
ブンゴウ
ブンゴウは、SEO記事の作成に特化した国産AIライティングツールです。
最大の魅力は、対策キーワードを入力するだけで、AIが競合上位10サイトを自動分析し、最適な記事構成案をわずか数分で提案してくれる機能にあるでしょう。
この構成案を基に、最新AIモデルのGPT-4oを用いて、自然で高品質な本文を一括で生成できます。
記事作成にかかる時間を最大90%以上削減できるというデータもあり、コンテンツ制作の効率を飛躍的に高めてくれるツールといえるかもしれません。
月額9,800円から利用可能なプランが用意されており、企業のオウンドメディア担当者やアフィリエイターにとって、非常に心強い味方となるはずです。
7日間の無料トライアルも提供されているため、まずはその優れた機能を実際に体験してみることをおすすめします。
AIのべりすと
「AIのべりすと」は、小説やTRPGのシナリオ制作など、物語の創作に特化したユニークな国産AIライティングツールです。
ユーザーが入力した文章に続く展開をAIが自動で生成するため、物語のアイデア出しや執筆の補助として大きな力を発揮してくれるでしょう。
特に、キャラクター設定や世界観を詳細に登録できる機能が秀逸で、これにより物語全体で一貫性を保ちながら執筆を進めることが可能。無料でも十分に試せますが、月額1,320円からの有料プランでは、さらに高性能なAIモデル「とりんさまAI」が利用できる点も魅力となります。
一般的なビジネス文書作成ツールとは異なり、クリエイティブな執筆活動を強力に支援する点で、多くの創作者から支持を集めています。
BuzzTai(バズタイ)
株式会社BuzzTaiが開発した「BuzzTai」は、SEOで成果を出すことに特化した国産AIライティングツールです。
最大の特徴は、指定したキーワードで検索上位に表示される最大20サイトをAIが瞬時に分析し、評価の高い構成案を自動で作成する機能にあります。この競合分析に基づいた構成案は、記事の品質を高め、検索上位を狙うための強力な武器になるでしょう。
さらに、構成案から本文までワンクリックで生成することも可能で、執筆作業の大幅な効率化を実現します。月額9,800円から利用でき、SEOに不可欠なサジェストキーワードや再検索キーワードの分析機能も搭載。
本気でSEO対策に取り組むブロガーや企業のコンテンツ担当者にとって、非常に心強いツールとなるはずです。
Rytr(ライトル)
優れたコストパフォーマンスで注目を集めるAIライティングツールがRytr(ライトル)でしょう。
このツールはブログ記事や広告コピー、SNS投稿文など、30種類を超える豊富なユースケースに対応し、日本語を含む40以上の言語でコンテンツを生成する能力を持ちます。
独自のAIとGPT-3を組み合わせた技術が用いられており、20種類以上のトーン(口調)を選択して文章の雰囲気を変えられる点もユニークな特徴です。
料金プランは特に魅力的で、毎月10,000文字まで利用できる無料プランが用意されています。さらに月額$9から始められる有料プランや、月額$29で文字数無制限となるUnlimitedプランは、頻繁に利用するユーザーにとって非常に経済的。
ブラウザ拡張機能を使えば、様々な場面で手軽に利用できるため、AIライティング入門者や個人ブロガーに最適なツールの一つといえます。
JasperAI(ジャスパーエーアイ)
旧Jarvisとしても知られるJasperAIは、世界で最も有名なAIライティングツールの一つでしょう。
特にマーケティングやセールスライティングでその真価を発揮し、ブログ記事からSNS投稿、広告コピーまで50種類を超える豊富なテンプレートを持ちます。
長文コンテンツの作成を強力に支援する「Boss Mode」や、SEO分析ツール「Surfer SEO」との連携機能は、競合と差をつける上で大きな武器となるはずです。
文章だけでなく、画像生成AI「Jasper Art」も利用可能。30以上の言語に対応しており、生成される日本語の質も非常に高い評価を得ています。
UIは英語が基本となりますが、月額49ドルのCreatorプランから始められ、SEOを意識した本格的なコンテンツ制作を目指す方に最適な選択肢です。
Autoblogging.ai(オートブロギングエーアイ)
Autoblogging.aiは、SEOを意識した長文記事やアフィリエイト記事の作成に特化したAIライティングツールになります。
最大の特徴は、Amazonの商品URLを貼り付けるだけで、本格的なレビュー記事を自動生成できる機能でしょう。
この機能により、アフィリエイターは商品紹介コンテンツの作成時間を大幅に短縮できるのです。記事生成には複数のモードがあり、キーワード入力のみで記事を作る「Quick Mode」のほか、見出し構成などを細かく指定できる「Pro Mode」も利用できます。
料金は月額49ドルの「Standard」プランから存在し、日本語コンテンツの出力にも対応しています。
海外製のツールですが、複数の記事を一度に作成するバルク生成機能も備わっており、効率的に記事を量産したいブロガーやメディア運営者にとって強力な味方となるはずです。
NoteAIアシスタント
人気プラットフォーム「note」に標準搭載された「NoteAIアシスタント」は、クリエイターの執筆活動を強力にサポートしてくれる機能。
記事の構成案作成や文章の続きの執筆はもちろんのこと、誤字脱字の校正、読者の興味を引くタイトルの提案まで、AIが多彩なアシストを提供してくれます。
特筆すべきは、noteの編集画面から直接呼び出せる手軽さにあるでしょう。
外部のAIライティングツールを開く手間が一切なく、執筆の流れを止めずに利用できる点は大きなメリットです。
また、「プレスリリース風に書く」「インタビュー記事にする」といったユニークな機能や、文章のトーンを「丁寧」「フレンドリー」に調整する機能も備わっています。
この便利な機能は、月額500円のnoteプレミアム会員なら月に10回、法人向けのnote pro会員なら月100回まで利用可能。
日々の創作活動でアイデア出しや表現に悩むクリエイターにとって、執筆のハードルを下げてくれる心強い相棒といえる存在です。
AIライティングツールに関するよくある質問
AIライティングツールの導入を検討する際、「本当にSEOに強い記事が書けるのか」「料金は高額ではないか」といった疑問や不安を持つのは自然なことです。
特に、生成された文章の著作権の扱いや、日本語表現の自然さについては、多くの方が気になるポイントでしょう。
こうした疑問点をあらかじめ解消しておくことが、あなたに最適なツール選びの第一歩となります。
なぜなら、AIによる文章生成はまだ発展途上の技術であり、その実力や限界について未知の部分が多いと感じる方が少なくないからです。
過去の機械翻訳のような不自然な文章を想像してしまい、品質に対して懐疑的になるのも無理はありません。
また、専門的なツールというイメージが先行し、利用へのハードルを高く感じてしまうケースもあるでしょう。
例えば、著作権の問題については、多くのツールが商用利用を認めており、利用規約でその範囲を明記しています。
料金に関しても、月額数千円から始められるプランや、使用した分だけ支払う従量課金制など、様々な選択肢が存在するのが現状です。
まずは無料トライアルなどを活用し、実際の性能を確かめてみることをおすすめします。
AIライティングツールの文章はペナルティになるのか?
AIライティングツールで文章を作成したこと自体が、直ちにGoogleからペナルティを受ける原因にはなりません。
Googleは2023年2月に公開した公式ガイダンスにおいて、重要なのはコンテンツの生成方法ではなく、あくまでその品質であると明言しました。
つまり、ユーザーにとって有益で信頼性の高い、独自性のあるコンテンツであれば、AIを利用していても問題視されないという考え方です。
一方で、検索順位の操作だけを目的とした、無意味なキーワードを詰め込んだだけの低品質なコンテンツは、Googleのスパムポリシーに抵触する可能性が極めて高いでしょう。
AIが出力した文章をそのまま使うのではなく、人間によるファクトチェックや、経験・専門性に基づく加筆修正を施し、コンテンツの品質を担保することが不可欠となります。
AIライティングツールの料金はどのくらいか?
AIライティングツールの料金は、無料から月額数万円を超えるものまで多岐にわたります。多くのツールには無料プランやトライアル期間が用意されており、まずは気軽に試してみることが可能です。
例えば「Catchy」では毎月10クレジットまで無料で利用できるため、使用感を確かめるのに最適でしょう。本格的に導入する場合、個人や中小企業向けのプランは月額1万円前後が相場です。「SAKUBUN」のPersonalプランは月額11,000円で提供されています。
一方、大企業向けのプランやAPI連携といった高度な機能を利用する際は月額3万円から10万円以上になることも珍しくありません。契約期間によっても料金は変動し、年契約を選ぶと月額料金が割引されるケースがほとんど。
利用頻度や必要な機能、生成したい文字数などを総合的に考慮して、自身の目的に合った最適なプランを選択することが重要です。
まとめ:おすすめのAIライティングツールで未来の記事作成へ
今回は、自社に最適なAIライティングツールをお探しの方に向けて、
– AIライティングツールの選び方と比較ポイント
– おすすめのAIライティングツール16選
– SEO記事でAIを活用する際の注意点
上記について、解説してきました。
AIライティングツールは、コンテンツ作成の強力な味方になるでしょう。これまで時間のかかっていたリサーチや執筆作業を大幅に効率化できるからです。
しかし、多くのツールが存在するため、どれを選べば良いのか迷ってしまう気持ちもよく分かります。
だからこそ、まずはこの記事で紹介した選び方や比較ポイントを参考にしてください。
その上で、いくつかのツールに絞って無料トライアルなどを活用し、実際に試してみることが大切です。
これまで時間をかけて培ってきたコンテンツ作成の知識や経験は、決して無駄にはなりません。
むしろ、その経験があるからこそ、AIが生成した文章を的確に判断し、読者の心に響くコンテンツへと仕上げられるのです。
AIを優秀なアシスタントとして活用することで、コンテンツ作成はより創造的で楽しい活動に変わっていくでしょう。
単純作業から解放され、企画や戦略といった、より付加価値の高い業務に集中できるようになります。
さあ、この記事を参考に、まずは気になるツールを一つ試してみることから始めてみましょう。
AIという強力なパートナーと共に、あなたのビジネスがさらに飛躍することを筆者は心から願っています。
SEO対策とは?はこちら
SEOの外注(SEO代行)をご検討の方はこちら
SEOコンサルサービスをご検討の方はこちら
SEO対策費用についてはこちら
SEO会社をご検討の方はこちら